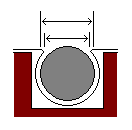去年、ちょっと触れたが、ついに網戸を張り替えた。
理屈としては難しくない。
網戸のフレームには溝が切ってある。フレームに網を置き、上からゴム紐をその溝にはめ込むことで固定する。
そのゴム紐の太さは何種類かあるわけだが、要注意なのは、ゴム紐は溝に
がっぱり嵌っていて周囲を網が覆っている形になるので、フレームに嵌った状態では実際よりも細く見える。まぁ、それがわかるのは、俺が細めの奴を買ってしまったからなのだが。
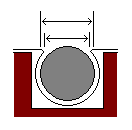
しょうがないので、今まで使ってた紐を再利用した。今のところ、特に問題はない。
早速なので、これを元ネタに一席。
勿論、網戸に相当する俚言はない。
常識的に考えて古いものではなさそうだ。平安時代に端を発する、とか言ったら大分びっくりする。
網戸などを作っている
セイキ グループの
ページによれば、アルミサッシの普及がきっかけ、時期としては 1960 年頃ということになる。
そら俚言はないわなぁ。
ただ、そのページに書かれているように、材料から「
サラン」という呼び方はあったらしい。
だが「網戸」は夏の季語である。
ところで、「網戸」という言葉に疑問を持った人はいないだろうか。俺は持った。窓に戸?
いつもの
大辞林より。
前の文章に戻るのだが、つまり「窓」というのは開口部のことで、そこを閉めるために滑らせたり回転させたりするのが「戸」。アルミも木製も、可動部は「戸」なのだ。
で、窓ではなく、部屋の仕切りになっているのは「障子」。これも
前に取り上げた。
へぇぇ、そうなんだ。
似たようなものとして、「蚊帳」はどうか。
結論から言えば、見当たらない。古いもののはずだが、これも「
窓」「
夢」と同じ種類の、生活に密着していて古いものなのに俚言が生まれなかった単語、だろうか。
「かや」という呼び方は「蚊屋」なんだろうが、「かちょう」って読み方が衰えていったのはなぜだろうな。
蚊帳は昔、母方の祖父母の家にあった。子供はそういうものらしいが、確かに楽しかった。自分の家にはないから珍しいこともあっただろうし、押入れとか机の下にもぐりこむのと同じ、胎内回帰願望の一種だろうか、と思ったりする。
一字延ばして、「蚊遣り」はどうか。蚊取り線香を入れる「蚊遣り豚」くらいにしか残ってない単語だが。「蚊遣り豚」自体が、「残っている」と言っていい単語かどうか、って問題はあるな。
なんで「遣る」のかについては、もともとは殺虫目的ではなく、追い払うためのものだったから、という話がある。
俚言はやはり見当たらず。
あれがなんで豚なのかについては諸説紛々だそうな。
『
蚊遣り豚の謎―近代日本殺虫史考』という本も出ているらしいのでそちらをどうぞ。
網戸がないなら雨戸はどうか。
これは単なる蓋だから古くからあるはずだ。40 年前ってこたぁあるまい。
「
とぼ」という語が関東北部にある。「
とんぼ」「
とぼー」という形もある。
戸の裏に露出している骨組みからトンボを連想したのか、と思ったが、「とばくち」であろう、という解説が見つかった。
北国にないのは、もともと開け閉めしやすいものではないから、凍りついたら閉じ込められてしまうため、という文章を見たが、「
まくりど」「
まぐりど」という形が能登と山形にある。
防虫関係で調べてみると、沖縄の言葉がよく引っかかる。「
サンニン」というのは「月桃
(げっとう)」のことらしいのだが、そもそも、その「月桃」がわからん。
そういや「虫除け」という言葉はあるが、それに相当する「虫を殺す」という意味の言葉はないような気がする。「殺虫」の砕けた奴。やっぱり、虫は「除け」たり「遣っ」たりするものだったんだろうか。
今回の文章を書くためにあちこち調べていて、「やっぱり日本の夏は、蚊取り線香に浴衣だよね」という文章がやたらと目に付いた。
が、キンチョーの
ページにあるように、蚊取り線香の原料だった除虫菊が日本に入ったのは明治時代、やっと 120 年経ったところである。別に、そのキャッチフレーズにケチをつけるつもりはないが、日本古来のものだという認識は間違い。
まして、「蚊取り線香に浴衣」というのがノスタルジックで観念的なものに過ぎないだろ、ということは指摘しておく。日本の夏を本当にそれで乗り切れる人が一体、どれだけいるものやら。
網戸の網は、
てぼっけ (不器用) な俺でもピンと張れた。目が曲がっている、という気はするが、意外に簡単という印象を持った。ゴム紐を嵌め込むのにちょっと力が要るが、躊躇している方はすぐにでもやってみるとよい。