| 目 次 1. 本との出会い 2. 本の概要 3. 本の目次 4. 内容要約 5. 著者紹介 6. 読後感 |
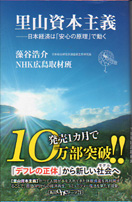 藻谷浩介・ NHK広島取材班共著 角川Oneテーマ21(新書) |
「本の紹介6」に戻る トップページに戻る 総目次に戻る |
| 目 次 1. 本との出会い 2. 本の概要 3. 本の目次 4. 内容要約 5. 著者紹介 6. 読後感 |
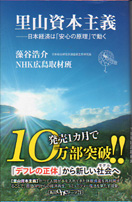 藻谷浩介・ NHK広島取材班共著 角川Oneテーマ21(新書) |
「本の紹介6」に戻る トップページに戻る 総目次に戻る |
1. 本との出会い
NMCの読書会とV Age Clubの新書を読む会で採り上げ、良い本だと思いました。ホームページに載せて、多くの方々に読んでいただき、具体化する上での問題点を考えて行きたいと思っています。
2. 本の概要
東日本大震災を契機に従来の生活を見直し、かって人間が手に入れてきた休眠資産を再利用することで、金のかからない生活を送り、コミュニティーの復活を目指していこうと提案しています。
3. 本の目次
はじめに──「里山資本主義」のススメ………………………………………… 3
第1章 世界経済の最先端、中国山地
──原価ゼロ円からの経済再生、地域復活………………………… 27
第2章 21世紀先進国はオーストリア
──ユーロ危機と無縁だった国の秘密……………………………… 64
中間総括 「里山資本主義」の極意
──マネーに依存しないサブシステム……………………………… 117
第3章 グローバル経済からの奴隷解放
──費用と人手をかけた田舎の商売の成功…………………………155
第4章 “無縁社会”の克服
──福祉先進国も学ぶ“過疎の町”の智恵………………………… 204
第5章 「マッチョな20世紀」から「しなやかな21世紀」へ
──課題先進国を救う里山モデル……………………………………232
最終総括 「里山資本主義」で不安・不満・不信に訣別を
──日本の本当の危機・少子化への解決策……………………… 251
おわりに──里山資本主義の爽やかな風が吹き抜ける、2060年の日本……298
あとがき………………………………………………………… ………………305
4. 内容要約
はじめに──「里山資本主義」のススメ (NHK広島取材班・井上恭介)
「経済100年の常識」を破る
「経済の常識」に翻弄されている人 もっと稼がねば、もっと高い評価を得たいと猛烈に働いている。帰って寝るだけの生活。食糧・下着などはすべて買ってくる。猛烈に働いている割には、豊かな暮らしを送っていない。
発想を転換して豊かな暮らしをする。石油缶を改造した「エコストーブ」を作り、そこに釜や鍋をのせて食事の仕度をする。裏山で拾って来た雑木を燃料にする。畑を借りて野菜を作る。食事がおいしくなる。グローバルな経済システムに組み込まれ、あきらめていた支出を減らして豊かな生活をする。
発想の原点は「マネー資本主義」
ドルが金と交換できなくなる。ビッグスリーが凋落する。収入の無い人にも車を売りつける。ローンを組んで、ローン債券を組み合わせ、数学的な加工をして金融商品が作られる。リーマンショックが起きる。
「弱ってしまった国」がマネーの餌食になった
かたぎの経済に変える。
年金の仕組み
ユーロ危機とギリシャ
晴耕雨読 → 里山資本主義
「マッチョな経済」からの解放
東日本大震災のあとに芽生えた新しい発想
「元気で陽気な田舎のおじさんたち」
メッセージが浮き上がったカボチャ
エコストーブ
里山資本主義は価値観の転換である。
世の中の先端は、もはや田舎の方が走っている
東日本大震災から半年たった2011年の夏の終わり。NHK広島で始まった「里山資本主義」の番組作りの推進役を、藻谷浩介さんにお願いした。氏は全国の市町村ほとんど全部を歩いている。
この本のポイント
次の3点に要約される。
1. 木材チップ燃料(エネルギー革命)
2. CLT(クロス・ラミネイテッド・ティンバー 集合材)
3. 価値観の転換─豊かな暮らしとは─過疎を逆手にとる上の3点について、少し詳しく説明する。
5. 著者紹介
1. 木材チップ燃料(エネルギー革命)
エコストーブは石油缶を改造して作り、里山で拾って来た枯れ枝をもやす。
貯蔵、流通まで考えるとチップ化が必要になる。木材加工で従来捨てていた、おがくずや木の切れ端をこまかくし、チップに加工する。過去に植林して来た木が伐採の時期を迎えているので、計画的に伐採・植林を繰り返すことによって、あまりお金をかけないで利用できる。
樹木搬出の林道は、従来の規則では材木を搬出するだけの幅のものは作れない。また専用の大型運搬機械も国産品はなく、輸入品しかない。需要のあるこことがわかれば、国産は可能であると思われる。
これらの問題点を解決する必要がある。オーストリアではチップ化が進んでいるので、見習う必要がある。日本では環境が整っていない。民間でやってみせる。必要性を宣伝する。
植林して育った木を有効に使うことができるが、法的な裏付けも必要と思われる。その過程で杉や桧を花粉症を起こさない樹木に変えて行くことも大切である。
2. CLT(クロス・ラミネイテッド・ティンバー 集合材)
新しい集成材CLTは通常の集成材は、板を繊維方向が平行になるように張り合わせているのに対して、直角になるように互い違いに重ね合わせる。「直角に張り合わせた板」は建築材料としての強度が飛躍的に高まる。
オーストリアではCLTでの建築は9階建てまで認められている。CLTは地震にも強く、耐火試験も行われ、燃えにくいことが確認されている。
3. 価値観の転換─豊かな暮らしとは─過疎を逆手にとる
無名な人の素敵な生き方、今の生活を少しでも前進させる知恵に率直に反応し、取り入れる気質を持つ人は、価値観の転換ができる。田舎にUターン、Iターンしても、単に地元企業で「職」を探すのでなく、お金うんぬんではない豊かさを見つけ出す嗅覚にすぐれている人が望ましい。
地域社会に入り込み、地域社会に秘かにとけ込んで行く若者も豊かさを見つけ出せる。
企業で比較的クリエイティブな仕事をしてきたリタイア組、その中でも、元気でがんばれる75歳までの15年間に思い切って何かに打ち込みたいと考える人も価値観の転換ができる。
藻谷浩介Kousuke Motani
1964年、山口県生まれ。株式会社日本総合研究所調査部主席研究員。株式会社日本政策投資銀行特任顧問。88年東京大学法学部卒、同年日本開発銀行(現、日本政策投資銀行)入行。米国コロンビア大学ビジネススクール留学、日本経済研究所出向などを経ながら、2000年頃より地域振興の各分野で精力的に研究・著作・講演を行う。平成合併前の約3200市町村の99.9%、海外59ヶ国を概ね私費で訪問した経験を持つ。その現場での実見に、人口などの各種統計数字、郷土史を照合して、地域特性を多面的かつ詳細に把握している。09年度にはシンガポール出向の機会を得、地域・日本・世界の将来を複眼的に考察した。10年度より地域企画部地域振興グループ参事役。12年度より現職。政府関係の公職多数。著書『デフレの正体』(角川oneテーマ21)は50万部のベストセラーとなり、生産年齢人口という言葉を定着させ、社会に人口動態の影響を伝えた。他に『実測!ニッポンの地域力』(日本経済新聞出版社)がある。
NHK広島取材班
(日本放送協会広島放送局)
2011年夏、中国山地の異様に元気なおじさんたちの革命的行動に衝撃を受け、藻谷浩介とタッグを組んで「里山資本主義」という言葉を作り、1年半にわたって取材・制作を展開。
井上恭介
リーマンショック前からモンスター化する世界経済の最前線を取材指揮。「マネー資本主義」の限界を見切った直後、東日本大震災に遭遇。その番組を制作するさなか、転勤で広島へ。里山資本主義に出会う。
夜久恭裕
里山経済のみならず、医療・教育から戦争まで、多くの調査報道で知られる報道番組のエキスパート。里山を掘り進めるうち、オーストリアの"大鉱脈"を掘り当てた。
6. 読後感
第1のポイント(木材チップ燃料)では1) 樹木搬出の林道が従来の規則では作れない。 2) 専用の大型運搬機械が輸入品しかない。という2つの問題点があります。オーストリアなど先進国の例を学び、解決して行く必要があります。
第2のポイント(CLT)でも、法規の改正が必要です。
第3のポイント(価値観の転換)では、実績を増やして行くとともに、絶えざるPRが大切です。
このような本を広く読んでもらい、世論を喚起することが大切だと考えています。
「本の紹介6」に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last updated 4/30/2014]