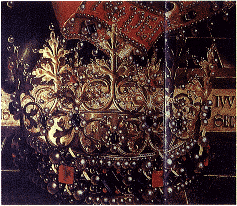
ファン・アイク兄弟『ゲント祭壇画神秘の小羊』部分
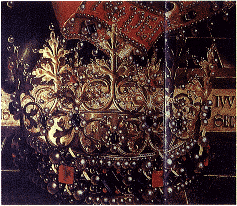
「美術」の目次に戻る
「趣味」の目次に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
目 次
油画は絵具を塗った上にまた絵具を塗り重ねてゆける絵です。油絵具にはその絵具を塗っても、下に描かれているものがその絵具を通して透けて見える色と、見えなくすることができる色とがあるので、油画を描く人はこういう絵具の性質を利用して、ある部分では下の色をかくし、またある部分では下に塗った色をいかしながら絵を描いていくのです。
1. いきさつ
2. 科学の目で見る日本近代絵画の変遷
3. 油画をもっと読むための解説書
1. いきさつ
新日曜美術館(NHK 3CH 日曜日朝9時~10時 夜8時~9時再放送)で、この美術展の紹介がありました。15号台風が来た後、時間がとれたので上野の芸大美術館に行き、ゆったりと勉強することができました。
「油画を読む -高橋由一から黒田清輝の時代へ-」展
解剖された明治の名品たち 特別陳列:金刀比羅宮の高橋由一作品
2001年8月7日(火)~9月24日(月)
東京芸術大学大学美術館
2. 科学の目で見る日本近代絵画の変遷
科学の目で絵画を見たらどうなるか。東京・上野の東京芸術大学・大学美術館で開催中の展覧会「油画を読む」 (9/24日まで)は絵画の秘密の一端に触れると同時に、日本の近代絵画の変遷を知ることができる催しだ。
大学が所蔵する高橋由一、浅井忠、黒田清輝、原田直次郎ら明治期の画家の作品58点のほか、香川県・金刀比羅宮所蔵の6点(いずれも高橋由一作品)の計64点で構成。作品の隣にそのⅩ線写真、赤外線テレビ画像写真、顕微鏡観察した拡大写真などを並べて展示している。
たとえば、高橋の「司馬江漢像」は江戸中期から後期に活躍した画家を真横から描いた絵だが、赤外線を当てると下から若い男性の顔が浮かび上がる。また、代表作「鮭」は現代の描画法と違い、絵の具の粘りを生かした描き方をしていたことが分かる。原田の「老人」は頭部の輪郭線が三回変更されていた。
展覧会は、明治画壇を二分した勢力の絵画技法や技術の違いを科学の目で明らかにしている点でも興味深い。浅井らの明治美術会と、これに対抗した一世代若い黒田を中心としたグループは、画面の色調から前者を「脂(やに)派」、後者を「紫派」「外光派」と称する。脂派の絵は色彩感覚に乏しいものの、溶剤に強く絵肌が美しい。一方紫派の絵は、それほど強くない溶剤にも簡単に溶けてしまうものが多く、油絵本来の絵肌を持つものが少ない。これは現代にも続いている現象だという。
[出典 「文化往来」日経新聞 2001.9.14]
3. 油画をもっと読むための解説書(解説書に載っていた、いくつかの写真は省略しました)
油画とは:東京芸術大学では創立以来油絵コースのことを「西洋画科」と称し、昭和9年より「油画科」と改め、昭和24年から絵画科油画専攻となり現在に至っています。「油画」は、「ゆが」、「あぶらえ」、「あぶらが」等いろいろな読み下し方をされています。
こうして絵具を重ねて仕上がった油画は、絵の前に立った私達が思っているよりもたくさんの色の絵具が使われていることも多いのです。地面の下に重なっている地層と似ていますね。地層を探ると過去の地球の様子がわかりますが、絵の場合も、その絵を描いた人の工夫や失敗が発見できることがあります。
さあ、絵の内部へ探検してみましょう。絵の内部を探るにはどうしたらよいでしょうか。私達は健康診断の時レントゲン写真(X線写真)を撮りますね。絵の場合も同じで、X線や赤外線、紫外線といった光を使って絵を見てゆきます。
油画の断面(写真省略)
「読む」その1. X線写真
みなさんおなじみのレントゲン写真です。X線写真では特に、古くからたくさん使われてきた白い絵具(シルバーホワイト、鉛白といいます)がはっきり写ります。この絵には一人の人物が描かれていますね。
これのX線写真を見ると、どうでしょう、この人の顔の横にもうひとつ顔が見えますね。逆さまになっている人もいます。何人いるか見つけてみてください。同じ人ばかりでしょうか。一枚のカンバスに老人を描いたり、若者を描いたり、それぞれ違ったポーズで描いたりしていることがわかります。最初にいったように油画は重ねて描くことができるので、何度も描きなおして人を描く練習をしたのでしょう。
私は「エクステル」という者です。ちなみに男です。私の下にこんに絵があったなんて自分でもおどろきです。(写真省略) 「読む」その2. 赤外線写真
X線では白い絵具(シルバーホワイト)がどのように使われているかを見ることができましたが、赤外線写真では黒い色(炭素が入ったもの)を見ることができます。
絵を描くとき、すぐに色を塗らずに下描きをすることがよくありますね。絵具の下に隠れている木炭や鉛筆、コンテなどで描かれた下描きの線も見ることができるのです。これによって、下描きの時ポーズをあれこれ変えてみたり、位置を変えたりしたことがわかったりします。また、字が書いてあるのが見つかって、その絵が制作された年や作者などがわかったりすることもあります。この写真では下に別の人物を描いていたことがわかりますね。
わしは「司馬江漢」じゃ。高橋由一さんが描いて下さった。わしのチャームポイントの耳毛とのど毛もちゃんとみてくれ。(写真省略)
「読む」その3. 紫外線写真
下の二つの写真(写真省略)を比べてみて下さい。紫外線写真ではふだんは見えない黒い点々や、ぼおっと青白く光っている所がありますね。この黒い点々は、この絵が描かれた後、時間をおいて改めて絵具を塗った部分なのです。絵は50年くらい経つと傷んできます。絵具がはげてしまうこともあります。そんな部分に修復家は絵具を補います。これを補彩といいますが、この部分が黒く写るので、この絵は過去に修復されたということがわかります。また、青白く光っている部分は、絵の表面を保護するために塗られたワニスです。
「読む」その4.側光線写真(写真省略)
これは今までの三種類の光のように特殊な光を利用したものではなく、通常の光を横からあてて撮った写真なのです。一方向からのみ光をあてているので画面の凹凸がよく見えます。絵が痛んで、でこぼこになっている時は、その状態がよくわかるので、これをもとに修復してゆきます。また、絵具をのせた筆の跡もよくわかりますから、この絵だと顔の向かって左側の明るい部分、特にほお骨や鼻など、出っ張つている所に絵具をたくさん塗っていることがわかります。
では最後に、この展覧会の大きなテーマである明治時代の油画を理解しやすくするために、日本の油画の歴史のお話をしましょう。
日本近代油画の流れ
このページ冒頭にある絵を見て下さい。これは∃ーロッパで描かれた絵ですが、本物そっくりでさわれそうですね。西洋絵画では19世紀に入るまでは、このような写実性、迫真性が求められてきました。当然油画の描き方も材料もその目標にあわせて進歩していったのです。
幕末から明治にかけて、西洋の文化が日本に本格的に入り始めました。西洋の油画を見た人々は、その「そっくり」で「さわれそう」なところに目を奪われたのです。そしてこのような絵を描きたいと思う人も出てきました。高橋由一はその代表的なひとりです。当時は油画を教えてくれる人も少なく、材料も手に入りづらかったので大変でした。由一の作品を見るとなんとか西洋画に迫りたい、という気迫が感じられますね。『鮭』(2001.9の「1 みんなの広場」に掲載)という作品は、由一がそれにかなり成功したことを示しています。油画はただ絵具を重ねてゆけば「そっくり」で「さわれそう」になるわけではありません。下に塗った色を利用して絵具を薄く塗った所や、盛り上がった絵具の厚い所との差をいかして遠近や明暗を合理的に表現してゆくのです。『鮭』の胴体と尾、そして背景の絵具の厚みの差に注目して下さい。背景の暗い色を利用し、明るい所に絵具をのせてゆくこのようなやり方は、西洋画の伝統的な手法です。こういう描き方をした人を日本では、その絵の色みから「脂(やに)派」、「旧派」と呼んでいます。
油画を学ぶために西洋へ留学する人も出てきました。その∃ーロツパでは19世紀に入って新しい絵画の流れが出ていました。印象派の登場です。印象派の画家は光の科学に基づいて絵を描こうとしました。一瞬の光を画面に留めたいという願望は、戸外での手早い制作に対応できる、チューブに入った固練りの絵具が売り出されたことで可能となりました。画面は明るくなり、絵具の塗り重ねや、厚みの差は少なくなっていったのです。
ヨーロッパに留学し、このような新しい流れをくんだ絵を学んだのが黒田清輝ら「新派」の画家でした。印象派の画家達が光の科学的探究を行ったのに対し、「新派」の画家達はもっぱら明るい光溢れる画面づくりに終始しました。彼等が「外光派」と呼ばれるのもそのためです。影に黒や褐色ではなく、紫色を用いましたので「紫派」とも呼ばれました。藤島武二『池畔納涼』、中沢弘光『少婦』に、その特徴がよく表れています。黒田が東京美術学校の西洋画科教授になり、その後の油画の主流は「新派」になってゆきます。
油画の保存修復の面からみれば、西洋の長い油画の伝統にならった「旧派」の技法は耐久性に優れたものでした。それに対し、技法よりも画家の「心持ち」を表現することを重視した「新派」の絵には傷みの激しいものも少なくありません。日本の油画の主流を「新派」が担い、その後の流れがますます画家の主観を重視する傾向を強めていったのは、国も人も近代化してゆくうえで当然のことだったといえるでしょう。ですが、制作のさいに材料との対話、絵の耐久性に対する配慮がなされてこなかったことは、保存修復の立場からみれば残念なことでもあります。 文:作間美智子
レイアウト/デザイン:米倉乙世
監修:歌田眞介
制作:東京芸術大学文化財保存学保存修復油画研究室
[出典 上記パンフレット]
「美術」の目次に戻る
「趣味」の目次に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last Updated 9/29/ 2001]