| 目 次 1. はじめに 2. 演目と配役 3. 解説と見どころ 4. 感 想 |
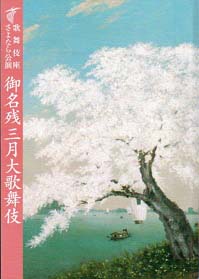 |
「演劇」の目次に戻る 「趣味」の目次に戻る トップページに戻る 総目次に戻る |
| 目 次 1. はじめに 2. 演目と配役 3. 解説と見どころ 4. 感 想 |
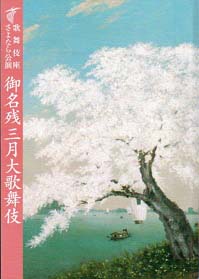 |
「演劇」の目次に戻る 「趣味」の目次に戻る トップページに戻る 総目次に戻る |
1. はじめに
先月(2010年3月)は、「御名残3月大歌舞伎」第1部を見に行きました。歌舞伎座さよなら公演の最後の月を今月(2010年4月)に控え、顔見世興行の感がありました。
出し物は菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)の加茂堤(かもづつみ)、楼門五三桐(さんもんごさんのきり))、女暫(おんなしばらく)の三本で、役者としては吉右衛門、左團次、菊五郎、松緑、玉三郎などです。
2. 演目と配役
1. 加茂堤(かもづつみ) 一幕
桜 丸 梅 玉
万 世 親 王 友右衛門
苅 屋 姫 孝太郎
八 重 時 蔵
2. 楼門五三桐(さんもんごさんのきり) 一幕
大薩摩連中
石川五右衛門 吉右衛門
真 柴 久 吉 菊五郎
3. 女暫(おんなしばらく) 一幕
大薩摩連中
巴 御 前 玉三郎
蒲冠者範頼 我 當
轟 坊 震 斎 松 緑
女 鯰 若 菜 菊之助
成 田 五 郎 左團次
舞台番辰次 吉右衛門
3. 解説と見どころ
【加茂堤】
『菅原伝授手習鑑』は、延享3年(1746)、大坂竹本座で人形浄瑠璃によって初演されました。竹田出雲、三好松洛、並木千柳らによる合作の、 全5段の時代物で、『義経千本桜』、『仮名手本忠臣蔵』と並び、三大名作のひとつとされています。
すでに古浄瑠璃で語られていた菅原道真(菅丞相)の伝記を中心にして、道真に仕える白太夫の子として、三つ子の梅王丸、松王丸、桜丸を登場させるところがこの作品の特徴です。これは、当時、大坂に三つ子が生まれた話題を取り入れたと言われていますが、道真の太宰府流罪という悲劇だけでなく、時の権力により、その三兄弟たちも敵味方に別れ、それぞれ悲劇的な展開となる趣向が、この物語に一層深みを与えています。
初段の中にあたる『加茂堤』は、道真の左遷の発端となる重要な場面です。原作では、最初に三兄弟が登場しますが、歌舞伎では、末子の桜丸だけの登場となります。桜丸は、醍醐天皇の弟の斎世親主に仕える舎人で、斎世親王と道真の養女である苅屋姫の恋仲を取り持つ場面から始まります。穏やかな春景色の中、斎世親王と苅屋姫という若いふたりの淡い恋と、桜丸と八重夫婦の瑞々しい仲が微笑ましく措かれています。
しかし、斎世親王の行方を探す三善清行の登場により、物語の雲行きは次第に怪しくなります。清行から逃れるため斎世親王と苅屋姫は行方知らずとなり、このことが後に道真流罪の原因となり、悲劇が始まります。
前半部の牧歌的な風情と後半部の緊迫感という対比が巧みな構成となっていると言えるでしょう。また、最後の場面において、桜丸の代わりに妻の八重が女性ながらも牛車を引く場面は、八重の見せ場となっています。
【楼門五三桐】
『楼門五三桐』は安永7年(1778)4月、大坂中の芝居で初演されました。
太閤秀吉に逆らい、釜煎りの刑に処せられたと言われる大泥棒の石川五右衛門は庶民の絶大な人気を得、彼を主人公にした物語が数多く生まれました。並木五瓶によって書かれたこの作品もそうしたもののひとつです。
原作は全五幕の長編で、その中の一場面が、五右衛門と真柴久吉が対峠する南禅寺山門の場面です。
武智(明智)光秀の養育を受けて育った五右衛門は、光秀の仇である久吉へ復讐をする機会を窺っています。一方、久吉の長男久次の後見役である此村大炊之助は、真柴家の後継者争いに乗じて天下転覆を企みますが、事が露見して命を落とします。この大炊之助こそ、祖国明国のために久吉に恨みを晴らさんとする宋蘇卿(そうそけい)という明の皇帝に仕える重臣でした。宋蘇卿は死に臨んで、幼い頃に別れた息子に我が無念を伝えるため、絵から抜け出た鷹に遺書を託します。その遺書を受け取った五右衛門こそ、宋蘇卿の息子で、父の死と我が素性を知るというのがこの場面なのです。
スケールの大きい物語に相応しく、勇壮な大薩摩の演奏の後、浅黄幕が振り落とされると、桜の咲き誇る中、豪華絢欄な南禅寺の山門となります。ここでの五右衛門の「絶景かな、絶景かな」と始まる有名な台詞は聞きどころのひとつ。
やがて、山門がせり上がりますが、これは大道具の見せ場。続いて、金欄地のどてら姿に大百日という蔓の五右衛門の姿とは対照的な巡礼姿の真柴久吉が現れます。
短い一幕ですが、歌舞伎ならではの色彩美と様式美満載の大舞台をお楽しみ下さい。
【女暫】
この作品は、歌舞伎十八番のひとつ『暫』を、女方が演じるところに、その趣向と面白さがあります。延享2年(1745)11月に江戸市村座で上演された『婦楠親[偏は音]粧鑑(おんなくすのきよそおいかがみ)』で、二世芳沢あやめが楠女房菊水の役を演じたのが最初だと言われています。しかし、その後、上演が途絶えていたのを、明治34年(1901)11月に市村座で五世中村歌右衛門(当時・五世芝翫)が巴御前の役名で復活上演して以来、上演を繰り返しています。
この作品の元となった『暫』は、横暴を極める「公家悪」と呼ばれる悪役が、善人方の首を刎ねようとするところ、「暫く」と声をかけて強力無双の勇者が登場、「ツラネ」という雄弁術を聞かせた後、悪人たちをやりこめるという筋立てで、祝祭劇的要素が強く、顔見世では必ず、この『暫』の趣向を用いた場面を上演して、1年間の繁栄を祈念しました。『女暫』もこれと同様で、祝祭劇としての華やかさは勿論のこと、歌舞伎の色彩美、様式美を大いに楽しむことの出来る作品です。
北野天満宮で蒲冠者範頼の命を受けた成田五郎ら、「腹出し」と呼ばれる赤っ面の敵役たちに、清水冠者義高や紅梅姫が首を打たれようとするところ、「暫く」と声が掛かり、柿色の素襖姿の巴御前が登場します。花道での巴御前のつらねは、聴きどころであると共に、見どころのひとつ。これに続いて、女鯰や鯰坊主たちとの滑稽なやり取りを見せた後、本舞台へと向かった巴御前は善人方を救い、大太刀を用いて打ちかかる仕丁の首を刎ねます。女ながらに大力の持ち主という奇想天外な設定の下、荒事に必要な華やかさと大きさを見せると共に、女方としての色気と艶をも保つのが、巴御前という役柄の特徴となります。
悪人たちを退けた巴御前の引っ込みが、眼目のひとつで、舞台番から六方を習い、その様子を見せた後、女方らしい恥じらいを見せて花道を入ります。
桜の咲きほこる華やかな舞台をお楽しみ下さい。
(出典 歌舞伎座発行のプログラム[平成22年3月])
4. 感 想
1年前に見た公演(2009.1)は正月だったせいか良かったのですが、今回は工事開始直前ということで、3部構成にしたためか、1幕の時間があまりにも少なくなりました。第3幕は1時間以上あったものの、第1幕と第2幕は15分程度という短さです。舞台装置の豪華さなどで歌舞伎座を見に来た人にはこれで良いのかもしれませんが、演技または役者を見に来るひとには、いかにも中途半端です。工事が終わる3年くらいの間は、歌舞伎からは遠ざかるしかないのかも知れません。
「演劇」の目次に戻る
「趣味」の目次に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last Updated 4/30/2010]