目 次 1. いきさつ 2. ものがたり 3. さし絵 4. 作者紹介 5. 訳者あとがき 6. 読後感 |
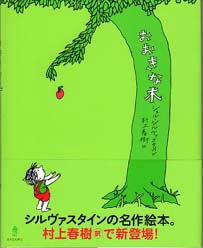 作者 シェル・シルヴァスタイン 訳者 村上春樹 発行所 あすなろ書房 |
本の紹介(絵本)に戻る 村上 春樹に戻る トップページに戻る 総目次に戻る |
目 次 1. いきさつ 2. ものがたり 3. さし絵 4. 作者紹介 5. 訳者あとがき 6. 読後感 |
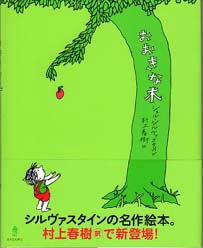 作者 シェル・シルヴァスタイン 訳者 村上春樹 発行所 あすなろ書房 |
本の紹介(絵本)に戻る 村上 春樹に戻る トップページに戻る 総目次に戻る |
1. いきさつ
この本は長い間読まれてきたものが、村上春樹さんの新訳で新たに発売されたことを、新聞記事で知りました。早速購入して読んでみました。ストーリーはいろいろな読み方ができるようです。早速、取り上げることにしました。
2. ものがたり
あるところに、いっぽんの木がありました。
その木は ひとりの少年のことが だいすきでした。
少年はまいにち その木の下にやってきました。
はっぱを いっぱいあつめ、はっぱで かんむりをつくり、木のぼりをし、えだにぶるさがってあそびました。
そしてりんごをたべました。(この木は、リンゴの木だったのですね)
「かくれんぼ」をしたり、くたびれると こかげでねむり、その木がだいすきでした。
だれよりもなによりも、木はしあわせでした。
でもじかんがながれます。(少年は成長して青年になります)
少年はだんだんおおきくなっていきます。(かのじょができます)
木がひとりぼっちになることがおおくなります。
このあと少年は3回、木のところにやってきて、まずお金、次に家、さいごにとおくにたびするための船をほしがります。木は、まずリンゴ、次に枝、さいごにみきを少年にあたえます。そのたびに、木はしあわせになります。
ずいぶんながいじかんがながれ、少年はもどってきました。木がなにもないことのいいわけをすると、少年はなにもできなくなったとこたえます。
「ぼくはもう、とくになにもひつようとはしない」と少年はいいました。
「こしをおろしてやすめる、しずかなばしょがあればそれでいいんだ。ずいぶんつかれてしまった」
「それなら」と木はいいました。そして できるだけしゃんと、まっすぐにからだをのばしました。
「ふるい切りかぶなら、こしをおろして やすむにはぴったりよ。 いらっしゃい、ぼうや、わたしにおすわりなさい。 すわって、ゆっくりおやすみなさい」
少年はそこにこしをおろしました。
それで木はしあわせでした。
おしまい3. さし絵
4. 作者紹介
少年はまいにち その木の下にやってきました。
少年はだんだんおおきくなっていきます。(かのじょができます)
少年はそこにこしをおろしました。
おしまい
シェル・シルヴァスタイン Shel Silverstein
1930年、アメリカ・シカゴ生まれ。イリノイ大学、ローズヴェルト大学などで学ぶ。絵本作家として有名だが、ソングライター、漫画家、詩人として、多岐にわたり活躍。著書に「ぼくを探しに」「歩道の終わるところ」(共に講談社) など多数。1999没。
5. 訳者あとがき
絵本「おおきな木」はアメリカで1964年に出版され、それ以来今までに30以上の言語に翻訳され、世界各地で人々の手に取られたロングセラーです。世代から世代へと大事に読み継がれてきたと言ってもいいでしょう。
この本の絵と文章を書いたシェル・シルヴァスタイン(1930−1999)には「ぼくを探しに」(1976)などの子供向けの著作が多くありますが、それ以外にも様々な方面に才能を持った人です。最初は大人向けの漫画家・イラストレーターとして出発したのですが、詩集や戯曲など様々な形式の作品を発表し、また作詞作曲家、ミュージシャンとしても高く評価されています。ヒット・ソングをたくさん手がけ、グラミー賞までとっています。こうなると何が本職なのかわかりませんね。
本人の話によれば、とくに子供向けの本を書くつもりはなかったのですが、出版社の担当編集者に「あなたならぜったいに素晴らしいものが書ける」と励まされ、尻を叩かれ、気乗りしないまま書き始めたそうです。でもそのあとも子供向けの本を書き続けているところをみると、書いているうちに「こういうのを書くのも、向いてるのかもな」と思い直したのかもしれません。その編集者には人を見る目があったようですね。
この「おおきな木」を読まれるとおわかりになると思いますが、シルヴァスタインは決して子供に向けてわかりやすい「お話」を書いているわけではありません。物語は単純だし、やさしい言葉しか使われていませんが、その内容は誰にでも簡単にのみ込めるというものではありません。そこにはできあいの言葉ではすらりと説明することのできない、奥行きのある感情が込められています。美しい感情があり、喜びがあり、希望の発芽があるのと同時に、救いのない悲しみがあり、苦い毒があり、静かなあきらめがあります。それらはいわば、人間の心という硬貨の裏表になったものなのです。
そういう意味では、作者シルヴァスタインは子供向けの本というかたちを借りてはいるけれど、結局のところ誰のためでもなく、自分自身の心にまっすぐ向かってこの物語を書いているのだ、と言ってもいいと思います。大人の視線で、上から見下ろして何かを語っているわけではありません。そしてそのような姿勢が、あくまで結果的にですが、子供たちの心を素直に打つのだと思います(もちろん大人たちが心を打たれてもちっともかまわないのですが)。人の心を本当に強く打つのは多くの場合、言葉ではうまく説明できないものごとなのです。だからこそ、この本は世界中で多くの人々の手に取られ、何度も何度も読み返されてきたのでしょう。
あなたが何歳であれ、できたら何度も何度もこのお話を読み返していただきたいと思います。一度ですんなりと理解し、納得する必要はありません。よくわからなくても、つまらなくても、反撥を感じても、腑に落ちなくてもやもやとしたものがあとに残っても、悲しすぎる、つらすぎると感じても、腹が立っても、とにかく何度も読み返してみて下さい。これまで半世紀近くにわたって、みんながそんな風にこの本を読み継いできたのです。きっと何かがあなたの心に残るはずです。あるいはあとに残るのは木の葉のそよぎだけかもしれません。でもそれだってかまわないのです。
この「おおきな木」は原題を“The Giving Tree”といいます。文字通り訳せば「与える木」です。このりんごの木は最初から最後まで、一人の少年に何かを与え続けます。木は原文では「彼女」と書かれています。つまり女性なのです。だから言葉づかいも女性のものにしました。多くの人はこの木を母性の象徴としてとることでしょう。しかしそれはもちろんひとつの解釈に過ぎません。あなたはそこに違う意味を読み取ることになるかもしれません。それはあるいはあなただけにしかわからない、個人的な意味かもしれません。あなたはこの木に似ているかもしれません。あなたはこの少年に似ているかもしれません。それともひょっとして、両方に似ているかもしれません。あなたは木であり、また少年であるかもしれません。あなたがこの物語の中に何を感じるかは、もちろんあなたの自由です。それをあえて言葉にする必要もありません。そのために物語というものがあるのです。物語は人の心を映す自然の鏡のようなものなのです。
この「おおきな木」はこれまで篠崎書林から本田錦一郎さんの訳で出版されていましたが、翻訳者が物故され、出版社が継続して出版を続けることができなくなったという事情もあり、今回訳をあらためることになりました。長く読み続けられた本なので、混乱を避けるために「おおきな木」という元の題はそのまま使わせていただきました。村上春樹
6. 読後感
2010年5月
目次に戻る
子供向けというより、大人向けの本だと思いました。 どちらかというとさみしい、人生のような気がします。生活が描かれていないからかもしれません。歳をとっても「少年」と書かれているのも気になりました。それでも村上春樹さんの「訳者あとがき」は素晴らしいと思います。これがなければこの本を取り上げたかは疑問です。
本の紹介(絵本)に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last updated 12/31/2010]