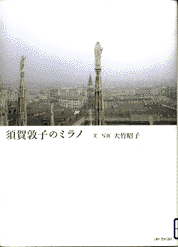
大竹昭子
(株)河出書房新社
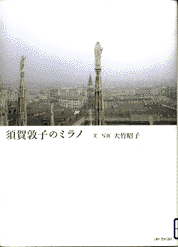
「須賀敦子の目次」に戻る
「本の紹介2」に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
目 次
1. まえおき
2. (本の)目次
3. サン・カルロ書店(写真−元のコルシア書店−別頁)
4. 本文より
5. 著者紹介
6. 須賀敦子略年譜
7. 紹介記事
1.まえおき
4. 本文より
この本は写真家であり、作家である大竹さんが、須賀敦子が住んでいたミラノのムッジェロ街(夫ペッピーノと新婚生活を送った)やコルシア書店(ペッピーノと知り合い共に働いた書店)を始めとする「コルシア書店の仲間たち」「霧のミラノ」の舞台を写真に撮り、作品に出てくる場所を訪れ、感じたことをまとめた本です。須賀さんの本ではないので「本の紹介2」に載せるとともに、「私の愛読書」の『「コルシア書店の仲間たち」ほか須賀敦子』からもアクセスできるようにました。
2. 本の目次
1 電車道 18
2 ムジェッロ街の家 34
3 コルシア書店の日々 50
4 三ッ橋のむこう側 69
5 墓参りの日曜日 85
6 ボンピアーニ一族 99
7 ナヴィリオの環 113
8 ミラノ最後の年 129
須賀敦子略年譜 142
はじめて『ミラノ霧の風景』を読んだとき、半分以上過ぎたところで「鉄道員の家」という文章にぶつかり、衝撃を受けたのを憶えている。それまでの物語が留学中の出会いや書店の仲間との交流という知的人種を軸にしたものだったので、作者の夫が鉄道員の息子だったという事実に、舞台が反転したような驚きを感じた。
「たしかにあの鉄道線路は、二人の生活のなかを、しつかりと横切っていた。結婚したのは、夫の父が死んですでに十年近かったのに、鉄道員の家族という現実はまだそのなかで確固として生きつづけていた。私自身にとってはおそらく、イタリア人と結婚したという事実よりも、ずっと身近に日常の生活を支配していたように思える」
「鉄道員」という言葉はわれわれ日本人にも重い響きをもっている。モータリゼーションがはじまる以前の時代の空気が、その言葉に凝縮されている。仕事を求めて都会にでてきた人々が鉄道駅にうごめいている風景。石炭をたいて走る蒸気機関車が生き物のようにあえぐ様子。鉄道はレジャーのためではなく、労働力と物資を輸送する手段だった。社会を底から支えている重みが鉄道員の職務全体を彩っていた。
「鉄道員の家」の冒頭に、早朝、鉄道官舎のベッドの中で、坂を上がろうとする貨物列車の車輪の軋みを聞いているシーンがある。
「夢うつつに、聞いている。車輪が軋む。少し前進する。また軋んで、止まる。機関車の音が一瞬、大きく息を吸いこむように強くなり、こんどは行くかな、と思うと、また車輪が軋んで、列車は停まる。車輪の軋みが、まだ暗い部屋いっぱいに広がる。その繰りかえしがさっきからつづいている。もう少し眠っておかなければ、昼間の仕事にさしさわる。そう思っても、車輪の軋みが眠らせてくれない。ときどき、助けでも呼ぶように、列車はヒュウと甲高い汽笛を鳴らす。その音を聞いている自分が、だんだん前進を阻まれた貨物列車のような気持になって、ベッドの中で肩にちからをいれている」
鉄道官舎の前の線路が中央駅にさしかかる最後の上り坂に当たるので、寒い冬の朝はレールが凍り、重い貨物列車の車輪はすべって立ち往生する。レールに砂をまいて空回りを止めようとしてもなかなか効果があがらず、少し前進してはまた軋むというのを繰り返す。
「夫の出張で、姑の家に泊っていることだけでもせつないのに、この音で目覚めてしまうと、なぜか心細さがどつと押しよせてきて、自分が宇宙のなかの小さな一点になってしまったような気持になる」
イタリア人と結婚したという事実より、鉄道員の家族の一員になったことのほうが重みをもっている日常とはどんなものなのか。透明な孤独が幾重にもたたみこまれたこの文章からは、それが静かに伝わってくる。
書店の給料が少なく母の乏しい年金を侵蝕することもあったから、ペッピーノは世間的な意味での大黒柱ではなかったかもしれないが、父親のいない家庭を精神的に支える存在だったことはまちがいない。結婚してまもなく、夫の帰りがおそくて気をもんでいたら、「うっかりしてお母さんのところに帰っちゃった」とてれくさそうに帰ってきたという話がある。実家と新居の距離は、ぼんやりと市電に乗っていたらあっというまに連れていかれてしまいそうなほど近かった。夫は新居に越しても半身くらいは鉄道官舎に残しているような気持ちだっただろうし、妻もそれを当然と考えて、ひんぱんに夫の実家を訪ねて家族に溶け込もうとしただろう。妻の実家は遠い日本だったから、それをはばむものはなにもなかった。
ペッピーノには鉄道員の息子のほかに知識人としての顔があった。ふたりが出会ったとき見えたのはそちらの顔だった。書店にいて仲間のものの考え方や進め方が自分とちがうと思ったとき、「これがイタリアの習慣なのか」とか、「イタリア人はこういうものの考え方をするのか」と了解しただろう。個人のちがいを意識しつつも、それを包んでいる文化的背景を見ようとしたにちがいない。
ところが、鉄道官舎にくるとがらりと変わった。書店のときのように理性的な頭が働かなくなり、部屋の暗さとか、ぐらぐらするテーブルとか、椅子のきしむ音などに気をうばわれる。全身が具体物のさざめきに満たされ、まるでイタリアではなくて「鉄道」という国に来たかのようだ。
結婚は出発であるとともに、これまでの生活との別離だから、どんな結婚もはじめは幸福感と同じ量の不安と孤独がある。須賀の場合はとくにそうだった。家族の反対を押し切って異国ではじめられた結婚であり、夫はイタリア人で、育った環境がちがった。夫の家族にはイタリアの国外に出たことのある人はひとりもいない。夫自身も苦学してようやく大学を出た。一方妻は世界一周旅行の体験を繰り返し話して聞かせる父のいる家庭で育ち、小学校から私立学校に通い、大学院に進み、二度の留学を果たした。
ふたりきりのときは詩や文学という共通言語があったから、このちがいが孤独に結びつくことは少なかっただろう。いや、ちがうことがかえって互いの興味をかきたてたかもしれない。ところが夫の家族に囲まれるとそれが後退し、夫が小説の中の人物のようになってしまうのだ。鉄道官舎にいるとき、須賀は二重、三重の意味で「異邦人」だった。
『トリエステの坂道』「あたらしい家」に、ニーノという電気屋に義弟のアルドの借金を催促されるというエピソードが出てくる。自分の借金でもないものを往来の真ん中でいきなり話題にされて平静を失った「私」は、その晩、夫といさかいを起こす。ニーノみたいな男におどかされるなんてきみらしくない、とふだんは温厚で丁寧な話し方をする夫がニーノのことを「あんなやつ」よばわりする。それを聞いたとたんに、「私」の心はニーノからするりと離れて自らの孤独の中に入っていく。この人たちはみんな幼友だちで、私だけがそこにいない、そう気づいて静かな孤独に包まれる。
孤独に敏感な魂を持った人だった。とくに夫の実家を描いた作品にはそれがより濃いように思えてならない。実際の生活では孤独な影などみじんも見せず朗らかに生きていただろう。新婚時代の書簡には生来の快活さがみなぎっているし、義弟のアルドさん一家も、自分たちとのちがいをまったく感じさせない人だったと語っている。だが作品を書いたとき、「宇宙のなかの小さな一点」のような魂の姿が描きだされたのだった。そこに作家の秘密が隠されている。須賀が描いたのは悲愴な孤独ではない。硬質な輝きをもった恒星のような孤独、人を励ますことのできる力強い決意だ。
[4 三ッ橋のむこう側 P.79〜83]
「夫の実家に私が出入りするようになったのは、私がローマからミラノに移って結婚する十ヵ月ほどまえのことだったが、当時、なによりも私をとまどわせ、それと同時に、他人には知られたくない恥ずかしい秘密のように私を惹きつけたのは、このうす暗い部屋と、その中で暮らしている人たちの意識にのしかかり、いつ熄むとも知れない長雨のように彼らの人格そのものにまでじわじわと浸みわたりながら、あらゆる既成の解釈をかたくなに拒んでいるような、あの「貧しさ」だった。すこしずつ自分がその中に組みこまれていくにつれて、私は彼らが抱えこんでいるその「貧しさ」が、単に金銭的な欠乏によってもたらされたものではなく、つぎつぎとこの家族を襲って、残された彼らから生の意欲まで奪ってしまった不幸に由来する、ほとんど破壊的といってよい精神状態ではないかと思うようになった。この人たちは、水の中で呼吸をとめるようにしてつぎの不幸までを生きのびている。そして、それが、この人たちにとって唯一の可能な現実なのかも知れなかった」 (『トリエステの坂道』「キッチンが変った日」)
この文章には重く複雑な意味が秘められている。一家に漂うのは単に金銭の乏しさがもたらす「貧しさ」ではなく、つぎつぎとこの家族を襲う不幸に生きる意欲を奪われたことに起因する、もっと込みいった「貧しさ」なのだった。
この「貧しさ」は金銭的な貧しさよりずっと悲劇的である。またいつかあの不幸にさらわれるかもしれないと思うと、生きることにおびえてしまう。幸福の瞬間でもそれがくつがえされる恐怖がつねに頭を離れない。長男のマリオが二十一のときに結核で死に、ブルーナも後を追うように翌年亡くなり、ルイージ氏も散歩から帰ると横になるといったきりぽっくり逝ってしまった。残された三人は「彼ら自身の現実そのものと引き替えられたかのような、三人の死そのものを生きつづける」ことになる。生者でありながら死者に半身をとられたような、得るものより失われたものの数を数えて暮らすような生活だった。
そんな家族に須賀敦子が加わった。リッカ家を襲った不幸と無縁の、遠い東洋の国から来た彼女は、生来の明るさを発揮して一家に光をもたらしただろう。彼女が実家に宛てて書いた手紙からは、ペッピーノに元気になってもらおうと一生懸命料理に励むさまが浮かんでくる。こういう料理を作ったら、ペッピーノがおいしいと言って食べてくれた、そんなことまでが楽しそうにこまごまと報告されている。努力が実ってそれまで頭痛薬を手放せなかった夫も、だんだん健康になってきた。まわりからもすっかり明るくなったと驚かれる。リッカ家を覆っていた暗い影がじょじょに薄れていくようなそんな明るい期待を抱いたにちがいない。だが予想は裏切られた。結婚から六年目の六月、ペッピーノは三日ほど患っただけで逝ってしまうのである。
ペッピーノと暮らしたムジェッロ街のアパートメントは、「時間が経っても、家具と家具が呼応しあって、ひとつの家の雰囲気を醸し出す」ということがなく、「荒涼とした廃墟で暮らしているような感じ」から抜けだせなかったという。この言葉に読者として驚かざるをえない。それまでの作品が、訪ねてきた者をすぐに自分の家のようにくつろがせてしまう幸福に満ちた家を想像させるだけに、「荒涼とした廃墟」という言葉に胸を突かれる。
ペッピーノの死後、少しずつものが見えてきた「私」はこう考える。もしかしたらこの荒廃は彼を失ってからのことではなく、「私たちがいっしょに暮らしはじめたときからすでに、ひそやかな毒のように内側から私たちを麻痺させ、私たちの生活を空洞化していたのではなかったか」と。
この言葉は容易にのみこめないほど苦い。
幸福な家庭に、感覚を内側から麻痺させ、生活を空洞化させるような「毒」が染みわたっていた。その「毒」がかつて彼の家族を襲った三人の死に由来するものだと「私」は考える。死者のエネルギーがふたりの住まいを侵し、知らないまに生のエネルギーを奪っていた、そう了解するのだ。ここで重要なことは、現実の生活がどうだったかではない。夫と家族の死をそのように納得し、作品に描いていることに意味がある。
こう考えると、「キッチンが変った日」がこれまでの作品と大きくちがうことに気づく。これまでの作品がすぎさった過去を追憶し、死者の魂を鎮魂するような視点で描かれているのに対し、この作品では筆者ははっきりと生者の側に立っている。人は死者のために生きることはできない。生者のために、生きていこうとする者のために、生きなければならない。そう自らを納得させて、生きるための選択を決意している。夫の死を乗り越え、つぎのステップに踏みだそうとしているときの自己の姿を措いているのがわかる。
[5 墓参りの日曜日 P.90〜95]
日本に帰ることはひとつの選択だったが、ミラノにいてもそれを追求する道があった。それは翻訳ではなく、創作という私的な営みに入っていくこと、かつて書いた「こうちゃん」のような作品をイタリア語で書いていくことだった。ガッティをはじめ、いろいろな人から、きみは自分のものを書くべきだ、と言われていたし、実際にいくつかの作品を書いていたようである。3月28日の日記に作品の名前がイタリア語で列挙されている。だが、それらを読み返した感想は「みな甘えていて幼稚でいやな作品だと思った」。生きすぎた四年のあいだに、自分の中に厳しい批評家が育っていた。
その日、昔の作品を取り出して読んだのは、コルシア書店を手伝っているジャナンドレアの家でクリスティーナという女の子に会ったからだった。クリスティーナが手作りした自作の本を見せてくれ、ふたりは意気投合し、興奮して語り合う。
「日本へ帰って教会の手助けなどするよりこの創作の道を歩きたい思いに駆られる。一年前にCristinaを知っていたら、私は、日本に帰らなかったかも知れない」(「日記」 3月27日)
十代の少女の恐れを知らない行動力に、背中をぽんと押されたような気がしたのだろうか。目の前の壁がすっと低くなり、こちらにおいでと手招きされているように感じたのかもしれない。ジャナンドレアにも「君が日本に帰るのはいいけれど、もう創作しなくなるのが惜しい」と言われ、「Peppinoがいなくなったから一人でたたかわねばならなくなったもので、どうにも余裕がなくなったと話す。だけど創作を忘れないように、云いつづけてね、とたのむ」(同上)。
結局、創作の道は選ばずに日本に帰り、慶応大学国際センターに職を得て、練馬に「エマウスの家」を設立した。「エマウス」は廃品回収業をしてその純益を福祉事業に当てるというフランスではじまったボランティア活動で、須賀は慶応の仕事をしながら、週に四日ほどそこに寝泊まりして若いボランティアを指導した。須賀にとってそれは社会改革運動というより、ヨーロッパに行って以来、ずっと考えつづけていた、人が働きながらともに暮らし祈る、在俗の修道院のようなものの実現だったのではないだろうか。
エマウスの家の責任者は三年ほどで退くが、辞めたときは四十代半ばだった。それから上智大学で教え、イタリア文学の翻訳を手がけ、自分のものが刊行されたのは六十一歳のときで、帰国から二十年ほどたっていた。
須賀敦子の人生は相対的には長いものではないかもしれない。だが、その軌跡をたどつてみると、たくさんの起伏があることに驚かされる。そしてその起伏の多くが彼女自身が選びとってきたもののように思える。自分が「淋しい生き方」をすることをあるときから自覚し、人生のひとつひとつの過程をおろそかにせず、ていねいに生きてきた。絶望のときにも、その先にかならず光があることを生き方をとおして体験的に学んできた。須賀敦子の文学はこのような生き方と切り離して考えることはできないだろう。作品は「虚構」だが、彼女の生き方は「虚構」ではないのだ。
ガルザンティ社の編集部長をしているジャナンドレアを中央駅に近い仕事場にたずねたとき、日記に、「もう創作しなくなるのが惜しい」という彼の言葉が書かれていたことを話すと、彼がこう言ったのが印象に残っている。
「アツコは書ける人だと思ったからそう言ったんだけど、ついに書いたじゃないですか!」
本当に彼の言うとおりだった。時間がかかったが、最後には書いた。書くことをあきらめず、情熱をおき火のようにともして書きつづけた。
ミラノを発つ日、ホテルに泊まって以来朝いちばんにする習慣になっていた、窓の横の紐を引いてシェードを上げる作業をした。シェードは重く、体重の軽い私は足を踏ん張り紐にぶらさがるようにして引っ張らないと上がらない。毎日おこなううちにようやくつかめてきたこつを意識しながら引っ張りあげ、すりガラスの窓を開くと、なにも見えなかった。向かいの建物も、ホテルの玄関の屋根に立っていた旗も見えない。ただ真っ白な四角がそこにあった。
前夜、ホテルの人が、このごろめっきり減ったけど、霧が出ると何も見えなくなって、こわいんだよ。そう身振り手振りで説明してくれた。道の向こうから来る人すら見えない。ぶつかると困るから、わざと足音を大きくたてて歩いたり、口笛をふいたりする。そうやってここにいるよ、とまわりに知らせるんだ。
そんなに奇妙なものなら、こわくても一度見てみたい。そう念じた霧がいま目の前にあった。窓を大きく開けたまま、後ろに下がっていった。両開きのガラス窓の向こうに、別の世界があるようだった。霧が晴れたら、それが見えるかもしれないと思った。
[8 ミラノ最後の年 P.138〜141]
5.著者紹介
大竹昭子[おおたけ・あきこ]
1950年東京生まれ。上智大学文学部卒業。
1979年から81年までニューヨークに滞在、執筆活動を開始するとともに、写真撮影も手がける。
著書に、『透きとおった魚−沖縄南帰行』(文芸春秋)、『眼の狩人−戦後写真家たちが描いた軌跡』(新潮社)、『バリの魂、バリの夢』(講談社文庫)、『東京山の手ハイカラ散歩』(平凡社)、『図鑑少年』(小学館)など。
6. 須賀敦子略年譜
1929 1月19日、兵庫県芦屋市翠ヶ丘に生まれる。
1935(6歳) 夙川に移る。小林聖心女子学院に入学。
1937(8歳) 父の転勤に伴い、東京都麻布本村町に転居。芝白金の聖心女子学院に編入。
1941(12歳) 聖心女子学院高等女学校に入学。
1943(14歳) 疎開で夙川にもどり、小林聖心女子学院に編入。
1945(16歳) 10月、再び東京に移り、聖心女子学院高等専門学校英文科に入学。
1948(19歳) 5月、新設された聖心女子大学外国語学部英語・英文科二年に編入。
1952(23歳) 慶応義塾大学大学院社会学研究科に入学。
1953(24歳) 大学院を中退。9月、パリ大学文学部比較文学科に留学。
1955(26歳) 7月、帰国。日本放送協会国際局欧米部フランス語班に嘱託として勤務。
1958(29歳) 9月、渡伊。ローマのレジナムンデイ大学で学ぶ。
1960(31歳) 7月、ミニコミ誌 「どんぐりのたわごと」創刊。9月、コルシア書店の企画に参加するため、ミラノに転居。
1961(32歳) 11月、ジュゼッペ(ペッピーノ)・リッカと結婚。
1963(34歳) Due amori crudeli(夫と共訳、谷崎潤一郎「春琴抄」「蘆刈」)ボンピアーニ社。
1964(35歳) La montagna Hira(訳、井上靖「比良のシャクナゲ」 「猟銃」 「闘牛」) ボンピアーニ社。以降、庄野潤三、川端康成、安部公房などの作品を次々とイタリア
語に翻訳。
1967(38歳) 6月、夫ペッピーノ、41歳で死去。
1971(42歳) 8月末帰国。慶応義塾大学国際センターに勤務。
1973(44歳) 8月末練馬区に「エマウスの家」設立。責任者となる。
1981(52歳) 慶応義塾大学文学博士号取得。
1982(53歳) 上智大学外国語学部助教授となる。ブルーノ・ムナーリ『木をかこう』訳、至光社。
1984(55歳) 3月から7月まで、ナポリ東洋大学日本文学科講師。ムナーリ『太陽をかこう』訳、至光社。
1985(56歳) ナタリア・ギンズブルグ『ある家族の会話』訳、白水社。
1988(59歳) ギンズブルグ『マンゾーニ家の人々』訳、白水社。
1989(60歳) 上智大学比較文化学部教授となる。
1990(61歳) 『ミラノ 霧の風景』 白水社。
1991(62歳) 上掲書で講談社エッセイ賞、女流文学賞受賞。ギンズブルグ『モンテ・フェルモの丘の家』訳、筑摩書房。アントニオ・タブッキ『インド夜想曲』『遠い水平線』訳、白水社。
1992(63歳) 『コルシア書店の仲間たち』 文芸春秋。
1993(64歳) 『ヴェネツィアの宿』文芸春秋。
1995(66歳) 『トリエステの坂道』みすず書房。タブッキ『島とクジラと女をめぐる断片』訳、青土社。同『逆さまゲーム』訳、白水社。
1996(67歳) 『ユルスナールの靴』河出書房新社。タブッキ『供述によるとベレイラは……』訳、白水社。
1997(68歳) 1月、国立国際医療センターに入院。イタロ・カルヴィーノ『なぜ古典を読むのか』訳、みすず書房。
1998(69歳) 3月20目、心不全で永眠。
『遠い朝の本たち』筑摩書房。『時のかけらたち』青土社。『本に読まれて』中央公論社。『イタリアの詩人たち』青土社。『ウンベルト・サバ詩集』みすず書房。
1999 『地図のない道』 新潮社。
2000 『須賀敦子全集』 (全8巻) 河出書房新社。
2001 『須賀敦子全集』 (別巻) 河出書房新社。
7. 紹介記事
須賀敦子のミラノ 大竹 昭子著
1998年に亡くなった作家・須賀敦子の足跡をイタリアにたどる紀行真集。ミラノは、61歳といっ遅咲きのデビューになったエッセー集『ミラノ 霧の風景』の舞台だ。著者は、残された作品の記述や資料を手がかりに街を歩き、ゆかりの人を訪ねて、「書くことをあきらめず、情熱をおき火のようにともして書きつづけた」故人をしのぶ。
須賀の夫ペッピーノが運営に情熱を注いだコルシア書店は、多くの友人や知人をもたらし、その後の生き方に大きな影響を与えた。「私たちがふつう思い描くような『本を売る』店ではなかった」という書店の雰囲気は、その後、修道会が経営を引き継いだ現在のサン・カルロ書店からも伝わってくる。(河出書房新社・1,800円)
「須賀敦子の目次」に戻る
「本の紹介2」に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last updated 8/1/2001]