芳文社の漫画雑誌「増刊 本当にあった (生) ここだけの話 まるごと県民性 SP」をネタにした文章、後編。
方言について否定的な話もあった。
一つは、よそ者が使う方言に対する不快感。
これは兵庫県。大阪のは前にも書いたことがあるが、やっぱり関西だった。
そうかと思うと、神戸市じゃないのに神戸出身だ、と言ってしまう話とか、尼崎は市外局番が大阪と同じ 06 だから大阪だ、とかちと郷土愛についての一貫性が感じられない。
まぁ、漫画だし、そういう人がいた、というだけで県民性だなんて言うつもりはないけどね。
そういや、神奈川のどっかで 03 のところなかったっけ。
もう一つは、会社に入ったら同郷の人がいて、親しくしてくれたので、あるとき、方言を使って話しかけたら、かっこ悪いからやめろ、と言われた、という話。
これは広島の人だが、このエピソードは、アンチローカルネタというくくりだった。徳島出身だから全員、阿波踊りができるわけじゃない、とか、北海道に引っ越したら帰省するたびに「暑い暑い」という新潟の人、とかそういうのばっかり集めてある。そういうこともあろうよ、という話。
福岡で、魚の話、二つ。
クエという高級魚がいるのだが、これを福岡では「アラ」と言う。魚の端っこで「アラが安い」とかいうと意思疎通ができないどころか、妙なトラブルになりかねないわけ。
で、別に「アラ」っていうアラ属の魚がいるというからさらにややこしい。
Wikipedia によれば、クエを愛知では「マス」と言うらしい。これはこれで紛らわしい。魚の地方名ってなんで同形が多いんだろうな。
三重は「クエマス」だそうだが、それはその紛らわしさを回避するための方策であろうか。
四国の「アオナ」はどうだろう。スーパーの店頭なんかでは「青菜」と間違ったりしないかな。
もう一つ、結婚して最初の正月には、嫁をもらった方の家から、嫁が生まれた家に「ぶり」を送るならわしがあるそうだ。
これは、「あんたんとこの娘はいい嫁ぶりだ」という洒落なのであるらしい。
祭りの話題は意外に多くない。漫画のネタになるってのは笑い方面だから、ってことかもしれない。
そんな中で笑ったのが、陸別町の「しばれフェスティバル」。名前の通り、寒さを楽しむ祭り。こともあろうに二月の厳寒期に、かまくら状の施設の中で暖房無しで一晩を明かす。熱源は、会場の中心に一つだけ設置された焚き火と飲食のみ。オフィシャルには「死なない程度に大自然のパワーを満喫していただきます」とあるからすさまじい。怖いもの見たさで参加してみたいと思ったり思わなかったり。
だって、その「バルーンマンション」って かまくら は、氷点下 15 度以下じゃないと作れないんだってよ。
笑うと言えば、「どんたく」は博多の人にとっては「祭り」じゃなくて「イベントだ」とか、ちと毒っ気のあるエピソードもあった。
「やる」「あげる」「くれる」も地域差がある表現だが、福島の人の投書で、「ください」という依頼を断るときに「くんに」と言う、というのがあった。つまり、「くれない」の変化なのだが、投書者にとっては「気づかない方言」だったようだ。確かに、音便化はしているものの「くれる」は全国共通だから、そういう勘違いをする余地はある。
「施錠する」という意味の「鍵をかう」は前にも取り上げた。「支う」と書き、一応、標準語ではあるのだが、共通語とは言いがたい。この雑誌では、岐阜のエピソードとして取り上げられているが、秋田でも津軽でも言う。
今年話題の字「愛」。
愛媛の漫画で、色々な学校の部活などで作るTシャツやジャージの類に「愛」と大書されていてほほえましいのだそうだ。
直江兼続は日本海側の話だが、ひょっとして愛媛や愛知でも盛り上がってたりする?
「カロム」というゲームがあるらしい。滋賀の彦根での普及率がすばぬけて高い。というか、昔は全国で遊ばれていたのだが、今は彦根にしか残っていない、というのが実情、その理由も不明、というものだそうだ。
因みに、ボード上で指を使ってやるビリヤードって感じである。Wikipedia にも記事はあるし、日本カロム協会という組織も (やっぱり彦根に) あって解説もされている。
漫画では、東京じゃ誰も知らないから自分が一番上手いに違いないと思って友達を誘ったが、という彦根出身者 (漫画家) の話が取り上げられている。
こうなると、もはや地域性でもなんでもなくなってくるが、山口の話。
道路際に、こんな感じで反射テープを張っておく。
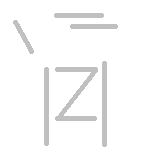
なんじゃそりゃ、って感じだが、夜、これにヘッドライトが当たるとお巡りさんに見える、という話。巧い、と思った。
というわけで、漫画雑誌を二週にわたって取り上げる、ということをしてしまった。
本屋で取り寄せたりできるんだろうか。