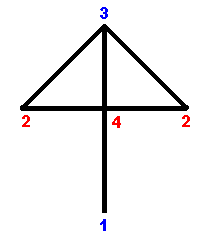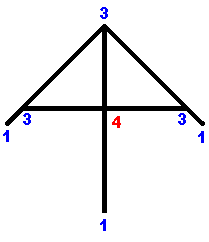ある線画が一筆書きできるかどうかは簡単に判別できる。
点に注目する。線が交差する点と端っこの点。
それぞれの点から出ている線を数える。線が 2 本交差していれば、その交点から出る線は 4、端っこの点なら 1 である。
次に、その中で、出ている線の数が奇数である点を数える。
そういう点を「奇点」と言うのだが、奇点の数が 0 か 2 の線画は一筆書きできる。それ以外だとできない。
これは、「線を引く」という動作を考えればわかる。ある点を出発して線が延びていく。起点は奇点であり、終点も奇点である。
つまりこれが「奇点が 2 の線画」で、一方の奇点から書き始めてもう一方の奇点で終わる。
奇点が 0 というのは、起点と終点が重なって一つの点になっているものと考えることができる。この場合は、どの点から書き始めてもよい。
実例を挙げると、相合傘 (左の絵) は、傘の石突(てっぺん)に当たる点の線が 3 本、持ち手の部分が 1 本で、ほかは 2 本と 4 本なので、石突か持ち手から書き始めればよい。ほかの点から始めたのでは一筆書きはできない。
これが、露先のついた傘 (右) だと、持ち手のほかに露先なども奇点となる。奇点が 6 つにもなってしまい、どこから始めても必ず奇点が残ってしまうので一筆書きはできない。*1
点に注目する。線が交差する点と端っこの点。
それぞれの点から出ている線を数える。線が 2 本交差していれば、その交点から出る線は 4、端っこの点なら 1 である。
次に、その中で、出ている線の数が奇数である点を数える。
そういう点を「奇点」と言うのだが、奇点の数が 0 か 2 の線画は一筆書きできる。それ以外だとできない。
これは、「線を引く」という動作を考えればわかる。ある点を出発して線が延びていく。起点は奇点であり、終点も奇点である。
つまりこれが「奇点が 2 の線画」で、一方の奇点から書き始めてもう一方の奇点で終わる。
奇点が 0 というのは、起点と終点が重なって一つの点になっているものと考えることができる。この場合は、どの点から書き始めてもよい。
実例を挙げると、相合傘 (左の絵) は、傘の石突(てっぺん)に当たる点の線が 3 本、持ち手の部分が 1 本で、ほかは 2 本と 4 本なので、石突か持ち手から書き始めればよい。ほかの点から始めたのでは一筆書きはできない。
これが、露先のついた傘 (右) だと、持ち手のほかに露先なども奇点となる。奇点が 6 つにもなってしまい、どこから始めても必ず奇点が残ってしまうので一筆書きはできない。*1