盆休みも終わろうかという朝の 4 時頃、腹痛で目が覚めた。腹痛とは言いながらなんだか背中の方も痛い。痛みは左側のみ。うつぶせになって左足を曲げてると痛みが和らいできたので、30 分くらいでまた眠りに落ちた。
時期的に酒のみまくりだったので腹痛が起こるのも当然、と思っていたのだが、翌日の 3 時半頃、また目が覚めた。今度は姿勢を変えても楽にならず、それどころか悪化する様子。腹の筋肉が痙攣を起こして、息も苦しくなったりする始末。暮れに胃腸化で貰った、消化器系の痙攣をとめる薬が残っていたのでそれを飲んで様子を見るが、30 分経っても改善せず。救急車呼ぼうかなぁ、でも、近所迷惑だしなぁ、確かサイレン鳴らさないでくれ、って言えばそうしてくれるんだよな、とか考える。
座椅子を低く倒して寝てるのが一番 (比較の問題) 楽だ、ということがわかったのでそうしながら、腹痛の割に便意が来ない、ということに気づく。しかも、痛いことは痛いが、なんか緊急性がないな、という感じもする。これは、でかい病院の救急外来に自分で行くこともできそうだな、と考え、電話帳をめくってたら痛みが和らいできた。それが 5 時。なんだかんだで 1 時間半も苦悶してたことになる。
で、起きたらおおむね収まってたので、翌日が休みだからそこで胃腸科に行くことにして、会社へ。
10 時頃、トイレに行ったら、ほうじ茶が出てきた。血尿である。ここでやっと、尿路結石だ、ということに気づく。仕事中にネットで調べて、明け方に痛むことが多いことなど、どんぴしゃであることを確認。その日は、スポーツドリンクの 2 リットル パックを買って帰った。
翌日、秋田市にはあんまりない泌尿器科を探して診て貰ったところ、左側の、腎臓と膀胱の間に石ハケーン。3mm×5mm というサイズは、十分に自力で出せる、ということで薬貰って帰ってきた。
前にチラッと書いたが、二度目。去年のは、排尿痛があって「ん?」と思いながらビール飲んでて、次にトイレに行ったらいきなり石が出てきてびっくりした。これは笑い話で済むが、今回のはなかなか辛かった。
前置きが長くなったが、ちょっとその辺で調べてみた。もう去年あたりからは、自分のその時々の関心事をよその地域でなんと言うかググってみる、ということでこのページは成り立っている。
当然と言えば当然だが、「尿路結石」に該当する方言は見当たらなかった。ないこともないような気がするが、とりあえずそういうことにしておく。
なので「腹痛」で攻めてみる。
厳密に「腹痛」はないが、「腹を壊す」という系列はいくつか。大阪あたりでは「いわす」と言うようだし、「くわす」という表現も見つかる。
あと、腹痛の表現として、「にがる」というのも。
それにしても、胃が痛いのと腸が痛いのとは、原因も症状も治し方も違うんだが、どっちも「腹が痛い」で片付けられてしまう、というのはすごいと思う。
和英辞典で「腹痛」を引くと間違いなく“stomachache”が出てくるが、これは見ればわかるとおり「胃痛」である。
「結石 and 方言」で調べると、薬草の呼び方が引っかかる。
「キランソウ」という草があって、結石に効くらしいが、これを「いしゃいらず」「いしゃだおし」「いしゃごろし」等と呼ぶらしい。いかにも効きそう。「地獄の釜の蓋」というのも同じことだが、すさまじい名前をつけたものである。
ただ、この辺は、地域にって指す薬草が違うらしい。アロエ*1、ゲンノショウコ、センブリなどが見つかる。
また、魚の骨に熱湯を注ぎ、その汁をすすることも「いしゃごろし」と言う。
さらに、これは英語のことわざだが、一日一個のリンゴは医者を遠ざける (“An apple a day keeps the doctor away”)、とも言う。同様のことわざは中国にもあるそうだ。
「リンゴが赤くなると医者が青くなる」というのもあったが、英語表現が見つからず。これを「柿」とした、日本のことわざもあるらしい。
ほかには、「味噌」「もつ鍋」などが医者の命を狙っている。
ウコンが結石に効く、という記述があるがよく見ると、腎臓とか胆嚢の石らしい。まぁ、腎臓も尿路ではあるが。すっかり、酒を飲むときには手放せなくなってしまったいるのだが、せっせと飲んでみたい。沖縄では「うっちん」と言う由。芸能人の愛称みたいだな。
今回の騒動で、いろいろと知見を広めた。
尿路結石にはビールがいい、というのは嘘だそうである。確かにビールを飲むと尿量が増えるが、あれは飲んだ分が出てるのではなくて、ビールに利尿作用があるかららしい。つまり、体の方が一生懸命に排水しようとした結果で、その後、しばらく出なくなる。その間に濃縮されてしまい、却って結石ができやすくなるんだそうだ。
レントゲンといえば写真だから現像だと思っていたら、乾板をセットするとそのままコンピュータに読み込む、というシステムがあることを知った。医療系のシステムに Windows が使われてるのを見るとやっぱりドキドキする。昨今は、車の内部も Windows らしいのだが。
石ができれば詰まる、ということで単純に理解していたが、それだけではない。石が尿管を圧迫すると、尿管のほうはその反動で収縮するのだ。つまり、
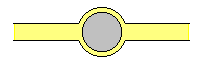
↑ではなく、
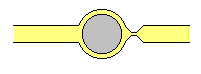
↑なのである。抗痙攣剤を投与するのは、この反動を抑えるためだ。
水分を飲めば出やすくなる、というのは確かだが、上のビールの話でもわかるように、水分なら何でもいい、というわけではない。
一番きついのは、コーヒーがよくない、ということだった。俺、昼間の水分摂取はコーヒーだけなんだけどなぁ。毎日 1 リットル強。
*1
アロエはアフリカ原産で、「アロエ」という単語そのものはオランダ語から来ている。大辞林には「蘆薈(ろかい)」という和名が載っているが、これは「ろえ」だという説あり。 (↑)