
神田明神本殿前

JRお茶の水には営団地下鉄の千代田線も止まるようになりました。JRホームの北側には神田川流れ、千葉寄よりの改札口を出ると川にかかっている聖橋の袂に出ます。橋を渡ると左側に東京医科歯科大学、右側の木立の中に聖堂があります。
ここを始めとして神社仏閣を巡り、最後は東大を経て本郷3丁目に出ます。そこからは営団地下鉄丸の内線に乗るもよし、都営地下鉄大江戸線に乗り上野広小路に出ることもできます。
約2時間の散歩が楽しめます。今年(2001年)の5月に会社の連中と歩いたコースです。
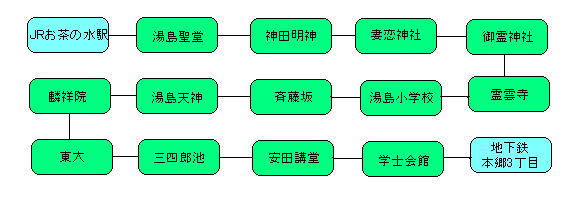
 聖堂 |
1 JRお茶の水駅−湯島聖堂(湯島1-4-25) JRお茶の水ホームの北側には神田川流れ、千葉寄よりの改札口を出ると川にかかっている聖橋の袂に出ます。橋を渡ると右側の木立の中に聖堂があります。 ここには孔子が祀ってあり、人徳門から否壇門(きょうだんもん)を経て大成殿に至ります。いずれも銅葺き屋根以外は黒漆で塗られ、御物であった孔子像を中心に四賢像(顔子、曾子、思子、孟子)を安置した大成殿は日曜祝日のみの開扉されます。 |
 神田明神 |
2 神田明神(外神田2-16) 聖堂の北側の道を渡ると江戸総鎮守の神田明神があります。 随神門から社殿へ、朱に金・緑の色彩が、聖堂の黒と対照的です。5月15日の神田祭には、神輿と人で境内はごったがえします。男坂上にイチョウの老樹があり、江戸に入港してくる船の目印だったそうです。男坂の石段を下ると、あの銭形平次が活躍した明神下で、幕末からの三業地だが、黒板塀に見越しの松の風情はほんのわずか残っています。 |
 妻恋神社 |
3 妻恋神社(湯島2-2)−御霊神社(湯島2-11) 神田明神のさらに北側、太い蔵前橋通りをわたって清水坂を少し登った右側に妻恋神社があります。日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征の折り、三浦半島から房総へわたるとき、大暴風雨に会い、妃(きさき)の弟橘姫(おとたちばなひめ)が身を海に投げて海神を鎮め尊の一行を救いました。途中尊が湯島に滞在したので、郷民は、尊の妃を慕われる心を哀れんで、尊と妃を祭ったのが妻恋神社の起こりと伝えられます。 御霊神社は妻恋神社の北側の道を西に向かった突き当たりにあり、上野から移されたものといわれています。 |
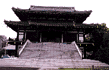 |
4 霊雲寺(湯島2-21-6)−湯島小学校(湯島2-28) 御霊神社の東の通りを北に向かって歩いた突き当たりが霊雲寺です。元禄4年(1691)5代将軍綱吉が創建した寺で、大元堂、灌頂堂、地蔵堂、鐘楼などを備えていました。大震災、戦災で焼失し、再建されました。 霊雲寺のまた北側に湯島小学校があります。 |
 湯島天神 |
5 実盛坂(湯島3-20)−湯島天神(湯島3-30-1) 湯島小学校の手前を東に曲がった先に(斉藤)実盛(さねもり)坂があります。 実盛坂へ行く途中の太い通りを北に向かうと突き当たりに湯島天神があります。イチョウの大木二本に守られた寛文六年(1666)造の表鳥居が迎えてくれます。泉鏡花の新派悲劇「婦(おんな)系図」の舞台で、現代のお蔦(つた)主税(ちから)が登場しても、さまになるのでは、と思える雰囲気が漂います。 天神下、男坂、女坂にはさまれた辺り、古い木造の二階家、三階家がみうけられ、久保田万太郎の家は、その中の一軒です。 |
 麟祥院 |
6 麟祥院(湯島4-1-8) 天神様の境内を北側の湯島切通しに出て、本郷3丁目に向かって3百米ほど歩くと、右側に麟祥院があります。ここには徳川3代目将軍家光の乳母を務めた春日の局(かすがのつぼね)の菩提寺で、卵塔の四方に穴を通した珍しい形の墓があります。われわれが訪ねたとき、ひっそりとして人気がありませんでしたが、静かに参拝する分にはかまわないと思います。 |
 東大赤門 |
7 東大(本郷7-3 三四郎池、山上会館、安田講堂、正門、赤門)−本郷3丁目(都営地下鉄大江戸線または営団地下鉄丸の内線) 切通しをさらに本郷3丁目の方に少し歩くと、元富士警察署があり、その手前を右に折れると突き当たりが東大の弥生門です。 東大の構内の大部分は、寛永の頃から加賀百万石前田家の上屋敷で、10万坪の豪壮な屋敷構えは江戸随一といわれました。屋敷のほぼ中央に心字池(三四郎池)があり、その西側に山上会館が、北の方に安田講堂があり、正門はその西側、赤門は南に下がった所にあり、本郷3丁目はもう目の先です。 |
ウオーキング・旅に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last Updated 3/31/2006]