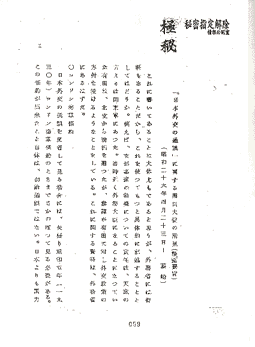
調書(外務省作成)
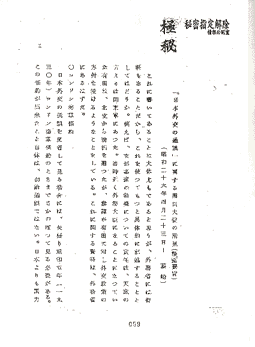
目 次
1. いきさつ
2. 朝日新聞のコラム 窓 論説委員室から
3. 外務省秘密文書03-119「日本外交の過誤」昭和26年4月10日付調書目次
4. 論座 2003.6 朝日新聞社 「日本外交の過誤」の解剖
5. 調査本文
6. 大使・外相の談話・省員の批評
7. 小倉和夫教授の「解剖」(第4項)
8. 総括
0. いきさつ
4月の下旬に朝日新聞のコラムで、この調査資料が公開されたことを知り、早速ホームページを調べました。
その結果外務省の外交資料館(外務省飯倉別館と同一敷地内)にこの資料が保管・公開されていることを知り、早速閲覧しに行きました。
丁度その頃、論座の6月号に小倉氏の論文があることを知り、早速購入しました。それが調査資料で、さらに調書の後半にある二人の大臣と四人の大使と省員のコメントを大変、興味深く読みました。
2. 朝日新聞のコラム 窓 論説委員室から
日本外交の過誤 薬師寺克行(やくしじかつゆき)
吉田茂首相の指示で1951年に作られた外務省の秘密文書が、最近、公開された。「日本外交の過誤(かご)」というタイトルが興味をそそる。
作成の経緯(けいい)がおもしろい。元国連大使の斉藤鎮男(しずお)氏の著書「外交」によると、この年の初め、当時、政務局政務課長だった斎藤氏が突然吉田首相に呼び出された。
首相は「日本外交は満州事変、支那(しな)事変、第二次世界大戦と失敗を重ねた。原因を調べて後世の参考に役立てたい」と、若手課長を中心に報告書を作成するよう指示した。
彼らは多くの先輩(せんぱい)外交官から聞き取り調査をした。出来上がった報告書は大胆(だいたん)な批判にあふれている。
内容を少し紹介(しょうかい)すると、日独伊三国同盟については「都合の悪いことに目をつぶった、現実に立脚(りっきゃく)しない砂上の楼閣(ろうかく)」と言い切っている。
日本軍の仏印(ふついん 現在のベトナムなど)進出は「かえって自分ののど元を締(し)め付け、揚(あ)げ句の果ては元も子も失う戦争に追い込まれた」。
そして、対外政策全体を「対華(たいか)政策の根本が改められない限り、本省や現地の事務当局がどんなに努力しても外交的には無に等しい。枝葉末節の苦心は、単なる自慰(じい)に等しい」と分析した。
安易な前例踏襲(とうしゅう)の誘惑(ゆうわく)をはねつけ、不断に外交政策を検証する知力やエネルギーが今の外務省にあるだろうか。
長い間眠(ねむ)っていた報告書は、幸い、他ならぬ外務省内の若手の間で話題になっているという。
(出典 朝日 2003.4.23 夕刊)
3. 外務省秘密文書03-119「日本外交の過誤」目次
昭和26年4月10日付調書(Pは調書の一連頁番号)]
1. 満州事変、国際連盟脱退……………………………………… P.2
2. 軍縮会議脱退、日独防共協定締結…………………………… P.5
3. 支那事変…………………………………………………………P.10
4. 日独伊三国条約締結……………………………………………P.14
5. 日ソ中立条約締結………………………………………………P.20
6. 仏印進駐、蘭印交渉……………………………………………P.26
7. 日米交渉…………………………………………………………P.31
8. 終戦外交…………………………………………………………P.36
9. 結論………………………………………………………………P.42
附 外交関係重要事件年表
「日本外交の過誤」に関する諸先輩の談話(日付順) 058頁より
1. 堀田大使(P.059〜077)
2. 有田大臣(P.078〜092, P.093〜098)
3. 重光大臣(P.099〜115)
4. 佐藤大使(P.116〜131)
5. 林大使(P.132〜139)
6. 芳沢大使(P.140〜150)
7. 省員の批評(P.151〜159)4. 論座 2003.6 朝日新聞社 「日本外交の過誤」の解剖
小倉和夫(前駐仏大使・青山学院大教授)
調書の解説であり、満州事変から戦後に至る外交上の問題点を順を追って説明している。付録的に次項の本文が掲載されている。
5. 調査本文
「日本外交の過誤」(抜粋)
まえがき(全文)
満州事変以来の対外進出政策は、ついに敗戦という今日の悲運に日本をおとしいれた。何事が起るにも起るだけの原因があるのであり、そしてその起ったことが又原因となって次の結果を生むというような見方からすれば、満州事変の勃発以来、太平洋戦争における敗戦に至るまでの一連の事象も、いわば必然の運命であったとも見られよう。又、その時々の当事者の立場からすれば、当時の情勢の下においては、それがなしうる最善のことであった、それ以外に道はなかったという弁明も成り立つ場合もあろう。しかし、今日の結果からすれば、この期間における日本の対外策は、大局的にいって、作為又は不作為による過誤の連続であったということにならざるをえない。又、今日の悲運は結局避け難かったとしても、一々の事実について今日の眼でこれを見れば、外にやりようがなかったともいい切れない場合が少くない。
このような立場において、満州事変以来日本が歩いて来た道をふり返り、外交的見地から反省して見ることとしたい。
(一)満州事変、国際連盟脱退
(前略)満州事変には、そのよって来るところ遠く、且つ深いものがあったのであるが、さればといって、当時の日本としては、武力進出策に出る以外に生きる道がなかったかといえば、そう断定するだけの根拠はない。むしろ、国内的、特に政治的な要因をしばらく度外視して考えれば、日本が満州を含む中国において英米と競争しつつ平和的に経済進出をすることは、十分可能であったと見るべきであろう。いわゆる幣原外交なるものも、このようなことを前提としてのみ考えられうるものである。(中略)
又、当時の外務当局に事変前の内外情勢の行詰りを打開しようというような積極性が乏しく、又事変勃発後においては、事毎に軍部に反対したが、その根拠が現実から遊離した観念論に終始したことも、反省の余地があるのではなかろうか。口先だけの反対は、その都度現実の力によって押し切られ、そして満州事変そのものだけについていえば、国際的な悪評をこうむりながらも、一つの既成事実をつくることに成功した。そして、国民は、その方について行ったのである。(中略)
又、連盟脱退は、日本が米英と袂をわかつ発端となったが、42票対1票というようなことになっても連盟に止まるというだけのよい意味の図太さがあってよかった。この種の潔癖さは、現実政治には禁物というべきであろう。(二)軍縮会議脱退、日独防共協定締結
日本は、国際連盟脱退後、昭和9年にはワシントン海軍軍縮条約を廃棄し(12月29日)、又、昭和11年には、ロンドンの軍縮会議からも脱退した(1月15日)。両者の国力には大きな懸隔があったのであるから、日本の国力についての現実的考慮からすれば、いずれもまとめた方が有利な話であったはずである。(中略)
防共協定締結の意図は、対ソ牽制にあり、英仏等を対象とするものではなかったが、当時すでにヒトラーのナチスドイツに反感を感じていた諸国が、満州問題も落着せず、北支方面にも着々その手をのばしつつあった日本とかかるドイツとの結合を、その表面の意図のいかんにかかわらず、政治的にいわゆる現状打破派の結合と見なすべきは、当然のことであった。(中略)
当時の外務当局が日独の協定をできるだけ色の薄いものにしようと努めた気持はわかるが、いくら色を薄めたところで、現実の政治的な意味合いには大して変りはない。政治的に重要なのは、協定の文言ではなく、文言のいかんにかかわらず、それが国の内外においてどう受け取られるかということである。まして、ソ連ないし国際共産勢力なるものの脅威は、当時国際的にさほど感ぜられていなかった。(中略)それに反して、日独伊の方が国際的に脅威を感ぜられていたのである。日本が中国に進出するに際しては、よく防共ということを口にしたが、それはいわば口実であり、又、一般にそう認められていた。従って、世界の非共産主義諸国の反共連盟の結成というようなことは、全く夢に過ぎなかったわけである。今日の世界の情勢にかんがみれば、先見の明があったといえないこともないかも知れないが、果してどれだけまじめであったか疑問であり、又たとえ先見の明があったにしたところで、一般に受け入れられなければ、現実的には無意味である。
この協定の締結と併行して、英国との国交調整をも実施するとの方針については、その後この問題は、取り上げられるには取り上げられたが、結局実を結ばなかった。
結局、防共協定の締結は、日本の国際的な孤立を脱却したいという感情を満足させた以外、その対外関係において何等の利益をもたらさなかったといってよい。(三)支那事変
(前略)昭和11年の二二六事件の後成立した広田内閣は、陸軍の華北五省分治工作を抑制しようとはしないで、国交調整を行わんとしたが、それではだめなことは、当然であった。当時、満州と華北の通車通郵等の実現せられた気運に乗じ、分治工作を抑制してかかったならば、当時の国民政府内の情勢から見ても、満州国問題は黙過の形において、国交を調整することも相当可能性があったと思われる。昭和11年末の西安事件の後にも、その可能性はあっただろう。しかし、満州で打切りにして両国の国交を調整するというこの可能性は、結局まじめに追及されないままで、支那事変に突入した。
廬溝橋事件に際して、内地師団派遣の問題があった。それまでの軍のやり方にかんがみれば、事変の拡大を避けるつもりであったならば、派兵には絶対反対すべきであった。(中略)
要するに、日本の中国に対する施策は、表向きはともかく、その実質において、名分の立たないものであった。ために中国民の反感も買えば、諸外国からの非難も受けた。そのやり方も、調子のよいときは調子に乗り過ぎ、止まるべきところで止まることを知らず、一旦調子が悪くなると単なる悪あがきに終った。紙の上では美辞麗句をならべた作文が会議を重ねて練られたが、実行に移され効果を挙げた政策という程のものは何もなかった。外務当局は、実質的には、占領地行政を少しでも緩やかなものにするために、又、軍の尻拭いをするために、限られた範囲で努力するというに止まった。従って、努力したわりに、実効はなかった。
(四)日独伊三国条約締結
(前略)今にして思えば、この独ソ不侵略条約の締結と欧州戦争の勃発は、日本が独伊と袂を分って独自の道に帰るべき絶好の機会であった。それには国際信義の上からいっても十分理由のあることであるが、日本の利益からいえば、少し位無理でもそうすべきであった。
(中略)この条約(引用者注・日独伊三国同盟)の眼目は、締約国の一つが現に欧州戦争若しくは支那事変に参入していない第三国から攻撃された場合には、他の締約国は、あらゆる政治的、経済的及び軍事的方法により相互に援助するということであった。この第三国がさしむき米国を意味していたことは、いうまでもない。
ところで、まず第一に、この条約の締結は、少しでも米国の参戦を牽制する効果があったであろうか。結果から見れば、少くとも、米国は、この条約の締結後、対英援助を控え目にしたというような事実はない。当時、日本では、米国の欧州戦争介入を阻止することが人類の福祉のためだというような高踏的議論が行われた。米国は、結局日本の真珠湾攻撃後、独伊が三国条約の約により対米宣戦したことによって、他働的に戦争に入ったから、米国が他から宣戦されなかった場合、果して、いかなる時機に参戦し、又は参戦しなかったかというようなことは、すべて仮設の議論になるが、戦後に発表された米英側の文献からすれば、米国は、真珠湾攻撃等のことがなくても、いずれは欧州戦争に参加したであろうといい切ってよかろう。米国が日米交渉に応じたのも、話ができたら、欧州戦争に介入する場合の後顧の憂が絶てるというところにねらいがあったと見るべきであろう。
次に、日本の立場からして、どんな利益があつたか。この条約の締結は、もともと、ドイツの戦果の華々しさに幻惑されたことが直接の原因であったと思われる。従って、あまり具体的な目的もなかったかも知れない。(中略)
要するに、三国条約の締結も、百害あって一利なき業であった。(五)日ソ中立条約綿結
(前略)松岡外相は、これに先立つドイツ訪問の際、すでにドイツの対ソ攻撃企図をほぼ承知していた。しかし、彼は、これを止めさせることに最後まで望みをかけ、既定方針通り、中立条約を締結した。この条約の締結によって、彼が近く開始するつもりであった対米交渉を有利にしようという腹であったことは、前にも述べた(モスコウ滞在中に、スタインハート米大使に会ったりしている)。
しかるに、北樺太の利権の解消をコミットしてまで作られたこの条約は、軍部の対米態度を硬化せしめ、従って、結局、むしろ日米交渉の成立を困難にした位のものであった。日米交渉が成立しなかったことから、そういえるというわけではない。その後間もなく、独ソが開戦し、松岡外相の日独伊ソ四国協商の夢もついえていたわけであるから、この四国協商の一支柱としての意味をもたない日ソ中立条約の存在が、米国にとって対日関係上何等の重圧でありうるはずはなかった。又、中立条約の本来の目的について見ても、この条約の存在がソ連の対日宣戦をいくらかでも控えさせ、遅らせたとも考えることはできない。(中略)
日本が対ソ交渉上、いつも劣位に立たされた根本の原因は、日本の米英との関係が悪化の一途をたどつていたことにあったと思われる。ソ連にしてやられるのは、米英と対立関係に入った日本の宿命であったといえよう。それにしても、これ程まで乗ぜられたということには、ソ連という国家に対する根本の認識の甘さもあずかっている。これは、ソ連による中立条約廃棄通告の受け取り方とそれ以後における日本の対ソ折衝にもうかがわれる。(後略)
(六)仏印進駐、蘭印交渉
(前略)今日からすれば、戦争を前提としない限り、南方に平和的に経済的、政治的進出をとげる機会は、当時多分にあったと思われる。仏印とは、経済交渉が成立していたし、タイ仏印国境紛争調停にも成功していた。蘭印交渉もできるだけのところで話合いをつければよかった。ドイツの欧州大陸における優勢を利用して南方へ無理な進出をしようとしたばかりに、かえってのど元をしめつけられるようなことになり、あげくの果ては、元も子もなくするような戦争に追い込まれた。これも、ひつきょう、大東亜共栄圏の夢におぼれて、米(当時は参戦はしていなかったが)、英、蘭等の戦意、底力を過少評価し、情勢判断を根本的に誤ったがためであるといえよう。(七)日米交渉
(前略)日米交渉なるものは、当初から決裂に至る半歳余の折衝において、双方の主張が根本的に何等かの歩み寄りを示さなかった点において特徴的であった。日本の方には(イ)三国条約の解釈、(ロ)在支日本軍駐留問題、(ハ)通商上の無差別原則の根本的な三間題について、実質的な譲歩する腹は毛頭なかったし、米国の態度もインフレクシブルで、数個の原則を固執するに終止した。今日からすれば、あの際日本は難きを忍んで譲歩すべきであったという論もできるであろう。右の三間題の如きは、日米交渉を本当に成立させる気であったら当然先方の主張を容れる覚悟でかかるべきであった。又、日本国内の情勢を離れて考えれば、これらの点で譲歩しても、交渉を成立させた方が有利であったことは、いうまでもない。近衛首相は、ロウズヴェルトとの会談を実現し、何とか交渉を成立せしめたいというところから、米国側のいわゆる国際関係に関する四原則(領土保全と主権の尊重、内政不干渉、通商上の機会均等、平和的手段以外による太平洋の現状不変更)を一たびは無条件に承認するところまで行ったが、これも後から日本側で制限をつけたりした。
そこで、一体、あの際日米交渉を開始することがアドヴァイザブルであったかどうか、ということが問題になる。当時は、支那事変に関連する日米間の懸案が山積していたが、まず、これらの懸案を少しずつでも解決して行って、交渉に少しでも有利なふんい気をじょう成するに努むべきではなかったか。又、米国が満州事変以来反対し続けて来た東亜の事態を大体そのままう呑みにさせることになるような条件で交渉を成立させようというのは、余りに甘い考がえ方で、本当に交渉を成立させるつもりであったら、相当実質的な譲歩もする用意がなければならないはずであった。この点について、まず国内を固めてから、交渉に乗り出すべきではなかったろうか。
もう一歩突さ込んでいえば、そこまでの用意ができなければ、むしろ全然交渉を試みない方がよかったということにもなるであろう。(後略)
(八)終戦外交(略)結論(全文)
何事によらず後から批判することは、やさしい。既往を反省し、そこから将来に対する教訓を汲みとって、初めて批判の意味もある。このような見地から、外交の事に当る者が常に反省しなければならないところとして、次の諸点を挙げることができよう。
(イ)第一に挙げるべきことは、当然のことではあるが、すべて根本が大切であるということである。外交は、単なる技術ではない。内政を離れて外交を考えることはできない。経世家としての気構えを必要とするゆえんである。条約等の字句については、細心の注意を払うことは当然必要であるが、それだけにとらわれて、政治的な意義、影響というような根本のことを忘れてはならない。対華政策の根本が改められない限り、本省や現地の事務当局がいかに努力して見ても、外交的には無にひとしい。軍というものが存在していた以上、当時としては、それ以上のことはできなかったにしても、根本に誤りがある場合には、枝葉末節の苦心は、単なる自慰に終る外ない。
(ロ) 第二に、常に物事を現実的に考えなければならないということである。これは、いろいろの意味で考えられよう。まず、感情におぼれてはいけないということも、その一つである。当時の日本の指導勢力は、数百年にわたるアングロ・サクソンの世界支配体制の覆滅というような夢を抱いていた。ドイツと結んでこれを実現すべき千載の好機を逸してはならないと考えた。これは、人種的な偏見とか、持たざる国の立場とかからして、感情的にはうなずけるところのものをもっていた。
しかし、夢を追うて現実を忘れ、理性を失ったために誇大妄想に陥ってしまった。情勢判断の眼は、希望的思考でくもらされた。
又、フレクシビリティということが大切であるという意味にも考えられよう。ソ連を日独伊三国側に抱き込むという夢が独ソ開戦によって破れた以上、これを前提とした外交政策は、一切御破算とすべきであった。日独伊三国条約を御破算にしていたら、日米交渉にも本気にかかれたであろう。しかし、満州事変以来の日本外交は、動脈硬化症にかかっていた。行懸りにこだわることの禁物なゆえんである。もっとも、このことは、国家としての言動の一貫性を無用とするわけではない。国際社会の通念として認られている程度の道義性は、国際信用をかちうる上に絶対必要なものである。国際連盟その他で言明したことがその後事実の上で覆されたことがいかに日本の対外信用を傷けたかを思い出す。さらに、現実的ということは、形式主義を排するという意味にも考えられよう。何でもすぐ議定書や条約の形にし、宣言を出したりしたがった傾きがある。前に挙げたいろいろな条約を締結して、目先の利益だけでも日本にもたらしたものがあっただろうか。ただ、われとわが手をしばる結果におちいっただけではないか。一体、政治的な意味合いの条約等は、それ自身としては余り意味のないものである。客観情勢が変ってしまえば、少くとも実質上、一片の反古にされる。程度の差こそあれ、これは、何もソ連を相手とする条約に限ったことではない。米英仏等には、ディーセントなところがあるが、結局それだけのことである。日ソ中立条約などは、いよいよとなったら、ソ連の方から真剣に提議して来たであろう。北樺太の買収位は、お土産につけたかも知れない。よい意味の実利主義をとるべきゆえんである。
実利主義ということからいえば、戦争をすることは、いつの場合でも損になるに決っている。少くとも、現代においてはそうである。まして、国力不相応の戦争を自らはじめるにおいてをやだ。およそ重要な政策を決定するについては、何等かのチャンスをとるということは附きものであろう。チャンスをとる勇気がなかったら、外交上でも、本当の成功はつかめないともいえよう。しかし、そのチャンスはあくまで現実的に合理性のあるチャンスでなければならない。かりに、あの際日本が隠忍自重して、戦争に入っていなかったと仮定したら、どうだろうか。戦争を前提とするからこそ、石油も足りない、屑鉄も足りない。ジリ貧だということになる。戦争さえしなければ、生きて行くに不足はなかったはずである。又、米国は、早晩欧州戦争に介入すべき運命にあったとすれば、その後だったら、日米交渉もできたかも知れない(もっとも、それも、日本が戦争は絶対しないという建前で行っての話であるが)。この点については、そうしていたら、日本は、戦争終了後において国際的な孤立に陥り、ひどい目にあったであろうという論もありうるだろう。しかし、スペインの如きは、現に米英側からだんだん接近して行っている。ソ連という国際関係におけるパブリック・エネミー・ナンバー・ワンが現れたからである。日本の場合にも、そうなりえなかったという理由はない。いずれにせよ、この方のチャンスがより合理的であったことは確かである。
外交については、よく見透しのきくことの重要性が指摘される。しかし、実際問題として、そう先々のことまで一々具体的に見透せるものではなかろう。要は、現実を現実的に把握し、これによって身の処し方を決めるということが、結果において見透しがよかったということになるのであろう。物事を現実的、具体的に考えれば、米英の経済力、国力も正当に評価しえたであろう。そうすれば、独伊と結んで日本独自の経済圏をつくりだそうというようなことは、現実性のない夢に過ぎないことも、明らかだったはずである。(ハ)いたずらに焦ることも禁物であるが、機会をつかむには敏でなければならない。太平洋戦争前に外交的転換をとげる機会を逸し、ソ連の参戦前に終戦の機会を逸したこと等は、反対の例である。外交的に一大転換をしなければならない、できるだけ早く終戦にもって行かなければならないと常に念じていたとしたら、もっとこれらの機会を政治的に利用する道があったはずである。もっとも、これは、分っていてやり切れなかったのかも知れない。
(ニ)そこで最後に、決断力と実行力の重要性ということになる。行懸りにとらわれていたら、見切りをつけるべきところで見切りをつけそこなう。そして、ますます深味(ママ)に入って行く。満州事変以来の日本の行き方がそうであり、又、外務省の身の処し方がやはりそうだった。
当時の日本においては、軍の権力が圧倒的に強かったという特異の事情があったことは認めなければならない。しかし、それも程度の問題で、それだけでは、すまされない。一国の外交の衝に当る者には、常に果断と真の勇気の必要なことは、いつの世でも同じであろう。世間的には不景気で評判の悪いようなことでも、あえて責をとって行う気がいの必要なことは、日露の講和の例にも明かである。
外務大臣がやめる腹さえ決めたら、もっと何とかなっただろう、少くとも一時的にもせよ事態の進行を喰い止めえたであろうと思われる場合が少くない。それでも結局は大勢を如何ともできなかったであろうということは、当事者の弁解として成立たない。当時の内閣制度の下においては、一人の大臣ががんばれば、内閣の総辞職を余儀なくせしめることができたのである。重大事に当っては、何でも彼でも穏便におさめるという必要はない。
6. 大使・外相の談話・省員の批評
6.1 堀田大使
ロンドン海軍条約を機に統帥権問題が起こり、軍部の横暴の端緒が開かれた。他にも満州事変、軍縮条約脱退、日独伊三国協定などにも鋭い所見が述べられている。
6.2 有田大臣
外務省は内政的基盤を持っていなかったことが非常な弱みであった。軍は金も組織(在郷軍人会)も御用学者も大分持っていた。6.3 重光大臣
その時々の当事者は、真剣に血みどろの闘いをして来たのだから、これを批評するのは難しいが、自分一個の批評はできるだろう。と前置きして次のように述べておられる。大東亜戦争が勃発したとき対支政策を改めるべきではないかということで力説したが、採用されなかった。
6.4 佐藤大使
満州事変の収拾を提案したのを、大臣が替わって具体的な対処をしないうちに、蘆溝橋事件が起こってしまった。
6.5 林久治郎大使
満州事変の勃発する直前に自分はに帰って来て、満州の事態がただならぬことを説いて廻ったが、どうも皆ピンと来ない様子だった。(中略) 政府が金を出す、つまり予算を通しさえしなければ、軍事行動が出来なくなる。現に満洲事変の当初、軍は金に困っていた。満鉄から三百万円借りたりした。これを政府も黙認している。満州事変を止めたかったら、なぜ金を出すことを拒まなかったのか。又軍の過激派の主な者を何人か馘にしたら、軍を反省させることもできたはずである。
6.6 芳沢大使
ここに書いてあることには大体同意見で、結構だと思う。何事もそうだが、外交も極端に行っては失敗する。過去数十年を回顧すると、この原則を破った感が深い。
6.7 吉村氏
外交とは、国家及び国民の利益を他国との利害調整の裡に推進するにあり。
満州事変は一部軍部の専断によって勃発したもので、その善後措置としての外交は、中国の主権を抹殺するがごとき方法は一、二世紀前の古い帝国主義的フオミュラと申すべく歴史の進展に逆行するものである。
7. 小倉和夫教授の「解剖」(第4項参照)
満州事変については、最も重要なポイントは、中国における民族主義の高まりと反植民地主義の動きに直面して、日本がいたずらにこれを「排日」として糾弾せずに中国の独立と発展に協力する、しかもそれを、西欧列強のいずれかを引き込んだ形で行うことを1920年代からもっと考えておくべきではなかったか。
8. 総 括
1. 従来、勉強してきた日清・日露戦争以来の問題点を総括している。
2. 二人の大臣と四人の大使による談話と省員の批評は、調書を上回るくらい内容が濃い。
3. 石橋湛山氏の「小国主義」に耳を傾け、東洋経済誌に載った日米の鉄鋼生産のデータを知っていれば太平洋戦争が、いかに無謀であったかが判る。
4. 情報が公開された今日、もっと採り上げるべき情報だと思う。
(2003.6 鈴木靖三)
「近現代史2」に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last updated 6/30/2003]