幻の旧石器を求めて
| 目 次 1. 本との出会い 2. 本の概要 3. 本の目次 4. 内容要約 5. あとがきに代えて 6. 著者紹介 7. 読後感 8. 参考図書 |
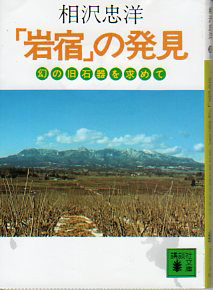 相沢忠洋著 講談社 |
「本の紹介5」に戻る トップページに戻る 総目次に戻る |
| 目 次 1. 本との出会い 2. 本の概要 3. 本の目次 4. 内容要約 5. あとがきに代えて 6. 著者紹介 7. 読後感 8. 参考図書 |
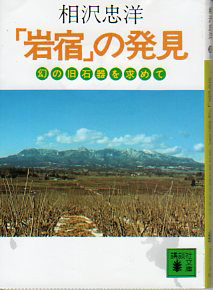 相沢忠洋著 講談社 |
「本の紹介5」に戻る トップページに戻る 総目次に戻る |
1. 本との出会い
第3部 岩宿発掘
2012年5月27日に、NMCの旅行で群馬県みどり市の岩宿遺跡を見学しました。主として岩宿博物館と岩宿ドーム(遺構保護観察施設)の2箇所を見ました。
旅行から帰って発見者の相沢忠洋氏が書いたこの本があることを知り、一気に読みました。とても良い本だと思ったので採り上げました。
2. 本の概要
桐生市に住んでおり行商で生活していた相沢青年が、この岩宿の切り通しで細石器を発見したのは、戦後間もない1946年の5月のことでした。さらに1949(昭和24)年の梅雨明けには、同じ場所で黒曜石の槍先形の石器を発見しました。この数ヶ月あと、東北大学芹沢長介教授と杉原荘介明大教授が現場に赴き、関東ローム層(赤土)中の石器を発掘します。こうして日本にも旧石器時代があったことを確認したわけです。 本の前半には相沢氏が若い頃両親が離婚して、苦しい生活を送ったことが書かれています。
3. 本の目次
第1部 少年の孤独
雷と赤土と空っ風………………………………………………………………10
炉辺の対話 10
すそ野の村々 19
哀愁のふるさと…………………………………………………………………23
“歴史”のなかに育って 23
こわれた一家団らん
30 小僧という身分……………………………………………………………39
浅草のはきもの屋で 39
古代へのあこがれ 54
海軍志願………………………………………………………………………64
戦争へ突入 64
敗戦から新しい時代へ 79
第2部 赤土の誘惑
空疎な日々……………………………………………………………………84
かごから解き放たれて 84
失意のなかから出発 94
大自然にふくらむ夢………………………………………………………… 100
細石器発見へ 100
深まる謎 111
黎明時代の遺跡と謎の石剥片の追跡 125
高まる遺跡への関心………………………………………………………… 130
登呂遺跡の刺激 130
赤土の崖の謎 134
東京の先生たちとの連絡 141
明るい光照らす 149
にがい経験とかべ 155
赤土に眠る黎明期文化………………………………………………………165
まぼろしの太古の世界 165
定形石器の発見 175
新しい学問の出発へ………………………………………………………… 180
“重大な発見”だ! 180
ついに発掘成功 188
たどりついた岩宿の丘 194
あとがきに代えて…………………………………………………………… 200
文庫刊行にあたって………………………………………………………… 208
カバー写真 相沢忠洋4. 内容要約
第1部 少年の孤独
著者が赤城山のふもとに散在する村を訪れたのは、昭和21年、戦争が終わって5ヶ月余りがすぎた春まだ浅い頃です。
祖先の残した、人間文化の体臭が、道の世界に開かれていることを知りました。赤城山の裾野の村々の一角、笠懸(かさかけ)村の丘陵地に露呈した赤土の崖――岩宿遺跡――です。
鎌倉は筆者のふるさとです。しかし昭和10年(筆者は10歳)の春、妹の死が契機となって父母が離婚し、それから筆者の暗い青年時代が始まります。
著者は父親と桐生市に住んだ後、一人浅草の履物屋に小僧として住み込みます。小学校は夜学です。露店で石斧を買い、それが縁で帝室博物館に行き、守衛の数野さんと親しくなります。小豆沢(おずさわ 板橋)の貝塚に行き、遺跡を見ます。
戦争は支那事変から太平洋戦争へと突き進んでゆきます。小学校卒業後、青年学校が義務教育になり、著者も浅草の富士青年学校普通科へと進みます。戦時色が濃くなり、物資の統制が厳しくなっていきました。著者は海軍に志願するため、桐生に一旦、帰ることとしました。昭和19年2月末に海軍から採用通知が来て、入団は5月25日と決まりました。集合地の高崎に行き、横須賀武山海兵団に入団することになります。3ヶ月の訓練の後、常磐線友部駅近くの筑波海軍航空隊に配属が決まりました。
年の瀬が近づいた12月25日に横須賀へ転勤になり、駆逐艦「蔦」の艤装員付きとなりました。ある日、主として大工部門を受け持っていた工員から酒保で酒を買うことを頼まれます。この人に自宅の下宿に誘われます。この人の奥さんが、なんと11歳のときに別れた著者の母親で、夫には内緒で打ち明けてくれました。
艤装を終えた駆逐艦「蔦」は訓練地の瀬戸内海に向けて出発し根拠地の呉に入港します。戦艦大和を見送った後、広島の原爆投下を遠望し、8月15日の玉音放送を艦上で聞きます。
関東地区の出身者は即日帰郷することになり、筆者も9月1日に上陸し、苦心の末、5日目の夜8時に桐生駅に降りたちました。
第2部 赤土の誘惑
著者が落ち着いたのは桐生市横山町の長屋でした。4畳1部屋で狭かったけれども、生まれて初めて独立独歩の人生が始まった喜びが大きかったのです。桐生は戦災で焼けなかったので、生活用品を赤城山の裾野の部落に行き、物々交換で食料を調達しました。そういう所でも縄文土器の破片は採集できました。
翌年の4月には横須賀へ母に会いに行きましたが、亭主が帰宅するとまずい雰囲気になり、2度と行くまいと決心します。
5月も終わりに近づくと、交換する品物も日用品、雑貨、小間物に変わってゆきました。行商で農村を歩くと、収集した土器や石器から祖先の生活の遺跡を知りたくなり、5万分の1の地図を買い求め、出土した場所に赤い丸を付けてゆきました。
夕方、村々での行商の帰りに、丘陵地の細道を歩き続けるうちに、山と山とのすそのが迫っているせまい切り通しにさしかかりました。両側が2メートルほどの崖となり赤土の肌があらわれていました。
そこに小さな石片が顔を出しているのに気づきました。荒れた赤土の地はだから、石片をひろいあげてみました。長さ3センチばかり幅1センチほどの小さなその石片は、手のひらの上で、ガラスのような透明な肌を見せて黒光りしていました。その形はすすきの葉をきったようで、両側がカミソリの刃のように鋭いものでした。
これらの石片が細石器ではないかという疑いと、今まで石器と一緒に出てきた土器が無いことなどの疑問が出てきました。
その後、次のような情報を得ました。
1. 八幡一郎先生の「日本の石器時代と細石器の問題」
2. 後籐守一先生の「日本人の古さ」
3. 新川(にっかわ)にある善昌寺の老僧の話
目標は石鏃(やじり)の出る遺跡の追求とし、黎明(あけぼの)時代の遺跡と謎の石剥片の追跡をすることにしました。第3部 岩宿発掘
なんとか専門の研究家にお会いしたいと思い、市川の国府台(こうのだい)に設けられたばかりの考古学研究所あてに、手紙を出しました。少したって返事が来て吉田格先生が桐生に訪ねてこられ、収集した石器について説明して頂くと同時に、高縄遺跡を一緒に発掘しました。
ただ遺物を集めるだけに熱心にならないで、さらにつっこんで問題を追及するため、東毛考古学研究所をつくり、赤城山麓における縄文文化早期初頭遺跡の基礎資料の集成を目的としました。
その頃、ある会社の社長が来訪し、生活を心配して、社員になることをすすめられ、その申し出でを受けることにしました。
梅雨期が明けた頃、いつもの崖で、赤土層の下の黒褐色の粘土層に黒曜石の槍先形をした石器を見付けました。赤城山麓の赤土(関東ローム層)のなかに、土器をいまだ知らず、石器だけを使って生活した祖先の生きた跡を発見しました。
著者の務め始めた会社が吉祥寺に支店を出すことになり、彼はそこに通うことになりました。
世田谷の赤堤町にある江坂輝弥先生を訪ねたとき、芹沢長介先生にお会いし、芹沢先生だけに赤土の崖から出る石剥片のことを話しました。
後日、芹沢先生からのご要望で青山のご自宅にお邪魔し、崖から採取した槍先形の石器と、細石器様の石剥片を持参しました。先生は八幡一郎先生の「満蒙学術調査報告」に載っていた細石器の写真と比較し、うりふたつだと感嘆の声をあげられました。そしてこれを重要だと断定する二つの理由をあげられました。ひとつは細石器様のグループが北関東にあり、もう一つは関東ローム層の中に土器を伴わずにあるということだと言われました。
9月になって芹沢先生から葉書をいただき、杉原荘介先生が登呂遺跡の発掘から戻られるので、明大の研究室に案内したいとのことでした。芹沢先生に伴われて明大の研究室に杉原先生を訪ねた結果、現地に行ってみたいということになり、10日に桐生に来て頂きました。岩宿に行って皆で掘り始め、夕方の4時頃、ついに杉原先生が青色の石器を掘り当てました。
翌12日、杉原先生は前橋を訪問し、県庁に寄り、桐生に戻って地元の村長さんや地主に会い、発掘目的の説明や本発掘の下交渉をしました。翌13日は終日調査を行いました。
考古学の常識は関東ローム層の赤土が出てくるとそこで発掘をやめていました。関東ローム層は1万年前から3、4万年前といわれ、人類や動物は住むことができないとされていました。
夢を求める執念と追求および学究グループの決断により、常識がくつがえされました。
10月から大々的な発掘調査が行われ岩宿遺跡が確認されました。
岩宿は、著者の青春の日の輝かしい思い出であり、人生の記念碑であります。
5. あとがきに代えて
岩宿文化誕生 岩宿遺跡は昭和24年9月11日から13日にかけて、3日間にわたる小発掘を予備調査とし、この成果を杉原先生は9月20日に新聞発表する、といいおいて帰京された。
私はこの発表を心待ちにした。一日千秋の思いとは、こういうときの思いではないかとも思った。
待ちわびた20日の夜明け、私は飛び起きて桐生駅へ走った。新聞売りのおばあさんが、売り台の用意をして朝刊を並べはじめるのももどかしく、朝日、読売、毎日とインキのにおいのする新聞をひろげて活字を追った。
あった、あった!
「旧石器時代の遺物――桐生市近郊から発掘――」
という見出しで、杉原先生があの握槌の石器を手にしている写真を掲載しているのもあれば、岩宿の位置を示す地図を載せているのもあり、それぞれに大きくあつかっているのだった。
私の胸は高鳴った。さっそく買い求めて、新聞を小脇にかかえこむようにして家へ帰っていく道で、「ついに岩宿文化は誕生したぞ」と心で叫んでいた。そして家へ帰っても、私は何度も何度も各紙の記事をあくことなく読みかえした。
このとき、私はちょうど引き揚げの長旅から帰って、背中の荷をおろしたときにも似た気持ちになっていた。
やがて10月2日から10日余りにわたって本発掘が実施された。明治大学考古学研究室を中心とする、杉原先生が隊長の岩宿遺跡発掘調査隊の本発掘、本調査で、その調査、設営などの裏方の仕事に私は走りまわった。
「旧石器時代の遺跡発見」との新聞発表によって、私か予想していた以上の大反響の波が岩宿の丘に集中してきた、といっても過言ではなかった。
明石原人の発見者で有名な直良信夫先生も来られた。明大の後藤守一先生ほかいろいろな先生がたが岩宿にこられた。
旧石器時代の遠古の文化が赤土のなかから発見されたということに、関心と好奇と、多少の疑惑の目が向けられ、続々と多くの人びとが群がり集まってきた。
私か予期していたように、山洞・山曽野グループは、前に彼らが掘った普門寺遺跡をタテにして、岩宿発見にたいする否定的言辞を流しはしめた。このことはいまもなお形こそかえながら、つづいている。
いつも静かに眠っている岩宿の丘は、にわかに騒然となった。そしてこのことは、私の長いあいだ抱きつづけ追いつづけてきた夢を、かき消してしまう結果を生んだ。
こうして3年余りもかけて追い求めてきた私の夢は、いまや学問の世界のなかへ現実の形としてその映像をうつしだしていったのであった。
騒然とした発掘調査も終わり、調査隊が引き揚げていったあと、10月中旬のある日、私はひとり遺跡に立ち、所在ない気持ちで山寺山に登り、いま二つの道の岐路に立つ私自身の出発点に立っていることを思わないではいられなかった。
私のたどるべき二つの道――それは一つには、関東ローム層中の未知の石器文化が、現実の日本の考古学という学問の世界にうぶごえをあげて歩みはじめ、それをより健全な姿に育てあげていくことであった。
そしていま一つは、孤独だった少年の日から心に求めてきた一家団らんへの思慕ということが遠大な世界のながにひろがり、さらに、そのなかになお追い求めていくことになったのである。
この二つの道は、時としてあい接近し、また遠く距り離れることはあっても、今日もなお私の上につづいている道なのである。父母の死 昭和36年11月――「山師のようなことはやめて働いて金をためろ」といいつづけた父は、空っ風が吹きはじめた前橋市の一隅で脳血栓で床に臥していた。
そんなとき思いもよらない通知がきた。群馬県では最高という「県功労章」をいただけるという通知であった。55歳以上でなければだめという賞を、特別にオリンピックで活躍した相原信行氏と私にくださるという。私はお受けしてよいものがどうか、当惑した。しかし病床の父におくる息子の私の人生日標のただ一つの証(あかし)はこれしかない、と考えてお受けすることにした。
11月23日、群馬県庁の正庁の間で受賞、その式が終わるとすぐその足で父の枕べに急いだ。その日いくらか気分がよかったのか、父は口もとをほころばせ、私が、
「県知事さんからこの賞をいただいてきた」
と、大きな賞状と銀盃を手にとらせると、
「よかったなあ、おまえやみんなに苦労をかけてすまなかった」
といって、何度も何度も、やせ細った手で銀盃をなでさするのだった。その5本の指先には、かたいたこができていた。
長い間吹きつづけてきた笛の芸ひとすじにうちこんだ男の指を、私はこのときはじめてじみじみとながめやった。
だが、私が父と交わすことのできた数少ないことばは、これが最後だった。その夜ふけ、寒気のさしこむなかで昏睡状態におちいり、12月5日、79歳を一期(ご)として黄泉(よみ)の旅にたっていった。
昭和39年、その年を送る除夜の鐘が鳴りはじめたとき、電報がとどいた。房州鴨川の生鴨川の生地で母が危篤という知らせだった。40年元日の朝早く、私と妹は母のもとに急もとに急いだ。母は私たちの顔を見るなり、ぼろぼろ涙を流した。
そのあふれ出る涙を、もはや母自身の手ではぬぐえない病状だった。松もとれ、七草もすぎたころ、母はこの世を去った。母が暮らしていた家の庭には、母が丹精をこめて育てたなつみかんの実の黄金色があざやかだった。
父には男として、母には女として、それぞれの人生の歩みがあつたのだと私は思った。父にとっても母にとつても、それでよかったのかもしれないと私には思えるのだった。それが人間の歩みとしての一端であるとするなら、また私も同じような道を歩みつづけていくのだろう。ただ許されるならば、親子が一家団らんの生活をもう少し味わいたかったということである。
赤土のなかに、遠久な時の流れをきざみつづけた人間の体臭を求めて23年余、その間、私はひたすらに岩宿文化を育てるのに懸命であった。百キロの道を自転車で上京したことも、再三あった。この世に生を得てすでに40年をすぎたいま、私は自分の心にいいきかせている。それは人間として、1人の男として、《肌に錵(にえ)、心に匂い》を求めつづけていきたいということである。
昭和42年、春まだ浅いころ、東京からの電話で、まったく考えもしなかった知らせを受けた。破格の大賞である吉川英治賞を授賞することに決まつたというのであった。
この受賞の喜びを、私はだれに知らせ、だれに喜んでもらったらよいのだろう。
受賞の日、うれしかるべき私には、なぜかさびしさがいっぱいで、胸がふさがるばかりだった。ただ戸惑うばかりだったのである。
授賞式の後、はるばる桐生からかけつけてくださった友人を江戸川まで送って、その帰途、私は墨田川の橋上に立った。川面は黒くよどんでいた。
そのよどみのなかへ、いただいてきた花束のなかから一輪をぬきとって投げこんだ。そして私は鎌倉で別れたまま、いまだに消思不明の末の妹の健在を願った。
橋上に立つと、目の前に思い出多い浅草の松屋のネオンが、やわらかな光を放ってまたたいていた。
友 情 思えば私は人間嫌悪(けんお)を長く心の奥底に秘めて今日まできた。それは私の生いたちの環境から生まれてきたものであろうか。いけないことと自省自戒しながらも、人間嫌悪の情を捨て去ることはできなかった。人間の好意を率直に受け人れられない自分のふがいなさには、時として、みすから腹立たしさを覚えることもたびたびあった。
しかし、そのような私に、近年人間としての真の友愛の手をさしのべ、教えてくれた何人かの人びとがあらわれてきた。私はこの人びとから人間としての広がりと深みの世界を教えられた。
この本を世に送りだすことについても、私はためらいつづけた。どうしても気がすすまなかった。その気のすすまぬものを決心させてくれたのは、じつは人間のあたたかみと友情によってのことであつた。
原稿を書きはじめて1年有余の月日がすぎてしまった。日々、原稿用紙のます目をうめていくペン先は、時としてはたと止まってなんとしても進まないことがあった。厳寒の深夜、ひとり起きでて遠い過去をきのうのように心にえがきだすのだった。
これを勇気づけ叱咤激励してくださった講談社学芸第2部の加藤勝久部長はじめ皆さまのご支援と、何かと鞭撻してくださつた玉上統一郎、千吉良進作、久保田千恵子、須藤素男の諸氏と、そのご家族の方がたのご助力を忘れることができない。
もし、この1冊の本が、読者のみなさまの何らかのお役に立つところがあるとするならば、人間としての友情を、身をもつて与えてくださった多くの方がたのおかげにほかならない。
岩宿の発見――それは私のつたない歩みのひとこまであつた。それから今日まで、私は私なりの夢を追い求め歩みつづけてきた。この長い旅路はなおこれからもつづくであろう。
いつの日か、孤独な私の心にともしびをかかげてくれ、いらい、私の座右の銘としている詩がある。
生涯身を立つるに懶(ものう)く
騰々(とうとう)天真に任(まか)す
嚢中(のうちゅう)三升の米
爐辺(ろへん)一束の薪(たきぎ)
誰か問わん迷悟の跡
何ぞ知らん名利の塵
夜雨草庵の裡(うち)
等間(門構えに日ではなく月)に双脚(そうきゃく)伸ばす
良寛の作詩といわれる。心荒れる夜など、この詩を口ずさんでいると心休まる。
私の歩みはいまも、どこかに遺されたはずの祖先の一家団らんの場を求めている。その指標するところ、求めてやまないまぼろしの日本原人の姿が浮かびあがってくるのである。
いまとなってふりかえってみれば、この1冊に記した岩宿遺跡の発見は、私の今日の歩みへの序章ともいえるものであつた。
昭和43年12月
相沢忠洋6. 著者紹介
相沢忠洋(ただひろ) 1926年生まれ。小学生の頃より歴史に興味をもち、東京四枚畑貝塚を踏査。戦後桐生市に住み、行商で赤城山麓を訪れるかたわらその周辺の遺跡を踏査し、ついに「岩宿石器文化」を発見した。 1961年群馬県功労賞、1967年吉川英治賞を受賞。著書「岩宿の発見」講談社刊。連絡先 〒376-0131群馬県勢多郡新里村奥沢537相沢忠洋記念館。1989年5月没。
7. 読後感
日本にも旧石器時代があったという大事な発見が、石器の好きな青年によって行われたことは、驚くべきことです。自分ができなかった一家団欒を常に追い求めるという発想が良いと思います。関東ローム層の中には石器が存在しないという先入観が、発見を遅らせていたのでしょう。余り正規の教育を受けていなかった著者が、このような自伝を書いたということにも、感心させられます。
8. 参考図書
列島の考古学 「旧石器時代」 堤 隆著 河出書房新社 2011.5.30 初版発行
「本の紹介5」に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last updated 6/30/2012]