アット・ザ・フアイヴ・スポット
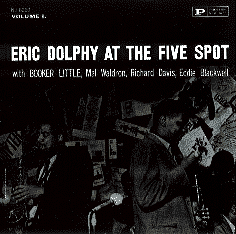
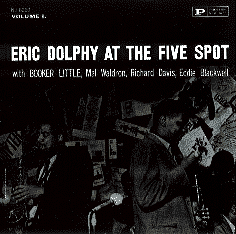
「ジャズの名盤」の目次に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
目 次
2 CDの紹介
1 タイトル、曲名、演奏者
CDのタイトルと収録された曲をご紹介します。
2 CDの紹介
ライナーノートに載っている、エリック・ドルフイーを始とする演奏者と、曲についての紹介です。
3 CDの聴き方
「ジャズ完全入門 !」に載っている内容で、このCDの聴き方が判ります。
1 タイトルと曲名
ERIC DOLPHY
AT THE FIVE SPOT, VOL.1
エリック・ドルフイー・アット・ザ・フアイヴ・スポットVol.1
1.ファイアー・ワルツ
FIRE WALTZ (Mal Waldron)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13:35
2.ビー・ヴァンプ
BEE VAMP (Booker Little)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12:23
3.ザ・プロフェット
THE PROPHET(Eric Dolphy)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21:17
4.ビー・ヴアンプ(別テイク)*
BEE VAMP (alternate take) (Booker Little)*・・・・・・・・・9:26
* CDボーナス・トラック
* Additional track not on original LP
■エリック・ドルフイー(as-1,3, bcl-2,4)
■ブッカー・リトル(tp)
■マル・ウォルドロン(p)
■リチヤード・デイビス(b)
■エド・ブラックウェル(ds)
1961年7月16日
NYCファイヴ・スポットにてライヴ録音
FIRE WALTZ/BEE VAMP*/
THE PROPHET/BEE VAMP (alternate take)*
Eric Dolphy (as, bcl*)
Booker Little (tp)
Mal Waldron (p)
Richard Davis (b)
Ed Blackwell (ds)
Recorded In Performance at the FIVE SPOT, New York City, July 16, 1961
このCDを制作するに当たっては、20blt K2スーパー・コーディングを用いてCD化致しました。
尚、この際に1960年代のアナログ・マスター・テープを使用しておりますので、アナログ・マスター・テープ固有のテープ・ヒス・ノイズ、歪み、ドロップアウトといった瑕を含んております。御了承下さい。
Prestige
ぼくには今でも、何かにつけて残念に思うことがひとつある。それは、モダン・ジャズ史上最大の巨人のひとりセロニアス・モンクと、60年代前半、閃光のごとく強烈な一条の光を放ったまま突然帰らぬ人となった鬼才、故エリック・ドルフィーとが、レコード吹き込みはおろか、ただの一度も相まみえることなく終わってしまったということである。これはジャズ史上、少なくともモダン・ジャズ史上における痛根の一事であった、といってよいのではあるまいか。
たしかに仮定の推理はいつも建設的ではない。ましてや過去に完了した一件に仮定形を適用したところで,一時の気休め以外の何物でもないに違いない。しかし、それを承知のうえであえて、もしモンクとドルフィーとが一度なりとも共演していたら、どんなに貴重な体験を与えてくれただろうと考えると、 単に気休めだなどとは言えぬような気がするのである。つまり、それは,音楽(あるいは芸術)の概念の問題であり,文化の革新の問題である.こうしたレヴェルで両者の音楽を対比させ,互いに関連しあう点を見出していくなら、単に気休めにしか見えないこの仮定も愉しいものであり,なかなか有効なものだと思う。
そういえば、ドルフィー自身も、『アウト・フロント/ブッカー・リトル』(キャンディド)の吹き込みでリトルやマックス・ローチと共演した直後に渡欧したとき、パリでこんなことを言ったことがある。 「いちばん偉いとおもうピアニス卜は、やっはりセロニアス・モンクだよ。よしお前といっしょにやってやろうとモンクがいってくれるだけの実力の持主になりたいが、こいつは夢におわってしまうような気がする。モンクとドルフィーというレコードを吹きこむことができたらなあ」(植草甚一著『モダン・ジャズの発展』)。
ドルフィーがいったとおり、ドルフィーとモンクとの共演は夢に終わってしまった。ドルフィー自身がモンクとの共演を渇望していただけに、当時もしドルフィーを心底理解するものがアメリカのジャズ・ビジネスに携わる人々の中にいたら,この夢の実現は決して虚しいものではなかったに違いない。生前のドルフィーは死ぬまでこうした人々の無理解に泣かされ,こともあろうにアンチ・ジャズのレッテルを貼られたりした。人は死して名を残すというが、 生前、絶えず貧窮に甘んじ、無責任な中傷に耐えつづけねはならなかったドルフィーにとって、いみじくもフランスのローラン・ゴデが怒りと辛辣さとをこめて叫んだように、死後の1965年に多くの批評家の支持でダウンビート誌から"名声の殿堂"(Hall of Fame)という栄誉を与えられた(これはゴデの記憶ちがいだろう)などということが、いったいどんなに大きな名誉だったというのか。それは"恥の殿堂"(Hall of Shame)ではなかったか。ジャズ界を歩く人々は、恥の上塗りをしたと,いっそう痛烈に思わなけれはなるまい。むしろドルフィーを死に追いやったのは自分たちだったのだ、という認識こそが必要なのだ。
生前パーカーは、 「偉大な音楽家はいつも生きている間には正しく理解されなかった。音楽家の生涯はいつもそのようにみじめだった。ベートーヴェンがそうだったように」と言ったという。それは音楽というものに対する、バーカーの醒めた認識であった。ヨーロッパには何百年も前にそうした歴史的な体験を練り返して砥め、それらを乗り越えてつくりあげてきた伝統的な丈化風土がある。バーカーも,ビリー・ホリデイも、初めてヨーロッパに行って,眞に開放的な気分を味わった。
ドルフィーも例外ではなかった。ミュージシャンにとってヨーロッパが天国というわけではあるまい。人種の坩堝であり、歴史の浅いアメリカの状況がひどすぎたのだ。いまでもその点は大同小異に違いない。しかし,当時の状況はとても現在の比ではなかっただろう。おそらくすベてのミュージシャンは多かれ少なかれ,こうした状況から逃げだしたいと考えていたに違いない。この当時アメリカのジャズ・ミュージシャンが数え切れぬくらいヨーロッパに渡ったのには,こうした背景があったのである。
ドルフィーは60年代に入って何度か渡欧したが、1964年にとうとうアメリカを捨てる決心をした。これは最後のチャンスであり、賭けであったろう。仕事口がなくて困っていたエリックを拾いあげたのは,かつての彼の師でもあるチャールス・ミンガスだった。ふたたびミンガスのワークショップに加わってヨーロッパへ赴いたドルフィーは、ミンガスと別れてそのままヨーロッパに居残った。
「ヨーロッパに永住するのか」とミンガスに訊かれて、当分アメリカを棄てる気持ちが一方にありながら、 「ちょっとの間のつもりだけれど、自分でもよく判らない」と答えたドルフィーの心には、言いしれぬ焦慮と不安とが渦を巻いていたに違いない。ドルフィーの遺作として有名な「ラスト・デイト」(ライムライト)は言うまでもない彼の傑作のひとつだが、フルートによるあの凄絶な名演「You Don't Know What Love Is」を聴くと、切りたった崖にはいつくばって、生への執念を剥き出しながら探求者として孤高の姿を浮き彫りにするドルフィーの向こう側で、不安と焦慮に駆られて暗澹としているもう1人のドルフィーがうずくまるようにして震えているのにぶつかる。ぼくなどはいまでもドルフィーの凄絶な闘いの跡にふれるたびに戦慄が走り,思わず身震いがする。生涯を孤独な闘いで明け暮れた1人の男の、はらわたをえぐるような吐露がそこにある。レコードの音溝に刻み込れた彼のアドリブ・ソロこそその吐露であり、そのわずか数年間おける吐露の集積こそ、彼の真摯な闘いの跡を克明に写した闘いの跡そのものにほかならない。 短いカーブを描いて36歳の恵まれぬ生涯を閉じたドルフィーの闘いの記録に、もしセロニアス・モンクとの邂逅が付け加えられていたら、ジャズの歴史はさらに豊かなものになっただろうと思うたびにドルフィーの,ひいてはほくらの不運を嘆かずにはいられなくなってしまうのである。
「アメリカ政府ではジャズ使節としてガレスピーをインドに派遣したことがあった。彼を選んだのは聴衆をよろこばすだけの道化帥的な才能があったからだ。なぜドルフィーに国家補助金を与え、彼の探求を楽なものにさせなかったのだろう、そのほうが大切なことだった」(植草甚一著,前掲書)と言ったのは先のローラン・ゴデたったが、ぼくならさしずめこう言うだろう。ダウンビート誌上でエリック・ドルフィーに新人賞や死後になって栄誉を与えたのは世界のジャズ評論家たちであったが、なぜ彼らはドルフィーに補助金を与えるよう関係者を説得したり、その探求を楽なものにさせる努力をしなかったのだろう。そうでなければドルフィーに1票を投じただけの意味はどこにもない。
ところで,このアルバムを聴いてぼくがすぐ思い浮かべるセッションは、 1957年の夏に、ところも同じファイヴ・スポットでセロニアス・モンクがジョン・コルトレーンを加えたクァルテットで白熱的な演奏を展開したと言われるもの。生前コルトレーンはこれを宝物のように大事にしていたというが、その後このテープがレコード化されたという話は耳にしない。しかし、この夜の演奏はいまもファンの語り草になっているほどで、先年ファイヴ・スポットのオーナーだったジョー・ターミニに会ったときも、彼が目を輝かして思い出したのがこの夜のセッションであった。現在、モンクとコルトレーンの共演盤としては『セロニアス・モンク・ウイズ・ジョン・コルトレーン』(リバーサイド)があるが,ターミニによれば、この夜のセッションは唯一の共演盤を上まわって余りあるものだったと言う。
入魂の妙技というが、参じた演奏家たちがシリアスに自己をさらけ出し、完全燃焼させていく彼らのホットなプレイに刺激されて、聴衆の熱気の水銀柱がぐんぐんあがっていく。この稀に見るエキサイティングな演奏にふれると、いまや幻と化しつつあるモンクとコルトレーンのセッションもおそらくこのような,あるいはこれ以上にスリリングなライヴではなかったかと、考えては胸が高鳴ってしまう。
ドルフィーと同じようにモンクの前衛性は時代をはるかに超えていた。彼の革新的な音楽が人々に理解されるようになったのは、ちょうど彼の息子のようなバド・パウエルが麻薬禍で落ち目になったころで、 30年代の終わりから40年代前半にかけて、誰からも認められずに細々とピアノを弾いていたときから、すでに15年以上が経過していた。ドルフィーが50年代後半にロスからニューヨークに出てきたころは、折しもモンクの革新が認められて、その声価が高まりつつある時期だった。あらゆるミュージシャンがこぞってモンクの革新と創造性に目を向けた時期だ。ドルフィーもその1人であり、彼がモンクの音楽から少なからずインスピレイションを感じとって、みずからの音楽の栄養にしていったことは充分に考えられることだ。
両者の即興芸術に共通する最大の一点は語法の特異性である。それは和声進行をもとにした即興的展開という点で従前のジャズの伝統的方式を根底から否定するものではなかったが、慣習的な方法論からは離れた独特のパターンをもつ、ユニークなシンタックスによって支えられていた。さらに言うなら、それらは伝統と前衛の,まさしくはざまにあるものだ。もちろん両者がそれをことさらに意識したとは思えない。また単に人とは違った音を出すことにつとめただけかもしれない。しかし、伝統と前衛を半分ずつ手のひらに握っているモンクとドルフィーの音楽は、その不思議な音の跳躍とストラクチュアがかもし出すアブストラクティズム的な印象によって、伝統の否定者もしくは破壊者としての面だけを多くの人々に植えつける結果になったのであった。もし彼等の前衛が真の前衛なら、多少の時間はかかっても、いつかは人々に理解され認められるはずだ。というのは、真の前衛が決して永久にアヴアンギャルドのままであることはなく、もしそれが真の前衛なら、それは次代の主流になりうる質をもっていなけれはならないからである。モンクの場合には、まさしくその真理が実証された。 では、ドルフィーはどうであろう。ドルフィーを偉大な創造的ミュージシャンと言う人は多い。むろんアンチ・ジャズ呼ばわりする手合いは1人もいなくなった。しかし、ドルフィーの音楽が何を語り、60年代ジャズにあってどのような位置を占め、どんな美学を生み出したのかということが明らかにされないまま、ドルフィーはいまやや不用意に美化されてしまったとは言えないだろうか。彼が過渡朗のミュージシャンであるといった乱暴な意見の詮議はともかく、何よりも彼がいかに真摯な表現者、探求者として、彼の人生を闘いぬいたかということ、そしてその過程で生み出された彼の音楽が、たとえどのような衣装をまとっていようと、そうした彼のひたむきな闘争の真実のあかしであったということを認めなければならないだろう。
このアルバムはドルフィーの最高傑作の1枚と呼んでいいものだが、セッション全体を通して聴くことを勧めたい。すなわち、このセッションは全9曲からなり,4枚のレコードに分散収録されて市場に出た。『Vol.1』『Vol.2』『メモリアル・アルバム』、それに『ヒア&ゼア』の4枚である。このうち『ヒア&ゼア』はドルフィーの死後に発表されたもので、その中の2枚がこのときのセッションに属するものだ。
●エリック・ドルフィー(as, bcl-「ビー・ヴァンプ」)
●ブッカー・リトル(tp)
●マル・ウォルドロン(p)
●リチヤード・デイビス(b)
●エド・ブラックウェル(ds)
1961年7月16日、NYC、クラブ ファイヴ・スポットにて
まず、マル・ウォルドロンのオリジナル、「ファイアー・ワルツ」でスタートする。3/4拍子作品で、テーマは16小節の繰り返し、ソロはas(16コーラス)→tp(17)→p(13)。このあとピアノのワルツ・コンプがあってテーマヘ返される。つづく「ビー・ヴァンプ」はこの吹き込みの3ヵ月後(10月5日)にわずか23歳の若さで夭折したブッカー・リトルの作品。A(28小節)/B(20)形式48小節作品ともとれるし、A(12)/A'(16)/A(12)/A"(8)形式48小節作品とも、さらに細かくA(8)+B(4)/A(8)+C(8)//A(8)+B(4)/A(8)形式48小節作品とも分析できる。モード(A)を主軸にしたブリリアントな作品だ。ソロはtp(4コーラス)→bcl(4)→p(4)→b(Bの20小節)。
ラストの長編「ザ・プロフェット」はドルフィーのオリジナルで、ユニゾンからクラスターへの変化を用いたテーマが印象的。彼の友人だった画家リチャード・ジェニングスの渾名をタイトルにした作品。彼は『アウトワード・バウンド』や『アウト・ゼア』のジャケット絵を画いている。曲はAA′BA′形式32小節作品。ソロはas( 4コーラス)→tp(2)→p(2)→b(1)。バラードだが、ソロは倍テンポの4ビートで進められる(dsなどは3倍速のテンポで挑発したりする)。何といっても鬼才ドルフィーのコーラスに胸熱くなる一篇である。 [悠 雅彦]
本CDでは、後に未発表録音集として発表されたアルバム『DASH ONE』(MPP-2517)で日の目を見た「ビー・ヴァンプ」」の別テイクを追加収録しております。
発売元■ビクターエンタテインメント株式会社
VICJ160010
STEREO (出典 ライナー・ノート)
3 CDの聴き方
ジャズには、聴いているうちに未知の世界に連れ去られてしまうのではないかといった、不安と期待の入り交じった不思議な気分にさせられてしまうものがある。エリック・ドルフィーの音楽がまさにそうで、彼の吹くアルト・サックスやバス・クラリネットからは、人の心の奥底に潜む、自分でも窺い知れない暗闇に火をつけてしまうような怪しい響きが聴こえてくる。
そういったドルフィーの演奏を「前衛」と捉える向きもあるが、そんな紋切り型の括りには収まり切らない底知れない部分が彼の音楽にはあるのだ。そのところを少し分析してみると、まず彼の吹く楽器の完璧な響きと力強さがある。たとえばアルト・サックスの音色は人によってさまざまだが、音に強いコシがあって、しかもそれが底光りするような深い艶を帯びているところや、また大変に演奏が難しいと言われるバス・クラリネットを豊かな響きで軽々と吹き切ってしまう力量は、ジャズ界でも屈指のものだ。
次いで、これがもっとも彼の音楽の特徴的な部分なのだが、メロデイ・ラインの構築の仕方が他のジャズマンたちとは明確に異なっており、しかもその原理が読み切れない。一般論だが、ダメな前衛音楽は、単に自分の怒りや抗議の気分を無秩序に楽器に叩きつけたような浅薄なものが多く、こういった代物は少し冷静に聴けばすぐにメッキが剥げる。楽屋裏が見えてしまうのだ。ところがドルフィーの音楽は、一聴、強烈な情動を喚起するのだが、それを引き起こすのは彼が同じ気分を楽器に込めたからだといった単純な聴き手の思い込みを越えた、不気味なほどの力を感じさせるのである。
この演奏はそんなドルフィーの危険な魅力が、非常にわかりやすい形でアルバムにまとめあげられているので、ジャズから異次元感覚を受け取りたいと思っている方には最適の一枚だ。
わかりやすいと言ったのは、臨時編成のバンドでのレコーディングや、サイドマンの経験が多かったドルフィーとしては珍しく、レギュラー・コンボ(録音のための特別編成でない恒常的なグループのこと)での演奏であるから、各自が安定した実力を発揮しているということ。そしてこの、エリック・ドルフィーとトランペッター、ブッカー・リトルの双頭コンボ(リーダー格が二人であるグループのこと)は、ハード・バップ的な演奏の枠組みを保っているので、フォーマットとして馴染みやすいということがある。
つまり、ドルフィーを除くリズム・セクションやプッカー・リトルのトランペットは普通のハード・バップ・スタイルで演奏を行なっており、そこに異分子としてのドルフィーが乱入しているという形なのだが、凄いというか不思議というか、そうやって出来上がった音楽全体がまったく違和感のない「ドルフィー・ミュージック」となっているのである。この辺がドルフィーの底知れなさの所以(ゆえん)である。
聴きどころは、ピアニスト、マル・ウォルドロン作曲の異様な緊張感をたたえた名曲「ファイアー・ワルツ」だ。まるで形を持った音の塊が弾け、飛び、跳躍するようなドルフィーのアルト・サックス・ソロの途方もなさ。そしてそれと対照をなす流麗なブッカー・リトルのトランペットが、滑らかな、しかし一抹の甘さもない鋭いフレーズを空中に吹き上げる。続くマル・ウォルドロンの、深い螺旋を描きながら地中にのめり込んでいくようなピアノ・ソロの暗い情熱……と、ジャズという音楽が時として描き出す、ミュージシャンたちの「行ってしまった境地」の凄みが余すところなく記録されている。 (出典 ジャズ完全入門 !)
「ジャズの名盤」の目次に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last Updated 2/28/2002]