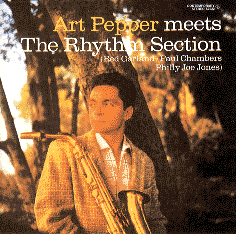
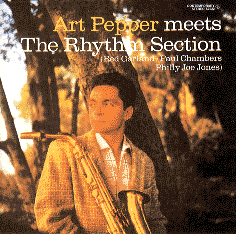
「ジャズの名盤2」の目次に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
目 次
1 タイトル、曲名、演奏者
CDのタイトルと収録された曲をご紹介します。
2 CDの紹介
ライナーノートに載っている、演奏者アート・ペッパーと、曲についての紹介です。
3 CDの聴き方
「ジャズ完全入門 !」に載っている内容で、このCDの聴き方が判ります。
1 タイトルと曲名
アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズム・セクション
1.ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ
YOU'D BE SO NICE TO COME HOME TO
(Cole Porter) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5:26
2.レッド・ペッパー・ブルース
RED PEPPER BLUES (Red Garland) ・・・・・・・・・・・・・・3:38
3.イマジネーション
IMAGINATION (J. Burke-J. Von Heusen) ・・・・・・・5:53
4.ワルツ・ミー・ブルース
WALTZ ME BLUES (A. Pepper-P. Chambers) ・・・・・・・・・・・・・・2:57
5.ストレート・ライフ
STRAIGHT LIFE (Art Pepper) ・・・・・・・・・・・・・・4:00
6.ジャズ・ミー・ブルース
JAZZ ME BLUES (Tom Deloney) ・・・・・・・・・・・・・・4:47
7.ティン・ティン・デオ
TIN TIN DEO (Chono Pozo) ・・・・・・・・・・・・・・7:44
8.スター・アイズ
STAR EYES (G. De Poul-D. Raye) ・・・・・・・・・・・・・・5:13
9.バークス・ワークス
BIRKS WORKS (Dizzy Gillespie) ・・・・・・・・・・・・・・4:19
10.ザ・マン・アイ・ラヴ*
THE MAN I LOVE (George & Ira Gershwin)*・・・6:37
* CDボーナス・トラック
* Additional rack not on original LP
■アート・ペッバー(as)
2 CDの紹介
■レッド・ガーランド(p)
■ポール・チェンパース(b)
■フイリー・ジョー・ジョーンズ(ds)
1957年1月19日 L.A.録音
YOU'D BE SO NICE TO COME HOME TO/RED PEPPER BLUES/IMAGINATION/WALTZ ME BLUES/STRAIGHT LIFE/JAZZ ME BLUES/TIN TIN DEO/STAR EYES/BIRKS WORKS/THE MAN I LOVE
Art Pepper(as)
Red Garland (p)
Paul Chambers (b)
Philly Joe Jones (ds)
Recorded January 19、 1957
このCDを制作するに当たっては、20bit K2スーパー・コーディングを用いてCD化致しました。
尚、この際に1950年代のアナログ・マスター・テープを使用しておリますので、アナログ・マスター・テープ固有のテープ・ヒス・ノイズ、歪み、ドロップアウトといった瑕を含んでおリます。御了承下さい。
アート・ペッパーはウエスト・コースト・ジャズの輝かしい星の一つであった。多くのウエスト・コースト・ジャズのサックス奏者がそうであったように、彼もまたスタン・ケントン・オーケストラの出身者であった。けれどアートは、その在籍時代は違うものの他のケントン・オーケストラ出身のサックス奏者たち、たとえばバド・シャンク、レニー・ニーハウス、ビル・ホルマン、ボブ・クーパー、リッチー・カミューカ、ビル・パーキンスなどとは違ったものを持っていた。のちにウエスト・コースト・ジャズ・シーンで活躍したほとんどのケントン・オーケストラ出身のサックス奏者たちが、一応にいかにも白人らしい、スマートさとソフトな感触とを売りものにしていたのに比べて、アートはそういったウエスト・コースターとしての特色をそこかしこに見せながらも、もっと黒っぽくてジューシィな風味のプレイでもって他のウエスト・コースターたちとは一線を画していたのだった。言ってみれば、マーガリンとバターの違いである。また、他のケントン・オーケストラ出身のサックス奏者たちの多くが、ケントニアンらしい編曲されたジャズ(そのことは、とりもなおさずウエスト・コースト・ジャズの特徴でもあったが・・・・・・)を好んだのに対し、アートはあくまでもアドリブ奏者としてのプレイにすべてを賭けたのだった。実際、彼が50年代に吹き込んだリーダー作のうちで編曲に重点を置いたものと言えばコンテンポラリー盤『プラス・イレヴン』のみで、それに前後して録音されたパシフィック・ジャズヘの6重奏や9重奏によるものに、そういった編曲の痕跡が見られるくらいなのである.そしてだからこそ、アート・ペッバーというアルト奏者は多くの、かつ不特定多数のファンから愛されたと考えられるのである。
不特定多数のファンからと言ったが、70年代以降になるとアートに対するファンの支持層が大きく二つに別れることになった。 50年代ペッパー派と70年代以降のペッパー派とにである。ここで私の立場をはっきりさせておく必要があろう。拙著『モダン・ジャズ・レコード・コレクション』(誠文堂新光社刊)のペッパーの項で、 "60年代半ば、アート・ペッパーはその見事なアドリブの花をドライ・フラワーにしてしまったのだった"と述ベたように、私は50年代ペッパーこそ真のアート・ペッバーであると信じてやまない者の一人である。 50年代ペッバーは70年代以降に比べて女々しいと言う人がいる。だが、私は男らしさの裏返ったアートの"女々しさ"こそが、ペッパーのペッパーたるゆえんであると思うのである。 50年代ペッパーか70年代以降かは結局は好みの問題と言ってしまえばそれまでだが、私は好みの問題などでは絶対になく、それは一人のジャズ・ミュージシャンへの想いのたけの問題であり、ジャズに対する美意識の問題でもあると思う。字数の関係からこのことについてあまり長々と論じるわけにはいかないが、論より証拠、本ディスクをはじめとする50年代ペッパーの名作群と70年代以降のものとを聴き比べれば、私の言わんとしていることは歴然とするはずだ。というわけで、以下、私の言うアートの素晴らしさや特色は、すベて50年代の彼についてである。 さて、本ディスクだが、これはアートが遺したワン・ホーンによるものの中でも最もスウィンギーな1枚であり、このセッションについてはすでに多くの人によってあらゆる角度から言いつくされているが、私としてはこれがCD化されたことにひとしおの感慨を覚える。いま、50年代ジャズの名演の数々が次々にCDで蘇ってその素晴らしさが再認識されているが、本セッションのCD化もまたこれがアートの代表的1枚であるだけではなく、 50年代ジャズのすぐれたものでもあるだけに大いに歓迎すベきものであると言えよう。しかも今回のCD化に際して、同一セッションながら別LP(『The Way It Was』)に収録されていた「ザ・マン・アイ・ラヴ」を最後に置いて、コンプリートな形にした点もファンにとってはありがたいことだと言えよう。それにしても『アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズム・セクション』とは、なんとスリリングな響きを持ったネーミングだろう。もうそれだけで、ペッパー・ファンなら耳の底に音がまざまざと浮かびあがってくるに違いない。また彼のファンならずとも、 50年代ジャズの支持者なら当時のマイルス・クインテットの黄金のリズム・セクションで、まさにザ・リズム・セクションと呼ぶにふさわしいその顔ぶれを見ただけで、ある種の戦慄が背筋を駆けめぐるはずだ。そしてアートとザ・リズム・セクションは、そういったファンたちの熱い期待を裏切らないどころか、それを上回るスリリングでスウィンギーな演奏の数々を展開しているのである。よく知られたスタンダード曲やバップ・ナンバー、アートの代表的自作に加えて予想もしなかったディキシーの名作、それにペッパー〜ガーランドの魅惑的な二つのブルース・オリジナルと、演奏曲もすベて申し分ない。申し分ないどころか、アートとザ・リズム・セクションはそれらの曲をそれぞれ望みうる最高のインタープレイでもって演じて見事だ。アドリブに賭けるアート、彼は他の追従を許さない圧倒的なタイミングのよさ、すなわちリズムのセンスの非凡さをいかんなく発揮して聴く者を昂奮のるつぼに追いこむ。そしてその昂奮はアート同様の、あるいはそれ以上のタイミングの妙、鮮やかなザ・リズム・セクションの動きと相俟って倍増されるが、それらのことは「ストレート・ライフ」のような急速調の演奏だけではなく、 「イマジネーション」といったバラード・タイプの演奏にまでおよんですぐれた効果を上げている。ところで、最近の調査によるとコンテンポラリーには、アートの未発表演奏のテープが大量にみつかったとのことだが、本セッションのものはここに収録されている10曲のみであったという。本セッションが素晴らしいものであるだけにそのことは残念だが、見方を変えればここでの10の演奏がすべてワン・テイクであったということを裏付けており、さらに言えば、本ディスクに聴かれる全演奏こそ、ジャズの最も特色的一面である一回性の輝かしき成果なのであり、まさに一期一会の好対決でもあるのだ。そして両者による対決は、ストップ・タイムを巧く使った「ジャズ・ミー・ブルース」を頂点に、アートとレッドによる「レッド・ペッパー・ブルース」「ワルツ・ミー・ブルース」というオリジナルや、 「パークス・ワークス」では聴く者をファンクな快感で包み、あまりにも有名な「ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ」では酔わせる。また、 「ティン・ティン・デオ」ではアートお得意のラテン・フレイヴァーが味わえるし、「スター・アイズ」と「ザ・マン・アイ・ラヴ」ではテンポの意外性に驚かされもするのである。私としては、各曲での4人それぞれのすぐれた個所を一つ一つ指摘したいのだが、もう残り字数も少ないし、ある意味ではそうすることはミステリーの犯人の名を明かしてしまうのと同じなので、聴き手にとってはかえってそうしないほうがよいかもしれないと思う。だから、アートペッパーという稀代の名手と、ガーランド〜チェンバース〜フイリー・ジョーからなる黄金のリズム・セクションとによってここにくりひろげられている手に汗にぎる、あるいは息をのむような輝かしき好演の数々を、ご自分の耳、心、体で十二分に味わっていただきたいと思う。ちなみに、この名セッションを遺した4人、アートペッパー、レッド・ガーランド、ポール・チェンパース、フイリー・ジョー・ジョーンズは、すべてもうこの世にいないのである。
[Apr. 86/久保田高司]
●本解説はCD初発売時のものを使用しております。
(出典 ライナー・ノート)
3 CDの聴き方
アート・ペッパー・ミーツ・リズム・セクション
ジャズの名盤と言われるものは、いくつかの特質を備えている。まず誰にでも聴きやすいこと。そして印象的な「名曲」が必ず入っていること。最後にもちろん、リーダーとなるミュージシャンの音楽的な個性を正確に反映させている名演奏であることなどだ。このアート・ペッパーのアルバムはそれらに加え、録音がよいということでオーディオ・マニアたちの「標準盤」としての名声も確立させた珍しいケースである。
聴きやすいというのはあいまいな表現だが、経験的に言うとミュージシャンの技量の高い演奏は概して聴きやすい。ヘタな演奏は、どこがどうと指摘できなくともそれだけで耳に引っかかるのだ。とくにサイドマンの質が悪いとリーダーの演奏の足を引っ張るだけでなく、音楽全体のノリが悪くなり、それだけで感興を殺がれる。もっとも聴きやすいだけで後に何も残らない演奏もあるが、これはそういう心配のない折り紙つきの名演である。
ミュージシャンの技量が高いのも当たり前で、この作品は当代一流のジャズ・グループ、マイルス・ディヴィス・コンボのリズム・セクションである、ピアノのレッド・ガーランド、ベースのポール・チェンパース、ドラムスのフィリー・ジョー・ジョーンズをそっくり借りて録音されたものなのだ。タイトルの「ミーツ・ザ・リズム・セクション」というのはそのことを表している。
次いでこのアルバムが有名なのは、女性ヴォーカリスト、ヘレン・メリルの名唱(→スタンダードの章を参照)で知られる「ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ」が、ペッパーーの情緒纏綿たる名演奏によってファンの心に強い印象を刻みつけたからだ。そしてその情緒性こそがアート・ペッパーの個性であってみれば、このアルバムが彼の代表作であるのもまったくうなずける。
録音についてはあまり関心のない方もおられるかもしれないが、このアルバムの制作元であるコンテンポラリー・レーベルは、ロイ・デュナンという、ブルーノートのルデイ・ヴアン・ゲルダーとも並び称される名録音技師を抱えており、ウエスト・コースト・ジャズ特有の明るいペッバーのアルト・サウンドを的確に捉えているところから、何種類もの高音質CDが内外で発売されている。オーディオ・マニアの方は一度いろいろ比較試聴してみるのも一興だろう。
聴きどころは、典型的な白人ウエスト・コースト・ジャズマンであるアート・ペッパーが、全員黒人のリズム・セクションと共演してもまったく違和感がないどころか、あたかもレギュラー・グループ(いつも演奏を共にしているグループ)のような息の合った演奏をしているところである。アート・ペッパーの自叙伝「ストレート・ライフ」(スイングジャーナル社刊)を読むと、ある朝目を覚ますと急にこのレコーディングの話が持ち上がり、半年もの間練習もせず手をつけていなかったアルト・サックスを慌てて修理するという場面が描かれているが、それはいくらなんでも眉唾のような気がする。それほどこの日のペッパーは出来がよいのだ。
ペッパーの特質は、ちょっと矛盾しているようにも思える「明るい哀感」とでも言うしかない独特の持ち味にある。彼のアルト・サックスの音色はあくまで軽やかで明るいのだけれど、そこから紡ぎ出されるメロディには、独特の哀愁を帯びたマイナー調の響きがあるのだ。そしてその個性は我々日本人の感性にフィットするのか、一時期活動を中断していたペッパーの再起を暖かく迎えたのは、日本のファンの熱狂的な支持であった。
(出典 ジャズ完全入門 !)
「ジャズの名盤2」の目次に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last Updated 5/31/2001]