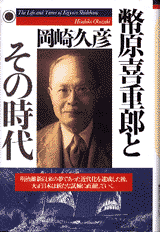
岡崎久彦著 著
(P H P研究所)
2000年4月20日
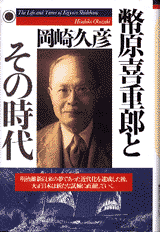
目 次
1. 著者紹介
2. 本の目次
3. あとがき
1. 著者紹介
岡崎 久彦(おかぎき ひさひこ)
1930年大連生まれ。東京大学法学部在学中に外交官試験に合格し外務省に入省。1955年ケンブリッジ大学経済学部学士及び修士。在米日本大使館、在大韓民国大使館などを経て、1984年初代情報調査局長に就任する。その後も駐サウジアラビア大使、駐イエメン大使を務め、1988年より駐タイ大使。現在は博報堂特別顧問。
著書に『隣の国で考えたこと』(中央公論社、日本エッセイストクラブ賞)、『国家と情報』(文芸春秋、サントリー学芸賞)、『戦略的思考とは何か』(中公新書)、『国家は誰が守るのか』(徳間書店)、『国際情勢判断』『小村寿太郎とその時代』『陸奥宗光とその時代』『情勢判断の鉄則』『日本外交の分水嶺』(以上、PHP研究所)など多数。
第11回正論大賞受賞。
2. 本の目次
第一章 新世代の外交官 11
−典型的な平和な時代の真面目な秀才
明治生まれの新世代人/教育熱心な中産階級の家庭/明治人らしい剛毅さをあわせもった幣原/桂園時代の安定期/やんちゃ坊主だった西園寺公望/けっして反体制的な自由民権派ではない/政治家・西園寺/大正政変/新しい時代の幕開け
第二章 アメリカの世紀の始まり 35
−新興日本と新興アメリカが太平洋で遭遇する
アメリカ史の転換期/マハンの『海上権力史論』/大海軍国への道/ローズヴェルト大統領の帝国主義政策/アメリカの国際政治とは/燃えあがる日本人差別/白人の警戒心を高める日系移民/アメリカ艦際の訪日/ジェイムズ・プライスの見識/デモクラシーの復元力/幣原の危機回避の努力/日米友好は少数の人が必死になって支えているだけであった
第三章 混沌の中国大陸 59
−拙劣を極めた21箇条要求
辛亥(しんがい)革命以後の中国の歴史をどうみるか/不撓不屈の革命家・孫文/日本は中国の革命志士たちの策源地であった/宮崎滔天(とうてん)の思想/新興日本に将来の夢を託して/日本外交の対応/日本の満洲進出積極論/欲張りすぎの二十一箇条要求/天下の非難を浴びる愚行だった/失った信頼は取り戻せたか
第四章 日英同盟の時代 85
−その時代、英国紳士は日本人の理想だった
幣原の信念はどこからきているのか/典型的な英国紳士/英国の外交センスへの敬意/英国流のコモンセンスと日本のアングロ・フィル/理想の官僚としての幣原喜重郎/議会民主主義達成への時代の潮流/政党政治腐敗の前奏曲/陸奥宗光(むつむねみつ)の遺志を継いだ男・原敬(たかし)/政党政治の幕開け
第五章 日英同盟の岐路 107
−日本は第一次大戦で同盟強化のチャンスを見逃した
歴史の大きな転換点/南洋群島をめぐる英米の思惑/伊吹の武士道的行為/慎重だった日本の派兵/白人同士の戦争/将来の軍事バランスへの顧慮/英国の失望/「日英同盟は脆い紙切れにすぎない」/それでも英国の懐は深かった/出兵のシンポリックな意義
第六章 ロシア革命とシベリア出兵 133
−ロシア革命の余波は日本にも及んだ
憎しみの哲学として共産主義/思想的不安感の瀰漫(びまん)/日露協約と帝政ロシアの崩壊/英、仏、米の思惑/シベリア出兵が決定される/一方的なアメリカ軍の撤退/幣原外交の冴えとその功罪/守るべきであった対米関係重視の戦略/原敬の信念
第七章 パリ講和会議 159
−同盟国英国の老練な外交が日本を救った
一等国日本の最初の晴れ舞台/アメリカ外交の建前と本音/人種差別撤廃の提案/激昂する日本の世論/激動の中国大陸/西原借款/石井・ランシング協定の成立/協定成立の背後/再び同盟国英国に救われる/二十世紀の二つの新たな潮流
第八章 日英同盟の終焉(しゆうえん) 183
−「旧外交」と「新外交」の岐路に立たされた幣原の選択
閉じこもるアメリカ/日英同盟とアメリカ/同盟の存続か廃棄か/バルフォア試案/幣原外交の始まり/信頼と自信のなかにひそむ陥し穴/幣原のウィルソン主義的信念/「新外交」は国際平和に有効か/同盟と集団安全保障/もし日英同盟が継続していれば
第九章 平和と軍隊 209
−ワシントン軍縮を成功させた加藤友三郎の見識、幣原外交の冴え
なぜ軍縮が成立したのか/幣原のよき理解者・加藤友三郎/山県有朋の死/原敬の現実主義/帝国国防方針の作成/二個師団増設と八・八艦隊計画/理論的には正しかった宇垣軍縮/反軍思想が昂揚した時代/近代日本の一つの原点
第十章 幣原外交の開花 235
−外相に就任した幣原は外交の新機軸を開いた
原内閣と高橋内閣/政党政治に対する幻滅/デモクラシー熟成の条件/清浦内閣解散と護憲三派の結成/「憲政の常道の時代/外務大臣幣原喜重郎/歴史的な外交演説/中国内政不干渉主義を貫く/原則を固く守って断じて妥協しない/中国の関税自主回復を支持/同情と同時に酔めた観察
第十一章 潮の変わり目 259
−幣原の協調路線に国民世論は反発した
幣原外交の基礎を侵蝕する国際情勢の変化/混乱状態の中国/浸透するソ連共産主義/一九二七年の南京事件/心臓の複数性/田中義一内閣の成立/特級品ではないが超一級品の人物/帝国主義の申し子・森烙(かく)/コミンテルンか中国ナショナリズムか
第十二章 中国統一の気運に直面する田中外交 285
−張作霖爆殺事件はその後の日本に決定的な悪影響を及ぼした
第一次山東出兵/東方会議と田中の対中政策/田中上奏文/蒋介石の第二次北伐/日中関係の転機となった済南事件/張作霖の爆死/ケロッグ=ブリアン条約/田中内閣の退陣/軍部暴走の発端
第十三章 幣原外交の最後の業績 113
−時代が変わっていく中、幣原は少しも変わらなかった
外務大臣に復帰/中国とソ連を説き伏せる/大正デモクラシーが残した最後の業績/政友会の党略/統帥権の法的解釈/最後の悲劇となったロンドン条約/行き詰まる内外情勢/マクマリーの観察/中国の革命外交/反旗を翻した在満邦人
最終章 幣原外交の終焉(しゅうえん) 337
−幣原の辞任で日本は対米外交の貴重な資産を失った
満州事変の序曲/面従腹背の陸軍/破局は時間の問題であった/幣原外交の行き詰まり/日本陸軍が生んだ天才・石原莞璽(かんじ)/石原の満州経略計画/柳條湖事件の勃発/国際連盟への提訴/表舞台から姿を消す幣原外交/幣原外交とはなんであったか/近代目本の原点であった時代
あとがき
文献目録
幣原喜重郎 年表
索引
3. あとがき
あとがき
この本が扱うのは、1910年代と1920年代である。もっと正確に言えば、1911年の中国の辛亥(しんがい)革命から1931年の満州事変に到る20年間の歴史である。これは日本近代政治史の中で扱いのもっとも難しい時代である。
1911年の辛亥革命で、アジアは動乱の時代に入る。日本では11年には明治大帝が崩御され、まだその諒闇(りょうあん)も明けぬうちに藩閥に対する国民の反乱ともいうべき大正政変が起こり、明治は、たちまちに遥か遠くに去ってしまう。そして、18年の原敬内閣成立を経て、24年の護憲運動以降、遂に政党政治が藩閥に勝ち、やがて、政友、民政の二大政党デモクラシーが達成される。その時代を象徴するのが本書の主人公である幣原喜重郎の国際協調路線である。そして、それに終止符を打ち、次の昭和の動乱の時代へと導くのが1931年の満州事変であった。
ところが、この時代はどういう時代だったか?という問いに対して明確なイメージを持っている人は少ない。なぜか印象が薄い時代なのである。
その一つの理由は人間の記憶の短かさにある。人間の記憶はつくづく短いものと思う。かの碩学キッシンジャーであっても、その記憶はナチス時代のドイツ、軍国主義時代の日本までであり、ヴァイマール共和国、大正デモクラシーにまで遡らない。ドイツか日本が過去戻るとすれば、その原点は1930年代だという既成概念が振り払い切れないようであり、それが日本警戒論につながっている。
現在社会的に発言されている最後の世代である80歳代が20歳になった時と言えば、1940年、もう軍国主義時代の真只中であって、大正デモクラシーは、ほとんど痕跡もなくなっていた。また現在言論界、思想界の中枢である50代60代の人々が、その一世代30年年上の親や教師から聞き学び、自らの幼時の体験と併せて理解できる時代は、せいぜい1930年どまりであり、それ以前に遡ることはない。つまりこの本の扱う時代は、ちょうど、今生きている人の記憶からは、忘却の淵を隔てた遠い過去の時代なのである。
愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶという。今生きている人の個人の記憶や経験で理解できないことならば、歴史をひもとけばよいということになるが、その歴史がないのである。ないというよりも、ありとあらゆる偏向史観のために、まともな理解が困難になっているのである。
日本の歴史は、明治の薩長史観に始まり、それがやがて皇国史観、軍国主義史観となり、戦後はマルクス史観、それがさらに過激化して反体制史観という各種の偏向史観によって、各時代の流れの本質が見えなくなるほど、ズタズタに切り裂かれている。
そしてそれは、おそらく、議会民主主義や政党政治についての日本人の判断が長い間固まっていなかったところからきているのではないかと思う。
明治維新直後、大久保利通や木戸孝允(たかよし)は外遊して、欧米の進んだ文物に触れ、日本の後進性を認識して、近代化の決意を固めた。
日本が鎖国している間に産業革命を経験した欧米の科学技術の進歩にはもとより驚嘆したが、それは学習と資本の投下でどうにか追いつけると感じた。しかし、とうてい一朝一夕には追いつけないと思ったのは、鎖国250年の間に、英国の名誉革命、アメリカ独立、フランス革命、そして1948年に到るヨーロッパの諸革命を経験した欧米における議会民主制度−当時は「憲政」と呼ばれた−の発達であった。
そうした明治の初心に戻れば、近代国家と近代軍隊を建設して、明治の終わりに強大ロシアを破って列強の一つとなり、そして明治憲法を制定して、大正時代に議会民主主義、それも政党が軍の上に立つ二大政党時代を現出したのであるから、それで日本の近代化のゴールは見事に達成されたことになる。日本が帰るべき原点は1930年代でなく、維新以来の夢が達成された大正デモクラシー時代だと言って少しもおかしくはないと思う。
ところが、その前者は、戦争をして勝ったのだからわかり易い。したがって、それについての認識はほぼい一致しているのに、後者についての認識が四分五裂のままなのである。
まず、かって内藤湖南も指摘したように明治維新後の歴史は薩長史観であった。一言で言えば、薩長を中心とする維新の尊皇の志士たちが幕府を倒し、たちまち日本中が夜が明けたよぅになって、近代化したという史観である。
ところが明治の自由民権運動−より正確には議会開設運動は、薩長藩閥体制打倒が終始その目標であったのだから、薩長史観によって正当に評価されるはずもない。薩長藩閥は、憲法制定後も、政党政治そのものを理解しようとしなかった。第二回総選挙の大選挙干渉の際、内相品川弥二郎は、「政党は国家の公敵、不忠不孝の徒であり、その撲滅こそ君国に忠たるゆえん」と公言した。
その時品川は、「破壊主義の徒、横暴の議論を逞しうし、あえて天皇の大権を侵犯せんとし」と言っている。当時の民党、自由党は暴力蜂起のはね上がりなどはもうとっくに整理した正統的な議会政党であり、憲法上正当な予算審議権を行使しただけであったのだから、品川の論は単なる無知、無理解である。
しかし、その考え方は、藩閥衰退後は皇国史観にとって代わられ、昭和に入って天皇機関説批判となり、君権が議会の制約を受けるという明治憲法の大原則さえ危うくなる。
その後にくる軍国主義史観では、政党政治は腐敗堕落の代名詞となった。
先に述べたように、今でも残っている世代がうっすらと覚えているのは、大正デモクラシーや幣原の軟弱外交に対する反発である。
権門上に奢れども国を憂うる誠なく
財閥富を誇れども社稜(しやしよく)を思う心なし
農村は疲弊して娘を売っているのに、西園寺公望、牧野伸顕、幣原喜重郎などの顕官、紳士は財閥と結託して悠々たる生活を楽しんでいる、というイメージである。
もっとも、農村の疲弊は、大恐慌後かなり時間を経てからの後遺症であり、大正デモクラシー時代の話ではないのであるが、このあたりのイメージは重複し混同されているらしい。
戦時中の思想は長く抑圧されていたが、最近ようやく解放されて、当時の革新思想を正面から見直すことができるようになった。そうなると、先に書いた、現在生き残っている世代、とくに歴史について高い問題意識を持つ人々の心の中にある潜在的イメージでは、大正デモクラシーについて否定的になる傾向がある。雑誌「正論」の投書欄などを見ると、復活しつつある歴史観は、圧倒的にこの1930年代以降の日本の雰囲気を背景にするもののように思える。
他方、戦後の左翼史観が目ざしたものは、社会主義であって、自由民主主義ではなかった。とくに彼らがブルジョア・デモクラシーと呼んだものでは決してなかった。したがって、大正デモクラシーの評価はおのずから低くなる。
さらに反体制史観となってくると、判断の基準はもっと単純化されて、権力に抵抗したものはすべて善、権力にすり寄ったものはすべて悪となる。それによって、明治大正にかけての憲政発達史はズタズタになって意味をなさなくなっている。
自由党の活動については、板垣退助以下の主流派の動きよりもほんの一部のはね上がりにのみ関心を払い、自由党が政友会になると、自由党の死と呼ぶ。
こうして明治の自由民権運動が各選挙区の中で育てた政治的地盤が、藩閥の弾圧でもどうしようもないぐらい強固に根づき、それを基盤として政友会が生まれ、原敬内閣の成立に導いていく日本の政治史がとうてい理解できなくなってしまっている。
こうした各種の偏向史観に加えて、占領軍史観というものがあると思う。歴史観というほど学問的なものではないが、明治以来大東亜戦争に至る日本の歴史はすべて悪であり、アメリカの占領と新憲法によって、日本は新たに生まれ変わり、善の道を歩むようになつたと教えようという、占領軍の政策によるものである。そもそも戦後日本のデモクラシーはライシャワーなどの進言により、占領軍が大正デモクラシーを復活させたものであるが、占領当局としては、この事実は伏せて、戦後のデモクラシーは、日本というまったく根のないところに占領軍によって新たにもたらされたものだと教えようとした。大正デモクラシーにはふれても、それは戦後の民主主義とは較べものにならないほど後れたものだったとの印象を与えようとした。
これは、軍国主義時代の言論統制に優るとも劣らない厳しい占領軍の言論統制の下で、国民の中にかなり深く浸透した史観である。軍国主義時代の厳しい検閲は1938年(昭和13)の国家総動員法の頃から敗戦までの7年間と考えれば、占領は1945年から1952年までの七年間であるから、同じくらい強い影響を国民の中に残してもなんの不思議もない。その上、この日本の過去をすべて悪とする史観は、占領終了後も、今度は日本を弱体化させたままでいさせようというソ連、中国の共産側プロパガンダと、これを受けた日教組や、新聞・出版関係の労組によって維持されたので、軍国主義偏向よりももっと長い期間、国民に影響を及ぼしている。
これだけの偏向史観に囲まれていては、大正デモクラシーの公正な評価が生まれてくるはずもない。どれ一つとっても、まともに評価することを故意に避けようとする史観ばかりである。この事実は読者にはもうわかっていただけると思う。
さて、これをどうしたらよいのかであるが、それを直す方法は、ただ、かきがらのように重なっている偏向史観を取り除いて、中の真実を求めるしかない。
私は今までの史観に代わる新しい史観をうち立てようなどとは毛頭考えていない。
私は長い間、情勢分析と判断が本務であった。情勢判断にあたっては、いかなる主観も 感情も、願望も一切まじえてはいけない。それが鉄則である。「新しい史観を」作ろうなどと考えるだけで、もう判断がゆがんでくることは経験でよく知っている。
私にできることは、『陸奥宗光(むつむねみつ)とその時代』『小村寿太郎とその時代』を書いた時と同じように、あらゆる偏向を排して、真実だけを、それも真実と真実の間の大小軽重のバランスを失しないように努めながら、私なりに書いたものを、一章毎に政治史、外交史、軍事史の先生方の御批判を乞いつつ、何度も書き改めていく方法以外にはあり得ない。今回もその方法にしたがった。そうやって偏向を排除していけば、おのずから真実が浮かび上がってくるであろうと考えたからである。その結果たどりついたのが、この本であるとご理解いただければ有難い。
あとは二つだけ付言したいことがある。一つは、別に「新しい史観」というわけではないが、こうして書いているうちに、「どうもこういうことではないか」と思うに到ったことがある。
それは第10章240頁のデモクラシー熟成の条件のところに書いた通り、大正デモクラシーと、現在の日本のデモクラシーとの間の、ほとんど唯一の、かつ、最大の違いは、明治憲法と現行憲法の違いでもなく、統帥権の独立でもなく、ただ、間に軍国主義時代があり、一つの大きな試行錯誤を経て、デモクラシーに対する日本国民の感覚が熟成されたことにあるようだということである。
日本だけの事情をみると、ああだこうだと細かい議論はあり得るが、ヴァイマール共和国のドイツと今のドイツ、50年代末にデモクラシーを経験したトルコ、タイ、韓国、フィリピン、ブラジル、チリ、アルゼンチン等が、その後独裁政治を経て、また現在デモクラシーに回帰している姿をみると、これがデモクラシーというものの本質からきているものではないかと思われる。
もう一つは、これも世界史の流れの判断からくるものであるが、もはや私の信念と言ってよいものである。もちろん情勢判断する者は信念など持ってはいけないのであるが、これは信念というよりも変わりようのない私の考え方である。
情勢判断では、事実関係を仔細に見ている人がいちばん強い。過去一年間の国際政治の流れ、さらに今後の会議や要人の日程などを詳しく知っている人には、その先一、二カ月くらいの国際情勢の大筋は見える。過去十年をよく見ている人は、あと半年ぐらい先までは見えてくる。
あと三十年、あるいは半世紀の世界と日本の将来を見るには、三、四百年遡(さかのぼ)らねばならない。
四百年といえば、約四百年前にイギリスがスペインの無敵艦隊を撃破して以来、アングロ・サクソンはオランダの競争を退け、ルイ王朝とナポレオンに勝ち、ドイツの挑戦を二度斥け、日本の進出を排除した。その間、一度敗けてからアングロ・サクソンとの協調を国家戦略とした国、即ち、オランダ、フランスは栄え、ドイツは二度目の敗北を喫した。
だから、私は、冷戦初期及び末期のソ連邦の脅威がもっとも厳しかった時代にも、遂にはアングロ・サクソンがロシアを屈服させる事に疑いを持たなかったが、果たしてそうなった。
アングロ・アメリカン世界の覇権は、少なくともあと半世紀は続くと思ってまず確実であろう。その間、日本はアングロ・サクソンの側に立っていさえすれば心配ない。
ほんとうは、西園寺公望の言うように、この前の大戦でも「英米の側で采配の柄を握っている」のがいちばんよかったことは間違いない。その意味で、私は、この本が扱っている時代について、西園寺、原敬、幣原と考え方が同じである。
しかし、日本はそれには失敗して、英米と反対の側について戦争に負けてしまったので、もう英米とまったく対等というわけにはいかない。18世紀以降のオランダ、20世紀のフランス、今のドイツ、ロシアと同じような立場である。
もっとも戦争に勝った英国も、今はアメリカと完全に足並みを揃えることによってのみ、国の安全と繁栄を確保している。湾岸戦争だろうとハイチだろうとどこでも、アメリカが出兵するところでは、いかに少数でも、アメリカ兵と肩を並べて英国の兵隊がいる。これは、第二章で紹介したジェイムズ・プライスの頃からの確立した英国の国家戦略である。
1945年(昭和20)夏、日本の敗戦直後、日本に完全な思想的空白、裏から言えば、今までの思想はすべて崩壊し、その後に生まれてくる数々の偏向や型にはまった思考が始まる前の、完全な思想的自由の一時期が訪れた。台風一過の朝のような清新な時期であった。
私の家にきた一人の客が呟いた。「あと何年したらアメリカに復讐戦ができるかな……」。これに対して、もう一人の客が言った。「二度と再びアングロ・サクソンと戦ってはならない。ドイツを見ろ。二度叩かれている」。
当時私は15歳の少年だったが、後者の意見が正いと思った。その感じ方は、その後40年の外交官の経験を経た現在でもまったく変わっていない。
今後左翼思想の後退にともなって、日本の外交路線をめぐる論議は、親米か、自主独立かの選択を中心にして行われると予想される。
その場合、私の情勢判断は明白である。日米同盟さえ堅持できれば、日本は、われわれの孫、曾孫の代まで、安全と繁栄を享受できると思う。そうでない場合、日本がどこまで漂流するか、それは私もわからない。
平成12年2月 岡崎久彦
「近現代史2」に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last Updated 8/31/2001]