Mirror for Americans: JAPAN
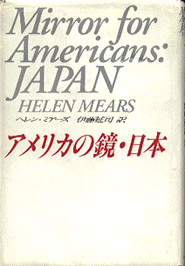
ヘレン・ミアーズ(Helen Mears)
伊藤 延司 訳
発 行 (株)アイネックス
発 売 (株)メディアファクトリー
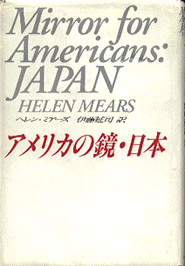
目 次
1. 概 要
2. 日本語版刊行にあたって
3. 訳者後書きより
4. 著者(ヘレン・ミアーズ)紹介
5. 目次
6. 内容紹介
1. 概 要
1949年日本占領連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが日本での翻訳出版を禁じた衝撃の書。戦後50年記念出版(帯書きより)。
1.パールハーバーは青天の霹靂ではなかった。アメリカは、さしたる被害なしに日本に第一撃を仕掛けるように画策した。
2.原爆投下は必要なかった。それは日本に対して使ったのではなく、ソ連との政治戦争で使用したのだ。
3.終戦直後、「アメリカは日本を裁くほど公正でも潔白でもない」と主張したアメリカの女性歴史家ヘレン・ミアーズ。日米関係が軋む今日、日本人必読の書!
2.日本語版刊行にあたって(白子 英城[アイネックス社長])
戦後50年のいま、われわれ日本人は、現代の歴史を日本中心の観点だけでなく、アジア、ヨーロッパ、アメリカを同じ時間帯で見すえるグローバルな視点から、なぜそうなったのか、をもう一度考え、議論し、そして現代史を総括しなければならないと思う。それによって、われわれ日本人が、過去にやってきたことで、何が悪かったのか、何が正しかったのかをしっかりと理解しなければならない。
3.訳者後書きより
1.「日本はなぜパールハーバーを攻撃したか」「なぜ無謀な戦争をしなければならなかったか」白子氏の疑問であるとともにミアーズがこの本を書いた動機でもある。
2.原題を直訳すると「アメリカ人(複数)のための鏡・日本」だが、このタイトルでミアーズがいおうとしていることは、こうである。「近代日本は西洋列強が作りだした鏡であり、そこに映っているのは西洋自身の姿なのだ。」
3.「私たち」には近代日本の犯罪に西洋文明が深く係わったというミアーズ自身の痛みが込められている。
4.ミアーズの「私たち」は、アメリカという国家であり、アメリカ国民であり、あるいは欧米植民地主義国家であり、西洋文明であり、キリスト教社会である。
5.すなわち、原題の「アメリカ人」は、ミアーズの意識では西洋的価値観を体現する「私たちアメリカ人=アメリカ」であると解釈することができる。
4.著者(ヘレン・ミアーズ)紹介
1900年生まれ。1920年から日米が開戦する前まで二度にわたって中国と日本を訪れ、東洋学を研究。戦争中はミシガン大学、ノースウエスタン大学などで日本社会について講義していた。1946年に連合国最高司令官総司令部の諮問機関「労働政策11人委員会」のメンバーとして来日、戦後日本の労働基本法の策定にたずさわった。1948年「アメリカの鏡・日本」を著す。1989年89歳で没した。
5. 目次
日本語版刊行にあたって……………白子英城 13
第一章 爆撃機から見たアメリカの政策……………15
1 フラッシュバック 17 7 クワジャリン環礁 42
2 島伝いの旅 23 8 罪なき傍観者 44
3 ヒッカム基地 27 9 グァム 47
4 パールハーバー 30 10 誰のための戦略地域か 49
5 ジョンストン島 36 11 戦略的占領 58
6 戦争犯罪とは何か 36 12 アメリカの墜落 67
第二章 懲罰と拘束……………75
1 なぜ日本を占領するか 77
2 攻撃と反攻 83
第三章 世界的脅威の正体……………93
1 つくられた脅威 96 5 降伏受諾 142
2 日本はいつ敗れたか 110 6 リーダーの資格 149
3 サムライ神話 114 7 日本は戦略地域か 150
4 銃もバターも 128 8 飢餓民主主義 152
第四章 伝統的侵略性……………157
1 神道からの解放 159 5 日本とアメリカ−その生い立ち 181
2 誰のための改革か 165 6 武士階級 195
3 「歴史的拡張主義者」 169 7 「間違い」の歴史 202
4 「伝統的軍国主義者」 175 8 思想からの解放 205
第五章 改革と再教育……………213
1 リーダーシップ 215 4 中途半端なカは引き合わない 226
2 歴史の証言 216 5 理論と実践 230
3 初めの占領 220 6 教育者の資格 237
第六章 最初の教科 「合法的に行動すること」……………243
1 歴史の復活 246
2 韓国の奴隷化 250
3 全体主義 259
4 改革か戦略か 262
5 国際教育なるもの 265
第七章 鵞鳥のソース……………269
1 満州事変 271 5 リットン報告 286
2 中国の歴史 273 6 日本は合法的に行動している 291
3 攻撃と反攻 277 7 確立された満州の秩序 296
4 アメリカの役割 279
第八章 第五の自由……………305
1 イデオロギーか貿易か 308 4 誰の不公正競争か 317
2 誰のための門戸開放か 308 5 飢える自由 324
3 誰のための自由経済か 314
第九章 誰のための共栄圏か……………339
1 戦略の失敗 341
2 倫理の失敗 344
3 日華事変からパールハーバーヘ 349
4 英語圏 357
5 誰のための共栄圏か 366
第十章 教育者たちの資質……………381
1 有罪か、無罪か 384 4 逆向きのリーダーシップ 396
2 力は引き合う 386 5 脅威とは何か 406
3 韓国の解放 389 6 パワー・ポリテイクスは逆境射する 411
付録 1 大西洋憲章 419
2 パールハーバー 420
国務省総括/上下両院合同調査報告 420
訳者あとがき 425
6.内容紹介
第1章 爆撃機からみたアメリカの政策 P.15
Bombsight View of Unanswered Questions of United States Foreign Policy
[要約]
著者が1946年占領政策に参画するために来日する際、真珠湾、グアムなど太平洋の島に立ち寄った折りに見聞きした事柄にふれながら、本書の基本的な考え方を示す導入部。10章のうち2番目に長い。
[抜粋]
1)パールハーバーは戦争の原因でなく、アメリカと日本がすでに始めていた戦争の一行動にすぎないようだ。したがって「なぜ日本がわれわれを攻撃したか」を考えるなら、「なぜわれわれは、すでに日本との戦争を始めていたか」について考えなければならない。
2)第3次世界大戦を防ぐためには、まず、第2次世界大戦の事実を整理する必要がある。
3)日本軍がフィリピンで犯した残虐行為は、日本の歴史にとって永遠の汚点となるだろう。日本兵が残酷で残忍であったことは明らかな事実だ。それでも、山下裁判とマッカーサー声明の根底にある考え方は受け入れがたい。戦争は非人間的状況である。自分の命を守るために戦っているものに対して、文明人らしく振る舞え、とは誰もいえない。ほとんどのアメリカ人が沖縄の戦闘をニュース映画で見ていると思うが、あそこでは、火炎放射器で武装し、おびえきった若い米兵が、日本兵のあとに続いて洞窟から飛び出してくる住民を火だるまにしていた。あの若い米兵たちは残忍だったのか? もちろん、そうではない。自分で選んだわけでもない非人間的状況に投げ込まれ、そこから生きて出られるかどうかわからない中で、おびえきっている人間なのである。戦闘状態における個々の「残虐行為」を語るのは、問題の本質を見失わせ、戦争の根本原因を見えなくするという意味で悪である。結局それが残虐行為を避けがたいものにしているのだ。
4)追いつめられてヒステリー状態にあったとはいえ、2千人の非戦闘員を殺すことは、もちろん恐るべき犯罪である。しかし、絶体絶命の状況の下で戦っているわけでもない強大国が、すでに事実上戦争に勝っているというのに、1秒で12万人の非戦闘員を殺傷できる新型兵器を行使する方が、はるかに恐ろしいことではないのか。山下将軍の罪は、なぜ広島、長崎に原子爆弾の投下を命じたものの罪より重いのか。
第2章 懲罰と拘束 P.75
Punish and Restrain
[要約]
なぜ日本を占領するか。米国が罰しようとしている日本の犯罪とは何か。日本の立場からの反論も述べている。この本の中で一番短い章。
[抜粋]
1)占領の目的は1945年9月19日、D・アチソン国務長官代行が語った言葉に要約される。「日本は侵略戦争を繰り返せない状態におかれるだろう。戦争願望を作り出している現在の経済・社会システムは、戦争願望を持ち続けることができないように組み替えられるだろう。そのために必要な手段は、いかなるものであれ、行使することになろう」
2)私たちの告発理由は「殺人」である。世界征服の一段階として、アメリカに対し「一方的かつ計画的攻撃」をかけたというパールハーバーの定義が告発の基礎なのだ。
第3章 世界的脅威の正体 P.93
Hindsight View of a World Menace
(Hindsight;目先の利かないこと[Forsightの対]、Menace;脅迫)
[要約]
日本が降伏した理由、日米の工業力・軍備の差、原爆投下の正当性に対する疑問など。第1章の英文タイトルとの対比に注意。この本の中で一番長い章。
[抜粋]
1)なぜ日本は降伏したのか。世界で「最も軍事主義的国家」であり、「ファナスティックな好戦的民族」がなぜ、武器をおいて占領を受け入れ、精いっぱい友好的な顔をして征服者に協力しているのか。
日本民族は好戦的ではなかった。日本の戦争機関は、占領や原爆投下のずっと前に完敗していたのだ。
2)1942年5月には、早くも私たちは日本軍の進撃をくい止めた。しかし、日本軍は別にアメリカ本土を目指していたわけではない。アメリカとオーストラリアの連絡路を切断するために前進していたのだ。1942年6月のミッドウェー海戦で、私たちは「海軍航空力の優位を確保し・・・その結果海軍力全体の優位」を確実にしていた。
3)パールハーバーの時点で日本の陸海軍が持っていた飛行機は全部で2,625機だった。
アメリカと連合国が太平洋の基地に配置していた飛行機は1,290機にすぎない。一見して日本の方が圧倒的に有利に思える。しかし、日本の飛行機は満州から太平洋まで、広く薄く配備しなければならなかった。月間生産量はわずか642機で、9ヶ月間このままの数字で推移している。1944年9月に月間生産量は最高の2,572機に達したが、それからすぐ原材料不足のために落ち始める。私たちのほうは1941年6月には月間1,600機の飛行機を生産していた。以後生産量は急速かつ着実に伸びて、1943年には9千機に達していた。1945年には私たちの1年間の製造機数は、日本が1941年から降伏までに製造した飛行機の2倍にのぼっていた。その上日本はアメリカの一に対して十の割合で飛行機を失っていた。
4)私たちはたった11日待った(ポツダム宣言の後)だけで、いきなり1発の原子爆弾を、そして2日後(原文のママ)にはさらにもう一発を、戦艦の上でもない、軍隊の上でもない、軍事施設の上でもない、頑迷な軍指導者の上でもない、二つの都市の約20万の市民の上に投下した。しかも犠牲者の半数以上が女子供だった。
原爆が投下されなくても、あるいはソ連が参戦しなくても、また上陸作戦が計画ないし検討されなくても、日本は1945年12月31日以前、「あらゆる可能性を入れても1945年11月1日までに」無条件降伏していただろうという意見をつけている(米戦略爆撃調査の公式報告)。
5)ソ連は中国領土内の一定領土及び財産を確保することを条件に、対日戦に参戦することを約束した(1945年2月7日のヤルタ会談における米ソの「最高秘密」合意)。
第4章 伝統的侵略性 P.157
Traditionally Agressive
[要約]
神道の意味、近代日本の変貌とその意味、日本と米国の生い立ちの違いなど。日本は伝統的な軍事主義国家かについても述べている。
[抜粋]
1)私たちの戦後対日政策には、神道と「天皇制」は本質的に戦争を作り出すものであるという考え方が組み込まれている。
神道と天皇崇拝は日本人の民族感情にとって重要な文化と宗教の伝統を表すものだった。これは、他の民族が固有の文化、宗教の伝統を持っているのと同じ国民感情である。伝統の力が強ければ強いほど、国家存亡の時には、戦争計画への国民統合に利用される。しかし、伝統が戦争の大義なのではない。ひとたび戦争が決定されると、伝統は防衛という名の戦争計画の背後に国民を統合するための手段となる。そうすることによって、為政者は複雑な戦争理由をわかりやすくするのである。
国家神道は、1868年、西洋の指導に応えて出てきたものだ。近代国家以前の日本では、神道は自然と祖先に対する信仰であり、習俗であった。
2)私たちは、日本人の性格と文明を改革すると宣言した。しかし、私たちが改革しようとしている日本は、私たちが最初の教育と改革で作り出した日本なのだ。
近代日本は西洋文明を映す鏡を掲げて、アジアの国際関係に登場した。私たちは日本人の「本性に根ざす伝統的軍国主義」を告発した。しかし、告発はブーラメンなのだ。日本の伝統的な発展パターンは、十九世紀半ば、アメリカを含む西洋列強の侵入と、ダイナミックな欧米文化の外圧的導入によって壊され、二つの異種文明が混在する日本が出現した。
3)ペリーからマッカーサーまで一世紀足らずの間に、日本は農業、手工業を中心とする交換経済から、産業、貿易中心の資本主義経済に移行した。そして、半独立の藩からなる緩やかな連合体は高度に中央集権化された国家に変わり、孤立主義を守る小さな島は軍国主義的、帝国主義的大国に変貌した。
近代日本は西洋の帝国主義列強に対抗するために帝国の伝統という虚像を身につけたのだった。
第5章 改革と再教育 P.213
Reform and Re-Educate---First lesons
[要約]
日本はもとは軍国主義的ではなかった。日本もかっては半植民地だった。欧米列強も日本の近代化を歓迎していた。米国に日本を教育する資格があるのかなど。
[抜粋]
1)ペリー以後の近代日本が、侵略的であり、拡張主義的であったのは確かだ。しかし近代以前の日本が平和主義であり、非拡張主義であったことも確かだ。
2)日本人は生まれつき軍国主義者であり、拡張主義者であるという宣伝文句ほど、私たちを混乱させるものはない。
15世紀、朝鮮に攻め入った孤独な将軍の遠征をとらえて、日本民族を生まれつきの軍事主義者と決めつけるなら、スペイン、ポルトガル、イギリス、オランダ、フランス、ロシア、そして私たち自身のことはどう性格付けしたらいいのだろう。これら諸国の将軍、提督、艦長、民間人は十五世紀から、まさしく世界征服を目指して続々と海を渡ったではないか。
3)日本の歴史を日本の立場から説明すれば、日本人は世界を征服する野望にとらわれていたのではない。世界のどこの国にも征服されたくないという気持ちに動かされてきたのだ。
4)この時期(1854年頃)から、十九世紀末までの日本はいわば半植民地だった。欧米列強の代表たちは、貿易のすべてを管理し、税率と価格を決め、沿岸通航を独占し、日本の金を吸い取り、99年間の租借権と治外法権に守られて日本に住んでいたのだ。
5)しかし、十九世紀後半になると、もはや外界と隔絶することも、時間をかけていることもできなくなった。日本は妥協を許さない欧米人を閉め出すことができなかった。欧米は自信を持った。科学と機械力で自信をつけた欧米人は、自分たちはアジア人やその他の「後れた」人種より本質的に優れていると確信して植民地に対していた。欧米の行動様式は欧米人が「正しい」と認めたものであり、それ以外の行動様式は「間違い」だった。欧米に順応すれば「進歩」であり、順応できなければ「反動」とされた。
6)私たちが戦争戦後を通じて、日本を非難する理由は、この中央集権的経済体制の発展が「全体主義」的であり、「戦争願望」を作り出したというものである。しかし、当時の欧米列強はこの発展を歓迎していたのだ。文明の後れた韓国と中国に西欧文明の恩恵をもたらす国、近代的秩序と規律を持つ国家が必要だった。だから日本の近代化が求められていたのだ。
第6章 最初の教科書「合理的に行動すること」 P.243
First Lessons ---"Do It Legal"
[要約]
1854年当時のロシアなどの状況、韓国の奴隷化、日本が最初に学んだことなど。英語のタイトルにあるFirst Lessonsは前章のタイトルのFirst Lessonsを受けている。2番目に短い章。
[抜粋]
1)1854年、アメリカが他に先駆けて日本を国際潮流に引き入れることができたのは、イギリスとフランスがロシアの地中海進出を阻止するために、クリミア戦争でトルコ帝国の支援するのに忙殺されていたからだ。英仏両国にしてみれば、ロシアの地中海進出は、極東に展開する自分たちの帝国と勢力圏にいたる独占ルートを脅かすものだった。
地中海で阻止されたロシアは、太平洋への出口となる不凍港を求めて、北東アジアへの進出をはかった。ロシアは英仏が中国から力で引き出した譲歩を利用して、日本と朝鮮北部に隣接する沿海州とウラジオストックを確保した。そして、日本本土の北に位置し、地理的には日本列島の一部である樺太と千島列島に入り込んだ。
2)いまになってみれば、日本が韓国を「奴隷化した」ことは明らかだ。日韓相互防衛のため、自国を併合してほしいと日本に要請した韓国皇帝の請願は侵略を糊塗するための法的擬制(リーガル・フィクション)であることも明らかだ。
3)日本と中国の関係は、全(九カ国)条約当事国と中国の関係がそうだったように、主権国家間の関係ではなく、大国と半植民地の関係だった。
4)国際関係の問題を正しく理解しようとする人なら、日本に対する最初の教育が問題を見事に解明してくれることに気づくだろう。今日私たちは「法と秩序」「条約の尊重」「国家の平等」「領土保全」「個々の人間に対する人道的配慮」といった、誰も否定できない原則にたって日本を非難している。しかし、最初の教育で日本は、そうした原則は文字に書かれた教典ではなく、力の強い国が特権を拡大するための国際システムのテクニックであることを、欧米列強の行動から学んだのだ。
第7章 鵞鳥のソース P.269
Source for the Gander(タイトルの意味については[抜粋]10)を参照)
[要約]
満州事変のいきさつと、欧米各国のとった態度。ここに太平洋戦争の発端がある。
[抜粋]
1)懲罰と平和の問題は、口で言うほど単純なものではない。まず第一に、満州事変に対する一般の見方が、きわめて複雑な事件を極端に単純化していることだ。第二に、一般に行われている日本非難は道義と人道を基盤にしているが、外国の侵略を押し止めるのは道義ではなく、国際法である。私たちが日本を罰する権利は、庶民感情や理想によっているのではない。超大国アメリカの工業力と軍事力を後楯にした米国務省の決定によっているのだ。
2)満州事変は、その後の日華事変同様、この複雑な状況の論理的帰結だった。韓国問題のときと同じように、大きな問題は中国での「権益」を守り、拡大しようとする西洋列強同士の対立だった。争っているのは、日本と中国ではなく、日本と欧米列強だったが、ロシア革命で状況が複雑になった。これによって中国の共産主義思想が日本の勢力拡大より大きな脅威になろうとしていたのだ。さらに問題を複雑にしたのは、アメリカの立場である。理想主義的政策を支持していたアメリカが、いまや即物的、国家主義的言葉でしか理想を語れなくなったことにいらだっていた。
3)アメリカ国内の世論は、この事件(満州事変)にそれほど関心を持っていなかったが、一応は中国を支持した。国際連盟加盟の小国はどちらかといえば中国についたが、大国の政府は態度をはっきりさせなかった。彼らにとって、問題は日本の意図だった。もし事件が日本の主張どおり、「法と秩序」を回復し、日本の「合法的財産」を守るための通常の「警察行為」なら、日本の法的立場は強い。日本は条約上の権利の枠内で行動したことになる。しかし、日本が満州併合を策しているなら事情は違ってくる。
4)アメリカと連盟がゆっくり動いている間に、満州の事態は急展開した。連盟が設置した調査委員会(リットン調査団)が満州に到着する前の1932年2月29日、満州人代表が瀋陽に集まり、中国からの独立と、独立国家満州国の樹立を宣言した。そして、リットン調査団が報告書を連盟に提出する前の1932年9月15日、日本は新しい国を独立国家として「承認」したのである。
5)しかし、日本は行きすぎたようである。1932年1月、満州事変は抗日運動が盛り上がる上海に飛び火した。上海の租界に権益を持つ各国の軍隊が警備体制についた。日中両国軍が衝突し、日本軍は中国側の拠点チャペイを攻撃した。各国は共同租界の周辺で起きたこの衝突に強い懸念を抱き、アメリカとイギリスは日本政府に抗議文を送った。何度か交渉が重ねられた結果、戦闘はやんだが、五月まで事態は収拾されず、日本軍は撤退しなかった。
6)日本にとって、リットン報告の見解は「法的」にきわめて重要である。もし、ある「軍閥政権」が外国勢力に認められたというだけで「中央政府」になれるなら、大国である日本が自分の勢力圏内にある望ましい政権を中央政府として認めてならない理由はないのだ。もし、中国の中央政府が報告で明確にされているように法的擬制なら、日本の満州も同じである、と日本は考えたのである。
7)日本がリットン報告にびっくりしたのは当然である。報告は日本の誇りを傷つけただけでなく、アジアの大国としての地位を根底から脅かすものであった。心理的衝撃は、日本は西側先進国ではないとされたことである。日本は五大国の高い席から、アジアの後進民族と同じ地位に引きずり下ろされたのである。
8)そこで日本人は、こうした非難は日本の行動に対してではなく、人種に向けられたものだという結論に行きつく。中国人もリットン報告を子細に読めば、同じ結論に達しただろう。国際連盟がリットン報告を受け入れ、連盟とアメリカが満州国を独立国として承認しなかったことから、日本は連盟を脱退した。
9)日本が満州で治外法権を放棄したことに対してもそうだ。欧米諸国が日本の行動に拍手を送ってあとに続けば、むしろ日本の侵略を非難しうる堅固で正当な論理的基盤を作れるはずだ。ところが、満州には欧米諸国の特権的地位を奪う権利はないと激しく攻撃したのである。
10)雌鵞鳥(グース)のソースは雄鵞鳥(ガンダー)のソースにもなる(訳注;西洋人に許されるなら、日本人にだって許される)のだ。
第8章 第5の自由 P.305
The Fifth Freedom
[要約]
日本側からみた満州事変の意義とアメリカの説明、日本にとっての満州の必要性、戦後の米国(連合国)の対日政策など。
[抜粋]
1)戦争原因を考えるに当たって、私たちは人種的、思想的側面にこだわりすぎ、経済的要因を無視している。日本の視点からいうなら、この戦争はアジア民族がアジアの支配勢力として台頭するのを阻止し、米英企業のために日本の貿易競争力を圧殺しようとする米英の政策が引き起こしたものだった。
それが米国政府の意図だったという見方は、アメリカ人なら誰も認めないだろうが、実際に行われた政策と米国政府の公式説明は、まさに日本の解釈を裏付けているといわざるを得ない。
2)日本が私たちの政策を(1)イギリスを全面的に支持する、あるいは(2)自分たちには必要ないが、とにかく日本にだけは渡したくない、あるいは(3)アジアでの戦略的利益を守る、ための政策であると考えたのも当然だった。
3)政策を判断するには、常に「平和と人類の幸福」という一対の物差しが必要だ。
4)戦後日本の絶望的状況にぶつかったアメリカの政策立案者は、政策を転換し始めた。日本の再建に数十億ドルの政府借款供与が考えられている。しかし、これは国民生活を考えてのことではなく、日本を対ソ連基地にすることが狙いらしい。同時に、米国企業は対日投資の効果を考え始めているようである。連合国の政策で破産した日本に資本を投入して、アジア市場への足場を築くという考え方が出ているのだ。
第9章 誰のための共栄圏か P.339
Whose Co-Prosperity Sphere?
[要約]
満州事変における連合国対日政策の失敗原因、日支事変さらに第二次世界大戦突入へのいきさつ、日本の立場と欧米の立場、現代への教訓など。
[抜粋]
1)私たちの目的である平和と人類の幸福を達成するための国際関係システムに向けて、私たちが指導的役割を果たせるかどうかの問題である。
満州事変に対する大国の政策の失敗原因は、はっきりしている。人道的目的というものは、パワーポリティクスの技術や特殊権益を考えていては達成できない。
2)1941年にようやくイギリス、オランダ、アメリカは対日貿易の断絶に踏み切ったが、もし1931年か1932年の時点でそうしていたら、日本は立ち往生していたはずだ。
3)戦略的に見ると、列強の政策は、(1)日本が拡張に向かわざるをえない心理的、経済的要因を強め、(2)同時に、日本が公然たる反抗を考えるほど強くなるのを助けて、失敗したのだ。
一方で、日本をイギリスの安全保障体制の一部として利用しようとする考えが、依然としてあった。日本を混乱状態にある満州地域の警察官にする。中国とロシアの緩衝材としてつかう。中国で共産革命が起きた場合に日本の力を借りる。中国の民族主義に対抗して、日本を条約国の統一を守る助けとする、という考え方があった。
4)民主主義国の倫理面での失敗はもっと深刻である。
米英二大国が1931年に満州事変に懸念を表明したとき、同時に治外法権を返していたら、不平等条約を放棄していたら、租借地と割譲地を返還していたら、自国の艦船と軍隊を撤退させていたら、満州を侵略であると厳しく断じることができただろう。
5)日本からみれば、問題はきわめて簡単だった。つまり、(1)満州に「合法的自衛」手段としての戦略拠点を確保し、(2)日本帝国圏(韓国と台湾)と満州、華北からなる経済ブロックを作って経済の安全保障を確立しようというのが日本の計画だった。そうすれば、これまでのように原材料物資と市場をアメリカ、イギリス、フランス、オランダに依存しなくてもすむ。
6)この時点までイギリスは蒋介石と日本の双方を牽制しつつ支援していたが、華北が独立を宣言し、日本と満州が共同して関税同盟と経済ブロックを結成する可能性が強まってくると、危機感を抱くようになった。イギリスは華北に大きな「権益」を持っていたから、支配的地位から降りようとはしなかった。そこで、イギリスは通貨再編成のために金融専門家、フレデリック・L・ロス卿を送り込み、銀の国有化計画を成功させて、蒋介石を外交的にも財政的にも強化した。同じころ、国民党大会初日の記念写真におさまろうとしていた汪精衛は、カメラに隠されていた銃に撃たれた。
7)1937年11月、日本は支配地域に共産主義の侵入を許さないための「自衛手段」と称して、独伊反共条約に加盟した。
8)1941年7月、アメリカ、イギリス、オランダは共同で各統治領内の日本資産を凍結し、貿易関係を全面的に中断した。
9)日本は、戦うか、三国の条件をのんで小国に身を落とすか、の決断を迫られることになった。日本の内閣は総辞職した。近衛公が去り、東条大将がやってきて、凍結措置は戦争行為であると無造作にいい放つ。次にくるのは必然的にパールハーバーとシンガポールの攻撃である。日本にいわせれば、これは当然の自衛行為であり、「帝国の存立」をかけた攻撃だった。そして戦争を論理的に正当化する法的擬制は大東亜の解放だった。
10)1934年、日本外務省情報部長(スポークスマン)、天羽英二が新外交政策を発表した。これは日本のモンロー・ドクトリンと呼ばれ、やがては大東を共栄圏に発展して行くものだが、この政策で日本は、日本だけが極東平和の責任を負っていること、中国にいる外国勢力が平和と秩序を乱すような行動をとったり、中国と日本の間に紛争をもたらすような行動をとった場合、必要なら武力をもってこれと対決することを明らかにした。日本外務省は、中国のいかなる政府に対しても、政治的借款の供与、政治顧問の提供は、一切禁止されると述べた。
米国政府は、日本がこの政策を「モンロー・ドクトリン」と呼び、アメリカの対中南米政策になぞらえようとしていることが許せなかった。しかし、日本から見れば類似性は明白なのである。問題は、私たちが日本と中国の関係だけを考えていたのに対して、日本は中国を支配している欧米列強と日本の関係であると考えていたことにありそうだ。アメリカのモンロー・ドクトリンはヨーロッパの支配が西半球まで及ぶことに反対するものだった。
11)国際関係を考えるさい、私たちは植民地体制の持つ意味を無視しているが、これは日本の犯罪に対する態度より、はるかに広い意味で重大である。満州事変と日本の共栄圏構想を再検証すれば、なぜ旧国際連盟が平和を守れなかったかが浮かび上がってくる。そして、現在の国際連合の間違いが見えてくるのである。
12)そこで、日本人は、今日のフィリッピンがかっての満州国と何ら変わらない存在であることに気づくのである。
13)満州事変とインドネシア事変(インシデント)は驚くほど似通っている。オランダは、日本が中国で行ったことを、インドネシアで行っている。これはかって中国が非難した行動なのだ。
今日蒋介石の中国が置かれている立場は、日本が最初の教育の時に置かれていた立場と同じである。アメリカ人はこの類似性について真剣に考えてみる必要がある。
14)日本は現地住民に独立を約束した。それだけでなく、独立を保障する具体的行動を進めていた。1935年にはすでに、満州での治外法権を放棄していたし、1940年には中国に正式に約束し、1943年には中国政府に租借地を返している。大戦中日本は、実際に、占領したすべての地域に現地「独立」政府を樹立していった。
15)すべての国が、法的擬制は敵だけでなく自分たちも持っていることを認める必要がある。東アジアの原住民が信託統治、あるいは非自治地域、あるいは戦略地域の名目で欧米の行政管理下にはいるほうが、植民地や信託統治領の行政のもとにいるより好ましいと考えているとは思えない。この人々にしてみれば、戦争は単にアジア人支配者を追放したにすぎない。そして英語圏がその足場を固め、アジアに近づいたというだけのことなのだ。
第10章 教育者たちの資質 P.381
Notes for Educators
[要約]
連合国の教育者としての適切性、日本の成功がアジアの知識人に与えたインパクト、パワー・ポリティクスに対する警鐘、イギリスの安全保障システムの評価など。
[抜粋]
1)日本と日本人の罪と罰という問題は単純ではない。確かに、日華事変の記録を普通に読めば、日本の指導部と軍隊の行為すべてが犯罪であるということができる。彼らの重大な犯罪には「情状酌量」の余地がない。彼らは残忍にも非戦闘員を爆撃した。彼らは他人の財産を略奪し破壊した。彼らは何百万の民衆に恐るべき惨禍をもたらした恐怖のの戦争の遂行者である。
しかし、日本が実際に「人類に対する罪」を犯したとしても、私たちが日本国民を懲罰するのは果たして正義だろうか。また、現在行っている懲罰が将来起きるかもしれない同様の犯罪の抑止力たりうるだろうか。答えは否(ノー)である。西洋列強が極東で行ってきたことをふり返り、戦争中の私たちの行動を認識し、私たちの現在の政策と連合国の戦争政策を日々の新聞紙上で追うならば、日本を有罪にしても民主主義諸国の罪は拭えないことがわかるのだ。日本が犯した罪は実際には何であったか、私たちが何で日本を罰しているのか、私たちがどういう根拠で罰せられるより罰する立場にいるのか、将来現れる侵略者にはたぶん理解できないだろう。
2)日本の本当の罪は、西洋文明の教えを守らなかったことではなく、よく守ったことなのだ。それがよくわかっていたアジアの人々は、日本の進歩を非難と羨望の目で見ていた。
3)政治意識を持つアジア人は日本の輝かしき成功からなにを学ぶべきか、よく理解していた。中国の革命指導者、孫逸仙(孫文)は「三民主義」の中で次のように書いている。
ベルサイユ講和会議で、日本は五大国の一員として席に着いた。日本はアジア問題の代弁者だった。他の諸国は、日本をアジアの「先頭馬」として認め、その提案に耳を傾けた。白色人種にできることは日本人にもできる。人間は肌の色で異なるが、知能には違いがない。アジアには強い日本があるから、白色人種は日本人もアジアのいかなる人種も見下すことはできない。日本の台頭は大和(日本)民族に権威をもたらしただけでなく、アジア全民族の地位を高めた。かってわれわれはヨーロッパ人がすることはわれわれにはできないと考えていた。いまわれわれは日本がヨーロッパから学んだことを見、日本に習うなら、われわれも日本と同じように西洋から学べることを知ったのである。
4)日本を見ればわかる。イギリスとアメリカに治外法権をは外してもらい、対等の主権国家として扱ってもらえるまでに45年かかった。中国はイギリスとアメリカに特権と治外法権を返上してもらい、対等の主権国家として認められるまでに104年かかった。
5)今日、私たちが日本の韓国「奴隷化」政策を非難するのは、要するに日本の植民地経営が著しく拙劣だったからである。しかし、一般に進歩の基準とされている、病院、学校、官庁(とくに現地行政機関)に占める韓国人の割合、通信施設の整備、産業化、資源開発などの分野でみると、日本の経営は他の植民主義諸国と比べて劣っていなかったばかりか、むしろ勝っていたといえる。
6)国際問題を正しく理解するには、ヤルタ協定をもっと詳細にみる必要がある。ヤルタ協定を考える場合、(1)満州の歴史、(2)私たちがパワー・ポリティックスと「暴力と貪欲」を否定するに際して、イギリスとアメリカの政策立案者が発した高邁な宣言、(3)ヤルタの取り決めにおける中国の立場、(4)国際関係における「合法性」の概念、の諸点からみると、西洋列強が「後れた」地域を「指導」する場合の教育システムの間違いが、実に鮮やかに浮かび上がってくる。
7)もう一つの「合法性」に関わる問題がある。ヤルタ会談の時点では、ソ連は日本と戦争していなかった。そればかりでなく、日本との間で不可侵条約を結んでいたのだ。イギリスとアメリカは、具体的条件を出して、ソ連が特定の期日をもって不可侵条約を破棄するお膳立てをしていたのだが、両国代表団はそれを違法とは考えてはいないのだ。その結果として、アメリカは8月6日(1945年)原爆を投下し、ソ連は8月8日宣戦を布告、翌9日に参戦した。
8)アジア人は一連の出来事をパワー・ポリティクスの最もひどい見本と思っているはずだ。アメリカ人に、それがわからないなら自己欺瞞である。
ヤルタ会談は、パワー・ポリティクスの実習としては画期的なものである。
9)私たちが掲げる平和と人類の幸福という目的に即してこのシステム(イギリスの安全保障システム[今日ではアメリカの防衛システムだが])をみると、明らかに不利となる事実を二つ指摘することができる。
第一は、日本はイギリスとアメリカの全面的協力がなければ、軍事大国になることができなかったということである。第二はソ連に関する事実である。イギリスのパワー・ポリティクスの絶えざる刺激がなかったら、ソ連はどうだったろうか。はっきりしているのは、平和を維持し、ソ連を抑止する目的でデザインされたイギリスのシステムは、そのいずれの目的も果たせなかったということである。パワー・ポリティクスは日本とソ連ではあらかに逆噴射したのだ。
10)日本を近代的軍事・工業国家に育てる中で、いくつかのことが見落とされていた。つまり、工業化はダイナミックなシステムに向かうこと、力はさらなる力の必要と渇望を生み出すこと、そして「安全な」同盟国は力を強めることによって安全でなくなること、パワー・ポリティクスが支配する競争世界で、ひとたび覇権の拡大(あるいは「合法的」拡張)に向かうと、物資と市場を競争相手に依存しているという事実が不安感と不信感を醸成させ、より多くのものを求めずにはおかない過剰「安全性」に駆り立てること、西洋列強がコミットメントでアジアに深入りし、日本がコミットメントで満州と華北に深入りしたように、コミットメントというものは国家を追い込むものであること、が見落とされていた。
付録 P.419
1.大西洋憲章
2.パールハーバー
国務省総括/上下両院合同調査報告