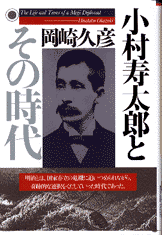
岡崎久彦著 著
(P H P研究所)
1998年12月4日
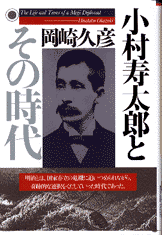
目 次
1. 著者紹介
2. 本の目次
3. あとがき
1. 著者紹介
岡崎 久彦(おかぎき ひさひこ)
1930年大連生まれ。東京大学法学部在学中に外交官試験に合格し外務省に入省。1955年ケンブリッジ大学経済学部学士及び修士。在米日本大使館、在大韓民国大使館などを経て、1984年初代情報調査局長に就任する。その後も駐サウジアラビア大使、駐イエメン大使を務め、1988年より駐タイ大使。現在は博報堂、千代田化工建設特別顧問。
著書に『隣の国で考えたこと』(中央公論社、日本エッセイストクラブ賞)、『国家と情報』(文芸春秋、サントリー学芸賞)、『戦略的思考とは何か』(中公新書)、『国家は誰が守るのか』(徳問書店)、『国際情勢判断』(PHP研究所)など多数。
第11回正論大賞受賞。
2. 本の目次
第1章 貧交行(ひんこうこう) 11
−貧乏を忘れ国事ばかり考えていた国粋主義者の信念
開成学校/小村の明治維新論/上士の伝統的士風/社交よりも読書と思索/顔のない外交/貧乏が度胸を支える/小村の国権主義・国粋主義/政党政治への懐疑/寡黙、禁欲的な国粋主義者
第2章 水を得た魚 31
−小村は時代が要請する「狂者」であり「けん者」であった(鈴木註 「けん」はけもの偏[へん]に環の旁[つくり]ですがフォントがないため平仮名にしました)
「狂者」と「けん者」/シナとの決戦が上策/日清開戦/満州経略の確固たる信念/閔妃殺害事件/「しまった、もう十年」/国粋主義勢力からの期待
第3章 瓦解する清帝国 49
−アジア最後の帝国は欧米列強になすすべなく屈した
アジア的大帝国の衰退/もはや「眠れる獅子」ではない/李鴻章を懐柔買収/シナに進出するドイツとロシア/米国の門戸開放政策と領土保全政策/大統領選挙の年の政治/日本が救った米の道義外交/義和団の乱/勝ち目のない戦争/規律厳正な日本軍/日本を代表できる人物/外相小村寿太郎
第4章 議会民主主義への執念 75
−自由民権運動の燈を絶やさなかった男・星亨[ほしとおる]の生涯
藩閥と政党の提携時代/第二の平和革命/桂太郎内閣/軍部独走の淵源/文官任用令/政党の反発/陸奥宗光が育てた奇才/孤軍奮闘の自由民権運動/星亨衆議院議長/憲政党分裂/立憲政友会/星亨が残したもの
第5章 ロシアの東方進出 99
−暴力と懐柔によって既成事実を重ねるロシアの手法
国境線は1メートルでも遠いほうがよい/ロシアの言葉の裏表/中央アジア経略の例/日本北辺への接近/修好から武力襲撃への豹変/本格化するロシアの極東進出/ペリー艦隊とおろしあの船/樺太領有の強い意志/対馬を窺う/ずるくて人がよい田舎もの 第6章 ロシアの満洲占領 121
−ロシアの意図を考えればいずれ戦争は避けられない
進撃するロシア軍/ロシアが朝鮮半島を放棄しない理由/ロシアの外洋への出口/「日本は永久に戦闘力を奪われなければならない」/日本の存立の問題/日本の「成人式」/ニコライの極東制覇の野望/コサックの蹄鉄のひびき
第7章 日英同盟 141
−小村の意見書が英か露かの選択に決着をつける
世界地図の空白地帯/世界を二分する超大国/臥薪嘗胆/ドイツが月下氷人的役割を果す/「日本兵はずばぬけて一番だと思う」/英国海軍からの謝意/日本の死命を制する朝鮮半島/名誉の孤立の終焉/アングロ・サクソンかスラヴか/小村意見書
第8章 日露開戦 165
−その背景には日本の弱点を補う「日英同盟」があった
満洲撤兵の意志なし/不可解だったロシアの進出/日英米共同戦線/ロシアの朝鮮半島進出/逃げ腰だった英と米/ついに開戦へ/開戦外交/資金と情報の供給源
第9章 日本民族の興隆期 187
−日本人の愛国心に世界は驚嘆した
時間との競争/遅滞作戦の誤算/国運を左右した大胆な人事/旅順艦隊制圧/エリートは率先して危険な任務につくべきだ/鴨緑江の戦いで初勝利/世界中で英雄となった黒木為禎(ためもと)/独断専行がことごとく成功/世界軍事史上不滅の大記録/「戦争こそ人類の徳と魅力が基礎である」/戦争とは何だろうか
第10章 死 闘
−旅順港攻略戦は日露戦争の最も悲痛な叙事詩だった 213
死を賭した戦い/陸の軍神橘中佐/死力を尽しての勝利/百三十日の死闘/日露両国の戦略上のディレンマ/真鉄(まがね)なすベトン/第三軍司令官乃木希典(のぎまれすけ)/死の争奪戦・203高地/武人の名誉/「ツアーリズム降伏の前奏曲」/日本の謀略戦 第11章 世界史の分岐点 239
−日本海海戦は奇蹟の大勝利
払底した弾薬/駆けつけた第三軍/日露戦争の関ケ原/満洲を朱(あけ)に染めた両軍の死屍/バルチック艦隊/対馬海峡か津軽海峡か/「半分なくすつもりで叩いてしまえ」/敵前大転回/信じられないほどの大勝利/「アングロ・サクソンの正統な後継者」/日本海海戦の世界史的意義/非白人の奮起
第12章 ポーツマス条約 265
−ローズヴェルトの説得にも小村は譲る気がなかった
「貧乏国がこれ以上戦争を続けて何になるか」/ローズヴェルト大統領の斡旋/領土と賠償については譲る気なし/ローズヴエルトの早期和平論/揺れ動くアメリカの世論/アメリカの対日態度の変化/日米共同の南満洲鉄道経営案/国の大きな運命を誤る/伊藤博文の知的エネルギー
第13章 韓国併合 291
−他に選択肢はあったのだろうか
日韓議定書/パワー・ポリティツクスの人・ローズヴエルト/桂・タフト覚書/無抵抗だったわけではない/保護国か併合か/伊藤の君子豹変/併合のほかに道はあったのだろうか/帝国主義時代に弱小国の安住の地はなかった
終章 明治の終り 309
日英同盟の改訂/世界政局の再編/第二次日露協約/条約改定の完成/小村と乃木の死
あとがき
文献目録
小村寿太郎 年表
索引(人名・事項) 3. あとがき
本書『小村寿太郎とその時代』は、明治維新から第二次世界大戦の敗戦に至る77年間の日本近代政治外交史の第二部として執筆されたものである。
私は、さきに『陸奥宗光』を書き、明治維新から日清戦争までの期間を書いたので、これはその続編である。ただし、この外交史はいずれ英訳することも考えているので、すでに発行した『陸奥宗光』はそのためには長過ぎるので、いずれ、短く書き直したものを出版する予定である。
日本近代外交史を書くことは昔から私の夢であった。
戦後初めての日本人としてケンブリッジ大学に入学したので、その頃は、戦中、戦後に英国で書かれた本をよく読む機会があった。そして感じたことは、戦争というものがいかに歴史の客観的判断をゆがめるかということであった。
英国が誇る最強戦艦プリンス・オブ・ウエールズを撃沈したマレー沖海戦において英国の海軍士官たちは、日本のパイロットの勇敢さに目を瞠った。しかし、「勇敢」(プレイブ、カレイジャス)とか「愛国的」(パトリオティック)とかいう英語はどうしても使えないのである。その場合英語ではファナティックな(気違いじみた、狂信的な)攻撃と表現された。
近代戦は第一次大戦以降は国家総力戦になった。その場合重要な役割を果すのは国民に対するプロパガンダである。傭兵や志願兵でなく、一般国民にまで戦争に協力して貰い、戦場で血を流して貰うためには、敵は悪の権化であり、味方は常に聖戦を戦っていると信じて貰わなければならない。同じ人間同士が戦うのであるから、現実世界にはそういうことはあり得ないのであるが、それを無理に信じこませるのがプロパガンダである。
戦時中のプロパガンダでは日本の方が強かった。日本が占領した地域は欧米の旧植民地だったので住民は当然解放を歓迎した。これに対して英米側は他にいうこともないので日本の残虐行為をいった。戦争は人を殺し合うのであるから残虐はお互い様であり、日本側も鬼畜米英などといったが、英米側はそれしかない。それも実体に乏しいので、「身の毛もよだつ」とか、「筆舌を絶する」とか、形容詞だけエスカレートした。
戦争が終ると、負けた国のプロパガンダは死滅するが、勝った倒のプロパガンダは歴史の記録として残る。私が居た頃は、こうした形容詞は、英語の書籍に雑誌に、至る所に残っていた。
本というものは一度出版されれば何時まででも残る。とくにアングロ・サクソンは歴史を書くことに優れている。中国と日本を除く世界中の歴史は、ペルシャ、インドのような国も含めて皆アングロ・サクソンが書いたといっても過言ではない。とくに英語が世界の通用語となっている現状では、英語で書かれた歴史が最終決定版となってしまう。このアングロ・サクソン史観で書かれた歴史は何時かは修正しなければならないと思っていた。
それから三十年も経って、今度は日本では教科書問題が起り、南京事件、従軍慰安婦など、戦時の行為に対するいわゆる謝罪問題が起きた。
戦争の記憶というものは通常一世代、三十年ぐらいで薄れ、あとは歴史家の仕事になるものである。ナポレオンがワーテルローで負けたのが1815年であり、その後は侵略者ナポレオンに対する批判侮蔑は激しかったが、1848年の革命の頃から、ナポレオンの業績はフランスのグロワール(栄光、国威)を輝かしたという史観に定着した。第一次大戦後のドイツ批判などはせいぜい十年ぐらいしかもたなかった。
日本でも、1945年の敗戦後30年を経た70年代後半には、戦争の問題はまったく過去のこととなっていた。当時私は防衛庁の参事官として国会答弁に三年間で三百回立ったが、過去の戦争に対する謝罪の問題や、周辺アジア諸国の感情の問題、まして南京事件や従軍慰安婦の問題などは、ただの一度も国会で言及されたことはなかったし、新聞にも一行も書かれていた記憶は無い。中国の新聞にも全く無かったと思う。
南京事件や従軍慰安婦の問題、戦争の謝罪の問題は、戦後五十年解決しないでほうって置いた問題というのは誤りである。一たん、歴史の過去となった問題が、戦後日本の極めて特殊な政治的社会的環境のなかで、意図的に、しかも誤報をきっかけに掘り起され、それが海外の反響を呼んで、新たに問題となったものである。
したがってこの間題が今後どうなるのかは、世界史に類例のない現象なので予測は難しい。発端が人工的、意図的なものであるから、意外に早く消え去るかもしれないとも思う。戦後五十年の節目でこの問題が大いに議論されたとき、私は積極的には議論に参加しなかった。私はつねに物を書く以上、それが後世に遺ることを覚悟しなければいけないと考えているので、十年経てば誰も問題にしないかもしれないことを殊更に論じるのは不見識のように感じたからである。
他方、この間題は、歴史の自然の流れを人工的に止めてしまって、教科書などで固定しようとしている問題でもあるし、他面、外国にとっては日本に対して交渉上優位に立つ武器として有用なものでもあるので、人工的にかなり長く続くものであるかもしれない。どちらになるか見通しが立ちにくい。
もし、これが長く続いた場合、最も心配なのは、これが未来の世代に与える影響である。
私は、かつて17世紀の英蘭戦争について調べて書いたことがある(『繁栄と衰退と』文芸春秋)。オランダは、スペインに対して英雄的に戦い、同盟国イギリスの危機を救っている。無敵艦隊の英本土侵攻を救ったのはオランダの功績である。
しかし、その後、三度の英蘭戦争を戦ったために、英国がスペインと生きるか死ぬかの戦いをしている最中に、オランダは金儲けだけしかしなかった蛭であり吸血鬼であったというのが英国のプロパガンダとなり、オランダが負けたためにそれがそのまま正史として残り、このオランダの功績はイギリスで書かれた歴史からはまったく抹殺されてしまった。しかし、私の本を読んだ日本人たちがオランダの人にその内容を話すと、オランダ人は眼を輝かせて、「それは私たちが子供の頃から繰り返し繰り返し聞かされた話です。どうして日本人がそれを知っているのですか」というという。
外国の歴史からは無視されても、オランダ人自身の英雄的な歴史は脈々としてオランダ人のなかに生き続けているのである。それが普通であろう。
しかし、日本の場合は、戦敗国として外国から偏向史観を押し付けられたのではなく、日本のなかの反体制的な勢力の偏向によるものなので、民族の伝統、歴史そのものが自らの手で抹殺されてしまう危険を蔵しているのである。
いまの教科書の不正確さを批判し、否定することは易しい。しかし、批判する以上、これこそが正しい史観だというものを持っていなければならない。またそういう正しい史観を持っていれば、偏向史観を批判したり、ああだこうだ論争に入る必要もない。ただそれを公表して偏向史観などは問題とするに足らずと無視すればよいのである。
これに反して、批判する側が、戦前の薩長史観、皇国史観を含む雑多な史観の寄せ集めで、整理がついていないと、ただ、論争の泥沼に入ってしまうだけになる。
しかし、どうすれば、真に公正、中正なる歴史なるものが書けるのだろうか。
歴史的な事実かどうかは学問的に検証できる。南京事件や従軍慰安婦などについて問題なのは、歴史的事実として検証できない怪しい記述が、教科書などに採用されているところにある。
しかし、もっと難しいのは、一つ一つの事実は真実であっても、歴史の大きな流れに関係のない局部的な事実をアンバランスに大きく取りあげている場合である。自分の主張に都合のよい事実だけを集めて、歴史の本当の流れを見ていない歴史をどうして直せるかということである。
事実と事実とのあいだの軽重、大小のバランスを判断するのには、何の客観的基準も法則も存在しない。基準とすべきはただ良識あるのみである。かつては、良識の代表のように皆に尊敬されている大先生が居てその人が通史を書けばよかったのであるが、学問の専門化が進み、通史の書ける人は少なくなったという。
私が人様よりすぐれた良識を持っていることなど主張する気はまったくないし、主張し得べくもない。私の取り柄といえば、外交と軍事の両方に実務の経歴があるということぐらいである。
そこで、本書の執筆にあたって私が取った手法は、草稿を三章ごとにまとめて、尊敬すべき歴史の専門家たちに読んで頂いてセミナーを開いて、教えをこ乞い、「そこまではいえないのではないか」、「それにはこういう反対の資料もある」というようなコメントを頂いて、「それならばバランスの取れた歴史といえる」と納得して貰えるまで書き直すということである。
物事の真実を追求するには、ソクラテス、プラトンが用いた対話が、いまでも最善の方法であるということであり、それ以外の方法は思い当らない。
近代政治史については御厨貴、井上寿一、坂本一哉の各先生、軍事については、桑田悦、平間洋一の各先生、外交史については、吉村道男、神山晃令(あきよし)各先生について教えを乞うた。各先生の無私の御協力には深く感謝申し上げる。
なお、文献については、ほとんどは孫引きである。かつて『陸奥宗光』を書いたときはすべて原典にあたって見たが、その結果得た結論は日本の学者は良心的であるということである。たとえ、結論は偏向している場合でも引用そのものは原典にあたって見ると極めて正確である。もちろん、原典にあたると、引用されてない部分に面白いところがあり、場合によってはその方が重要であると気付くこともあるが、一々それをやると無限の時間がかかり、通史を書くこととは両立しなくなってしまう。
日本近代史は、すでに多くの優れた研究者によって掘り起し尽されている。本書の目的はそれ以外の新しい事実を発見することにはない。それは今後益々出て来られるであろう優秀な若手の学者たちの御仕事であろう。
むしろ、近代史において、最大の問題であり、また、それが本書の目的であるのは、そうした正確な事実と事実のあいだの軽重のバランスを誤らない歴史を書くことにある。それを妨げる陥し穴は随所にあるが、新しい史実を発掘したなどと鬼の首をとったようにその部分を殊更に取り上げ、木を見て森を見ないことも戒心すべき陥し穴の一つであると思っている。
また、引用は、カギ括弧つきの引用であっても、なかの文章はなるべく、現代人にわかり易い文章に直した。また小中学生でも関心のある人は読めるように、小学校低学年以上の漢字にもルビをつけることにした。
なお、これだけの作業を始めることについては、私自身にそこまでの実力があるかどうかということの他に、五年余にわたると予想されるこの事業に集中することには私個人の人生設計上も、かなりの決心を要した。その間私を激励し、物心両面で支援して下さったのは、上野隆三氏を始めとする関西中心の財界の方々であり、その御恩はけっして忘れることは出来ない。
最後に、編集に当られた貞部(まなべ)栄一氏、今井章博氏、小林英史氏、ルビを振り索引、年表を作製して下さった東島裕子様、『Voice』に連載中の担当である横田紀彦氏、そしてセミナーの会場として種々の便宜をを与えて下さった外務省外交史料館の皆様に厚く御礼申し上げる。
また、博報堂岡崎研究所の小川彰氏、中島邦子氏、そしてすでに結婚退職された土橋孝子氏、それも含めて終始渝(か)わらぬ博報堂の御支援に感謝申し上げる。
平成十年秋 岡崎久彦
「近現代史2」に戻る
トップページに戻る
総目次に戻る
[Last Updated 8/31/2001]