酵母も微生物の一種です。ばい菌(細菌・酵母やカビ)からは病気を連想してしまいますが、微生物は有害なものだけではありません。
たとえば以下の食べ物は微生物がいないと作ることはできないのです。
ヨーグルト・チーズ・納豆・酢・醤油・味噌・パン・キノコ・日本酒・ワイン・ビールなどです。
酵母の発酵現象を実際に観察しながら、その不思議な世界を学んでみましょう。
以下のお話は 微生物と関った人々のお話 にやさしく書いています。
まずパスツールによる 微生物は微生物から発生することの立証
ドイツのシュワンによる生物学的発酵説
――アルコール発酵は酵母という微生物によって引き起こされることを唱える
ドイツのリービヒによる化学的発酵説
――アルコール発酵は分子の振動が糖に伝わると、糖が分解してアルコールができる。
1897年に決着
ドイツのブフナーによるアルコール発酵が生化学的触媒反応によることの証明
――酵母が死滅していても、酵母の細胞内から溶出したタンパク質の一種が引き起こす 1883年デンマークのハンゼンによりビール酵母の純粋培養に成功(ハンゼンの希釈法)
発酵とはなんぞや? その定義
細菌類、酵母類、糸状菌(カビ)類、藻菌類などの微生物そのものか、その酵素類が有機物または無機物に作用して、 メタンやアルコール、有機酸のような有機化合物を生じたり、炭酸ガスや水素、アンモニア、硫化水素のような無機化合物を生じ、 かつその現象が人類にとって有益となること
ビール酵母が溶液中にあるかないかということは大きな違いですね。
市販ビールでは麦汁1リットル中にほぼゼロ 手造りビールでは10億から100億もの活きたビール酵母が含まれています。
これは広域で、不特定多数の消費者に販売されているビールでは、酵母はことごとく取り除かれ、濾過されているためです。
市販の生ビールは「生」といえど単に熱処理をしていないという意味だけで、ビール酵母はすべて濾過されています。
このビール酵母がビールに深い味わいをもたらします。また体にも非常によく、最近健康食品で脚光を浴びていますが、それは濾過した時のビール酵母そのものです。
その他副原料の使用の有無などもあります。
市販ビールと手造りビールの製造工程の違いは次のようになります。
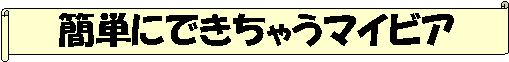
|
工程:沸騰したお湯にモルト缶の中身を混ぜます。 その溶液を冷やして,あらかじめ水を入れておいた容器に加えます。 ビール酵母を混ぜ,発酵栓をして10日前後発酵させます。 瓶に詰め換え、泡用の砂糖を入れ,3日ほど二次発酵をさせます。 さらに3週間ほど熟成させて出来上がりです。 飲めるまでの期間:約1カ月です。 一次発酵に10日前後 二次発酵に3日 その後3週間程寝かします。 作成の時期:平均気温が18〜26度なら室温で作成できます。 (5月から〜7月中旬と9月下旬〜11月ごろが作りやすいですね。) 費用は?:2000円程度で12〜18リットルできます。 |
ビール酵母のあわ立ちパワーは?
|
ビール酵母の実験をしてみましょう。 ビール酵母5gを200ccのぬるま湯に10分ほどつけておきます。(酵母の活性化) その後に大鍋で溶かしたワート溶液を200cc追加して酵母の状態を観察してみます。 |
 (入れた直後) |
 (1時間後) |
 (2時間後) |
発酵容器にどんな気体が入っているかローソクを入れて観察します。 アルコール発酵→酵母に含まれている酵素によって、単糖が、アルコールと二酸化炭素に分解されること 反応式:C6H12O6→2C2H5OH+2CO2 |
日本の酒税法における「酒類」とはアルコール濃度1%以上のものをいいます。
もう一つ、使用する原料の規制があります。
1.麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(麦芽の使用割合100%)
2.麦芽、ホップ、水その他政令で定める物品(米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でんぷん、糖類)(ホップに準ずるものとして、ルプリンまたはフムロン)(着色料としてカラメル)を原料として発酵させたもの。
ただしその原料中政令で定める物品の合計の重量が麦芽の10分の5を超えないもの
(麦芽の使用割合が67%以上)
副原料が麦芽の重量の50%を越えるとビールではなくなり雑酒(発泡酒)になります。
発泡酒はモルトの比率が低いというのはほんと?
ビールと発泡酒の違いは、酒税法における酒類の酒類・品目の分類の違いであり、1.使用原料と、2.麦芽使用率の2面があります。
酒税法上、「ビール」は麦芽の使用比率が約67%以上であること、副原料の種類も限定されています。一方、「発泡酒」は麦芽を原料の一部とした発泡性を有する酒類ですが、麦芽使用率により税額の差があるほか、唐辛子や果汁等「ビール」には使用できない原料を使用した場合にも発泡酒となります。
なお、発泡酒については麦芽の使用割合により税率が3分類に区分されています。
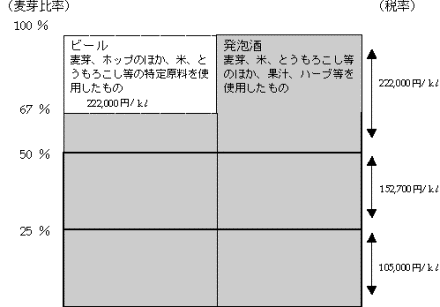
根拠条文等:酒税法第3条、第4条、第22条、租税特別措置法第87条の4
アメリカやイギリス・・オーストラリアなどの欧米諸国では自家醸造は禁じられていませんが、日本では現在、お酒(アルコール度1%以上のものをいう)の自家醸造は酒税法で禁じられています。
日本では、古くから米を醸した酒、どぶろくが各家庭で造られてきた歴史があります。
単に飲むだけのためでなく、その年にできた米で造ったどぶろくを神に捧げ、豊作を祝うといった神事や村祭りや冠婚葬祭などの行事には各家庭で造られてきました。
この江戸時代まではなんら規制を受けることなくできた個人の酒造りが、明治政府が制定した酒税法により今日にいたるまで禁止されています。
酒税法が成立した背景は富国強兵政策での近代化を推し進めた明治政府の財源拠出という事情があります。
明治32年に来るべき日露戦争に備えて自家醸造は一切禁止されました。
当時国家歳入の三分の一が酒税で賄われていたというから財源として非常に重要であったとは想像されます。
ちなみに今日では酒税が国家歳入に占める割合は4%にも満ちません。
市販の酒を買って飲むのはよいが、自分で造ってはいけないという論理は、たとえば市販のパンを買うのはいいが自分で作ってはいけないとか、音楽家の演奏を聴くのは構わないが自分で演奏してはならないということと同じになってしまいます。
ただし現行法律でも1%未満のビールを造ることは問題ないため、諸外国から多くのビールキットが輸入されています。