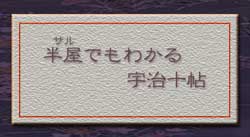光源氏と呼ばれた源氏の大臣が亡くなってから時は流れ、源氏の次男である梧桐は自らの出生に悩んでいた。若くして出家した母。そして父はなぜか、いつでも自分に厳しい目を向けていた。
現世一の実力者である兄、中宮である姉、元帝である秘密の兄(表面上は叔父)に引き立てられ、将来を約束されている梧桐。その身体からはえもいわれぬ高貴な香りが漂い、人々を魅了していたが、どうしても虚しさは癒えず、出家を願う日々だった。
梧桐の甥にあたる親王、八樹宮はことあるごとにそんな梧桐に張り合い、梧桐が高貴な香りを漂わせているのなら、自分は高価な香で勝負とばかりに香を焚きしめたりしていた。
そんな梧桐はある日、父の異母兄弟にあたる宮が俗聖として名高いことを知る。出家したくても出家できない立場の梧桐は宇治にあるその宮の家を訪ね、交流を結んだ。
ある日、宮の留守中に宇治を訪ねた梧桐は、都にもいないような美女が二人いるのを見かける。宮の姫である伊織と御幸だった。梧桐は知的で清楚な伊織にゆかしさを覚えるが、生涯を独身で通そうと思っている伊織には通じない。
そうしているうちに宮がなくなり、その葬儀を梧桐が取り仕切るなどしたため、伊織は妹の御幸と梧桐を結婚させようと考える。梧桐はそれを避けるため、かねてから梧桐の通う宇治に興味を示していた八樹に御幸を押しつける。しかし八樹は評判の浮気者。しかも家族のように接したい梧桐にも迫られ、心労のあまり伊織は死んでしまう。
愛する伊織を突然に失い、思い悩む梧桐は宇治の館を整備し、そこに伊織の人形を置いて供養しようと思いつく。
|
「………で」
「で、ってやだな半屋君。せっかくわかりやすいように解説してるのに」
「どこがだ。人がやめろって言ってんのに、べらべらべらべら話しやがって」
「えー。やめろなんて言ってないだろ。アァ?とかけっとか言ってただけじゃないか」
「ならやめろ」
「だって、追試って明日だろ。国語担当の青木君は二年の古文はやってないし、御幸君も嘉神君も転校生だし、梧桐君はああだし。それともアメリカ人のローヤーさんにでも教えて欲しいわけ?」
「………」
「ここからが盛り上がるところなんだよ。半屋君が出てくるし」
「フツーにやれ、フツーに」
「普通にやったって覚えにくいよ。俺はこれで一発で覚えたし」
「てめぇの脳がおかしいんだよ。とにかくまともにやれ。でなけりゃやるな」
「じゃあ続けるね」
そのころ、伊織と御幸に異母兄弟がいることがわかった。父である宮が認知しなかったので、その娘は母の連れ子としてひなびた場所で育てられていた。
御幸はその娘があまりにも伊織と似ていることに驚いた。それを梧桐に伝えると、梧桐はその娘―――半屋を伊織の人形の代わりに宇治の館に囲おうと思い立つ。
|
「はぁ?」
「せっかく盛り上がってきたのに水を差さないでよ」
「そりゃおかしいだろ」
「文句は紫式部に言ってよ。じゃあ続けるね」
「待て。とにかくその妙なたとえはやめろ」
「半屋君を女役にしたのがイヤなの? 意外に度量が狭いよね」
「ンなんじゃねぇ。とにかくやめろ」
「女役なのは平気なんだね。じゃあ続けるよ」
たまたま半屋を見かけた梧桐は、半屋があまりに伊織に似ていることに驚く。しかし父親に認知されていない半屋は、受領の継子にすぎず、梧桐とは身分が違いすぎる。
梧桐が悩んでいるうちに、半屋は継子であるゆえに破談となり上京し、御幸の元で世話になる。
ところがある日、半屋は御幸の夫である八樹に見つけられ、手込めにされそうになる。世話になった姉に顔向けできない。半屋はあわてて御幸の元を去った。
|
「………」
「どうしたの?」
「てめぇの神経のとんでもなさに呆れてんだよ」
「え、なに? 俺が半屋君を手込めにしようとしたってところ?」
「言うな!」
「あ、もう時間がないや。先、進めるね」
仮の宿に移った半屋を梧桐は見逃さなかった。梧桐は半屋をさらい、宇治の館に移してしまう。梧桐は帝の娘婿なので、いきなり身分の低い女を妾にすることもできず、すべては秘密裏に運ばれた。
一方、半屋を忘れられぬ八樹は、妻の御幸に半屋の素性を聞くがいっこうにわからない。しかしふとしたことから、半屋が梧桐に囲われて宇治にいることを知る。
ライバルである梧桐の囲い者である半屋に八樹の食指は動き、ついには宇治までおしかけて強引に契りを結んでしまう。都会的でまめまめしい八樹に半屋の心は動くが、別の日に梧桐に会えばまた半屋の心は揺れる。そしてまた八樹に会えば心が動く。そんなことを繰り返している間に梧桐に八樹とのことが見つかってしまう。
怒った梧桐は館の回りを厳重に警護させ、半屋が八樹に会えないようにした上で自分の屋敷に引き取ろうとする。一方八樹も半屋を自分の屋敷に引き取ろうとしていた。
追いつめられた半屋はついに自殺してしまう。それを聞いた梧桐と八樹は嘆いた。特に梧桐は伊織の形代にすぎないと思っていた半屋をいつの間にか深く愛していたことに気づき、後悔する。一方、八樹は嘆きのあまり床に伏せてしまう。
ところが半屋は死んでいなかった。ある僧に拾われ、その妹の尼僧の元で養生していた。身元を隠していた半屋だが、その尼僧の亡き娘の婿に見初められてしまう。そして半屋は出家した。その話は都に伝わり、梧桐が半屋を迎えに行くが半屋は出家した身、返事はない。梧桐は半屋は別の男に囲われているのだと思い、去っていった。
<源氏物語・完>
|
「てめぇ………」
「人がせっかく教えてあげてるのに、キーキーうるさいよ、君」
「なにが教えてあげてるのに、だ。こっちがやめろって言ってんのに、べらべらとわけのわかんねぇことほざきやがって」
「我ながらよくできたと思うんだよねー。半屋君、伊織さんにそっくりだし」
「似てねぇよ!」
「もし俺だったら、君が梧桐君とできてたら、それはそれで興味がわくだろうし」
「………。一度死んでこい」
「えー? 君はもし俺が梧桐君とできてても、興味ないわけ?」
「んなもんあるわけねぇだろ!」
「そう? 俺だったら絶対興味あるけど」
「てめぇと一緒にすんな」
「あ、恵比須君だ。じゃあ明日の追試、がんばってね」
言いたいことだけ言って八樹は去っていった。
半屋はしばらくしてようやく、恵比須も同じ学年だということを思い出したが、後の祭りだった。
翌日。古文の問題は八樹の言ったとおり、宇治十帖の要約だった。ストーリーは妙にはっきりと覚えていたが、半屋は一文字たりとも書かず、再追試となった。
それを聞いた八樹が次は何を教えようかと喜んだことは言うまでもない。
というわけで追試ネタです(違うって)。
近頃萌え萌えだった宇治十帖。ちょっと宇治に観光に行きたいぐらいですv なんでもボランティアのガイドさんが案内してくれるとか! ナイス!
実際は八樹も梧桐も御幸を好きになったりするのですが、そこは飛ばして、都合の良いところだけピックアップ(笑) 昔は嫌いだったんだけどな〜。宇治十帖も浮舟も。 |