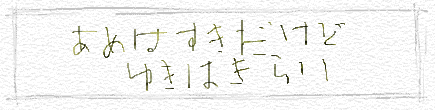雨は好きだけど雪はきらい。
窓の外に雪が降っている。昼前から降り出した雪は、珍しく積もりそうだった。
教室では数学教師がぼそぼそと、だれも聞かない数列の説明をしている。
今はシャーベット状の氷で覆われている校庭も、やがて一面の白に変わるだろう。
一面の雪。
あのバカが喜んで踏みまわりそうだ。
そう思いついて、半屋は顔をしかめた。
昔、学校帰りの公園で、梧桐が雪合戦をしていたことがあった。何十人も巻き込んで全員どろどろで。半屋はそれをちらりと見てそのまま通り過ぎて、家に帰った。
ゆきはきらい。
汚いまま未練たらしく残っていて。梧桐たちが暴れ回った公園には、中途半端な大きさの雪だるまやかまくらがいつまでも残っていた。
(くだんねぇこと思い出したな)
半屋は無意識にポケットを探った。少しつぶれた箱に指を滑らせて、ようやく、今が授業中だと思い出す。半屋は舌打ちをして、また窓の外を眺めた。
雪が激しくなっている。この分だと交通機関にも影響が出るだろう。
雪が嫌いだったのは昔の話だ。いつの間にか全てのことがどうでもよくなっていた。好きも嫌いもない。ただなにもなく日々がすぎてゆく。
昔、あの公園で一人で遊んだことがあった。
夏の激しい雨の日。
普段はごった返している公園には誰もいなかった。
その前の雨の日、傘をささずにぼうっとして家に帰ったら風邪をひいた。雨の日に外で遊んではいけないと親からひどく怒られた。
別に遊んでいたわけではない。半屋は外で遊んだりはしない。
その日は傘をささずに遊具を眺めていた。雨の日に遊んではいけないと言われた。だから、今なら遊んでもいいような気がする。
なんで雨だと傘をささなくてはいけないのだろう。体が濡れるのはプールも同じだ。
プールはよくて他はダメな理由がわからない。
半屋はジャングルジムに昇り始めた。雨に濡れた鉄が変に重くて冷たくて、上を向くと雨粒が目に入ってきて、昇りにくい。
てっぺんまで登って腰を下ろした。
このジャングルジムには普段子供が群がっているが、こんなことの何が面白いのかわからない。
まわりは誰もいない公園。雨は激しく半屋をぬらし、洋服が体にへばりつく。
でも、こういうのはキライじゃない。
半屋はしばらくそこでぼうっとしてからジャングルジムを降りた。
その日も風邪を引いてひどく怒られた。なんで風邪なんてひくんだろう。ただ濡れているだけなのに。
次に雨が降ったときもジャングルジムでぼうっとした。
生ぬるい雨なのに、体の芯まで冷えてくる。とても寒い。それでも半屋はそこを動かなかった。
「そんなに登りたいのか、山ザル」
下の方で怒鳴り声がした。
梧桐とかいう名前のやつだ。半屋の通う小学校の人数が少なくなって、近くの小学校と合併した。梧桐はその小学校に元々いたやつで、なぜか時々半屋にちょっかいをかけてきた。
ちらりと見て、無視した。
雨は重く寒い。でもキライじゃない。
「おい」
突然横で声がした。梧桐だ。半屋は視線を外した瞬間に梧桐の存在を忘れていたから、驚いてバランスを失いかけた。
「ンだよ、てめぇ」
「なんでここにいる。この前もいただろう」
梧桐の額に雨がつたっている。それでも梧桐の表情はまったく普段通りだった。
「るせーよ。関係ねぇだろ」
「さすがサルだな。昇るのが好きなのか」
殴るにもあまりにも場所が悪すぎる。半屋は無視して降りることに決めた。別にここにいたいわけでもない。
半屋が降り終わると、梧桐の方が早く地面についていて、なんだか威張っていた。
「オレの方が早い」
「んだと?」
「風邪っぴきの軟弱ザルより、オレの方が早いと言ったのだ」
「誰が風邪ひいてるっていうんだよ」
「貴様だ」
「ひいてねぇ」
半屋は梧桐に殴りかかった。コイツはキライだ。
ところが殴ろうとした半屋の腕を、梧桐は軽々とつかんだ。そしてそのままずるずると引きずられる。
「てめぇなにすんだ。放せ」
梧桐は楽しそうに、大きな屋敷の前まで半屋を引きずった。たぶんここが梧桐の家なのだろう。
「これで拭け」
結局家の中まで引きずられると、すぐに、梧桐が大きなバスタオルと着替えをもって現れた。
「ア?」
「水は空気に触れると熱を奪う。だから雨に濡れると風邪をひくのだ。プールなどとは違う」
「んだと」
梧桐はうめく半屋を無視して、さっさと着替えて体を拭いた。
そして
「どうしようもないサルだな」
と言って、まだなにもせずにそこに立っていた半屋の頭を拭きだした。
「いらねぇ」
「うるさい」
ほとんど取っ組み合いのケンカのように無理矢理着替えさせられた上に、ひき始めの風邪に効くのだと言う謎の煎じ薬を飲まされて、半屋は梧桐の家から追い出され、そのまま家に帰った。
風邪はひいていなかった。
「また昇るのか、バカザル」
ぬるい雨がしとしとと降る日、半屋が傘を差してぼうっと公園に立っていると、また横で声がした。
「誰が昇るか」
半屋は振り向かず、そのまま家に帰った。用もなく公園に行ってしまったのがなぜかはわからない。ただ横で声がしたとき、驚きはしなかった。きっと梧桐だろうと思った。だから振り向かなかった。
そのことをまた思い出したのは正月もすぎ、二月に入ってのことだった。
大雪で小学校が早く終わった日。この地方ではめずらしく、尽きることなく雪が降り続いていた。
学校帰りに通りかかるあの公園にも雪が降り積もっていた。
「セージ、次なにやる?つぎ」
公園の中から大きな声が聞こえてきた。
降りしきる雪の中、大勢の子供たちが遊んでいる。その中心にいるのは梧桐だった。雪合戦をしているのだろう。子供たちはみんなどろどろだった。
「痛いよセージ」
誰だかわからない子供の、甘えたような声。
半屋はそのまま公園を通りすぎた。
公園には汚くなったかまくらや雪だるまが何日も何日も残り続けた。
(………)
半屋は窓の外を眺めていた。
何かくだらないことを思い出していたような気がする。少し頭が痛い。
窓の外には雪が降り続き、降り始めの雪に灰色だった校庭も、段々白く染まり始めた。
もうすぐ放課後だ。
梧桐はまっさきに飛び出て、校庭で暴れ回るのだろう。
(………バカだからな)
半屋は小さく笑った。
笑えるようになった自分に気づいてはいなかった。
|