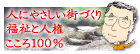 トップページ 新着記事 ホットニュース
トップページ 新着記事 ホットニュース アンケート メルマガ 初めてのかた リンク集 お問合せ サイトマップ
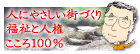 トップページ 新着記事 ホットニュース
トップページ 新着記事 ホットニュース ![]() 議会ウオッチ ひとりごと 掲示板
議会ウオッチ ひとりごと 掲示板
アンケート メルマガ 初めてのかた リンク集 お問合せ サイトマップ
2006年10月16日(月曜日)掲載
![]() 9月定例議会が終わりました。
9月定例議会が終わりました。
![]() 山本隆助役の後任に吉谷幸二技監を選任
山本隆助役の後任に吉谷幸二技監を選任
9月12日にはじまった9月定例市議会は、人事案件1件、契約案件2件、条例案件12件、補正予算案件5件、決算認定案件13件、 その他案件等38件の内、決算認定を除く議案についてすべて原案通り可決し、29日に会期を終えました。
追加議案として提案された助役人事は、9月25日付で病気療養中の山本隆助役から辞任願いが出されたもので、後半議会の28日に市長から提案のあった 吉谷幸二氏を全会一致で選任しました。
吉谷幸二氏は鹿児島県出身で建設省近畿地方整備局から昨年4月に高槻市に技監として赴任。現在、52歳です。
![]() 障害者自立支援法に基づく10月市町村事業実施で市の独自軽減策を追加提案
障害者自立支援法に基づく10月市町村事業実施で市の独自軽減策を追加提案
今議会で最大の争点となったのは、4月から施行された「障害者自立支援法」で、市町村事業とされた事業内容・利用料を定める「地域生活支援事業利用者負担条例」制定と就学前障害児通園施設「療育園」「うの花療育園」等の利用料負担を定める「療育センター条例」改正。
既に提案の1)日帰り・宿泊ショートステイ送迎加算、2)グループホーム市単独加算の継続に加え、3)市町村事業とされた「地域生活支援事業」の利用料負担上限を、日常生活用具給付を除き、国事業の介護給付事業の上限額と一括管理する総合上限制の創設、4)社会参加事業としてガイドヘルプ事業を12時間まで無料化、5)知的・身体障害児通園施設(うの花療育園・療育園)の利用料を国基準の1/2とし、食費実費(650円)徴収は、230円を上限に所得区分により150円、70円に引き下げる、6)グループホーム市単独加算に加え、現行報酬と10月以降報酬の差額の1/2を限度に追加算するとの独自軽減策が追加提案され、可決しました。
市町村事業および市独自軽減分の内容はこちらをご覧下さい。
![]() 「学校図書司書教諭選任化」「障害者自立支援法見直し」等の意見書も全会一致で採択
「学校図書司書教諭選任化」「障害者自立支援法見直し」等の意見書も全会一致で採択
議員提出意見書では、学校図書館の役割をさらに発揮するため国に対し、学校図書館法など関連諸法の改正と財源措置を講ずるよう求めた「学校図書館における専任司書教諭制度確立を求める意見書」、また「障害者自立支援法」の見直しなどを求めた「障害者自立支援法本格実施にあたり、障害福祉サービスの制度推進を求める意見書」を提案し可決しました。
![]() 決算認定は決算審査特別委員会で別途審議
決算認定は決算審査特別委員会で別途審議
2005(H17)年度決算については、10月23日(月)~27日(金)の日程で決算審査特別委員会が開催され、審議されることになります。なお、審査に先立ち、9月定例議会中に正副委員長を決める委員会が開催され、委員長には私・岡本茂が選出されました。
![]() 本会議、福祉企業委員会でも質疑
本会議、福祉企業委員会でも質疑
本会議では「消防・特別救急隊の24時間・365日本格運用」について一般質問。福祉企業委員会では、障害者自立支援法に基づく市町村事業実施について市の姿勢をただしました。
(本会議質問・答弁についてはわかりやすいように、項目毎に順番を変え、編集し直しました。)
「救命救急体制の向上と特別救急隊24時間365日 本格運用へ」
-本会議一般質問・答弁(要旨)-
就学前・障害児通園施設の保護者負担の軽減図れ
―福祉企業委員会「市立療育センター条例一部改正」質疑―
「障害者自立支援法」に関わり、市は安定的なサービス提供確保と現行サービス水準の確保をはかれ
―福祉企業委員会「地域生活支援事業利用者負担条例制定」質疑―
「救命救急体制の向上と特別救急隊24時間365日 本格運用へ」
-本会議一般質問・答弁(要旨)-
【第一問】
岡本茂の質問
2005(H17)年中の本市の救急出場件数は15,279件で前年(14,508件)の5.3%増、搬送傷病者数も14,414人で前年(13,633人)に対し5.7%増。出場件数は一日平均約42件、約34分に1回出場し、搬送人員は一日平均約39人で市民約25人に1人が救急搬送されたことになる。
特に、急病の割合が59.9%と高い割合を占め、そのうち65歳以上の高齢者は49,6%と半数を占めている。
「命を救う救急救命体制」の向上が何より求められるが、平均寿命や乳児死亡率の低さでは世界一のレベルを誇るわが国にあって、心肺停止患者の救命率は欧米諸国に比べてかなり低いと指摘されている。
本市では2000(H12)年の旧厚生省「病院前救護(プレホスピタルケア)体制のあり方に関する検討会報告書」および翌年3月の消防庁「救急業務高度化推進委員会報告書」を受け、三島救命救急センターとの連携協力を得る中で2002(H14)年10月1日から特別救急隊の試行運用がスタートさせた。
そして当初の平日(月~金)A9~P5の運用から、翌2003(H15)年1月から月曜のみ24時間運用に拡大、2004(H16)年10月からは月・水・金の週3回24時間運用となり、本年10月から終日365日、24時間の本格運用が予定されている。
まず、これまでの試行運用実績と今後の救急救命体制に関わって六点聞く。
1.試行運用期間中(昨年末までの過去3年3ヶ月)における特別救急隊出場件数と心肺停止重篤患者数は。その内、心拍再開し1週間生存されたいわゆる救命率と完全社会復帰された社会復帰率は。
消防長の答弁
平成14年10月の特別救急隊試行運用開始から平成17年12月末までの出場件数は809件で、搬送人員が312人。その内、心肺停止重篤患者数(CPA)は、141人。 うち、心拍再開された方は52人、「1週間生存された救命率」は、19人で約13.5%、うち5人が「完全社会復帰」をされ、率にすると約3.5%である。
岡本茂の質問
2.試行運用期間中、運用時間外に発生した心肺停止重篤患者数は。
消防長の答弁
運用時間外に発生した心肺停止重篤患者数は443人であった。
岡本茂の質問
3.通報を受けて現場到着までの平均時間、現場到着から病院到着までの平均時間は。あわせて、今回、補正予算化された通信指令端末のシステム化によって期待される効果はどうか。
消防長の答弁
特別救急隊は、南芥川町の大阪府三島救命救急センター内に設置した救急ステーションから市内各救急現場へ出場するものであり、覚知から現場到着までの平均所要時間は8.6分、出場から病院到着までの平均所要時間は25.7分。
指令端末装置の設置によって、期待される効果についてで、現在は「内線電話・FAX・無線傍受」の3通りで出場指令を行い、更に特別救急隊員からPHS(院内携帯電話)でドクターに連絡して出場。指令端末装置の設置で「音声・地図情報・文字情報」が同時に出力されるため、指令時の簡素化とともに、確実性が増し、更に出場までの時間短縮が見込めると考えている。
岡本茂の質問
4.救急救命士の養成確保について。 救急業務の高度化にとって救急医療機関との連携はもちろん、救急救命士の確保も欠かせない。本市における救急救命士の数と救急隊員に占める割合および今後の養成計画は。
消防長の答弁
現在、毎年4名を府立消防学校や財団法人救急振興財団等の救急救命士養成課程へ派遣し、養成に努めている。
今後、救急救命士の第1期資格者から順次退職年齢等(昇任・昇格)に達するので、今後も毎年4名の養成に努めてまいりたい。
本市救急隊員に占める救急救命士の数と割合であるが、救急隊員数は、消防隊員との兼任を含め185人で、そのうち救急救命士は53人、率にしますと28.6%である。
岡本茂の質問
5.特別救急隊試行運用と10月からの本格運用をふまえ、本市の救急救命のレベルは救命率の比較において全国平均、府平均のどのレベルか。
消防長の答弁
平成16年統計では全国平均5.8%、大阪府平均7.9%、高槻市平均9.7%。当市の救命率のレベルは、全国及び大阪府平均と比較して、高数値を示していると認識している。
【第二問】
岡本茂の質問
次に、救急救命体制強化に関わって、とりわけ、救急隊が現場に到着するまでの救命措置(119番通報を受けてから現場到着までの平均所要時間8.6分)について質問する。
三島救命救急センター所長でもある森田Drは「プレホスピタルケアの重要性」という論文の中で、「救急救命士によるプレホスピタルケアが整備充実されることの意義は大きいが、現場到着までの要する時間に限界がある」「脳障害を残すことなく救命効果が最大限発揮されるためには、居合わせた人によって119番通報の後、心肺蘇生ならびに除細動(AED)実施の一連の救命行為が迅速になされること」「市民が救命の主役になるまちづくりが重要である」と指摘している。
そこで、救命効果向上への取り組みについて、二点尋ねる。
1.市民を対象とした救命講習実施状況と市民による実際の心肺蘇生実施率について。
私も9年前に普通救命講習を受講し終了証をいただいたが、続けて受講しなければ実際にその現場に居合わせたときに実際に心肺蘇生を行えるのかどうかは大きな不安。
まして、AEDがおかれているのは知っていても、それを使ったことのある市民はまだまだ少数ではないか。本市における救命講習受講者数、あわせてAED受講者数と受講者へのフォローについてはどのように実施されているか。また、講習実施によって救急隊現場到着までに市民による心肺蘇生のための救命措置の実施率はどう高まったのか。
消防長の答弁
H6年に応急手当普及啓発活動実施要綱を制定し、傷病者の救命率向上を目指して、積極的に市民に対する応急手当の知識、技術の向上の普及に努めており、本年8月末までに消防本部が実施した救命講習受講者は、延べ2,188回、57,839人の市民が受講。この数字は高槻市民の約16%にあたり、約6人に1人の市民が受講されたことになる。
また、AED(自動体外式除細動器)の講習は、他都市に先がけ、昨年の4月からAEDの取り扱いを含めた救命講習を開始し、本年8月末までの受講者は、延べ378回、8,992人となっている。
受講者へのフォローは2年ごとに再講習の受講を推奨し、9月9日の「救急の日」等のあらゆる機会を通じて、応急手当の普及啓発を積極的に展開している。
市民による心肺蘇生法の実施割合につきましては、平成6年当初11%であったが、平成17年には全国平均の33.6%を上回る37.4%となり、応急手当普及啓発の効果が現れているものと認識している。
岡本茂の質問
2.「救命都市たかつき」に向けたAEDの設置状況について。
1999(H11)年から2003(H15)年までの5年間に救急隊員により搬送された心肺停止重篤患者の発生場所を分類した三島救命救急センター・森田所長の調査によれば、住宅が758症例で全体の78.1%と最も多いものの、不特定多数が利用する施設が11.9%、道路上が6%となっている。
とりわけ、不特定多数が利用する施設では駅構内が最も高く、次いでゴルフ場、老人ホーム、スポーツ施設となっている。
昨年7月以降、市内には、高槻市が各公共施設に設置したもの、あるいは各事業主体によって設置されたものがあるが、設置が急がれる駅構内や大型店舗等も含め市内における現在のAED設置数はいくらか。
消防長の答弁
昨年度の重点施策の一つである「安全・安心のまちづくり」の観点から、市の老人福祉施設・スポーツ施設・公園・文化施設・支所等に22台のAEDが設置。
また、JR高槻駅、阪急高槻市駅の主要駅、アクトアモーレ等の大型店舗には、高槻市医師会及びNPO高槻ライフサポート協会により、AEDが設置されており、更に、各事業所や高槻市医師会会員の診療所を含め約120台のAEDが市内に設置されていると聞いております。
【第三問】
岡本茂の質問
今回の24時間フル本格運用は全国にも誇れるべき取り組みであり、「安全・安心のまちづくり」を掲げる奥本市政にとっても、「救命都市たかつき」を市民のみならず全国発信する絶好の機会ではないか。
しかし、今回の本格運用開始にあたっては、すでに4年前の試行運用時に特別救急隊の発隊式を行っているので、現時点では特に開始式等は検討していないと聞いている。
確かに、医師同乗の特別救急隊そのものは発隊していることは間違いないが、三島救命救急センターというバックアップ施設との連携の下、24時間365日フル運用という質量とも全国でもトップクラスの救急救命システムが10月からこの高槻で本格運用するということでもある。
改めて、開始式等全国にPRする場を是非とも検討いただくよう強く要望しておく。
最後に、市消防本部「救急ステーション」のホームページには、特別救急隊試行運用中の社会復帰事例として「特別救急隊・命の絆」という感動的な話が紹介されている。
自宅で倒れ、特別救急隊によるAEDと心肺蘇生、気官挿入、薬剤投与等で自発呼吸を再開し、三島救命救急センターでの心筋梗塞緊急治療により19日後には無事退院し、完全社会復帰した男性が、翌年、救急ステーションを訪れ、「生きたままで、一周忌を迎えましたよ!」と語りかけていただいたという事例。
日夜、救命率・社会復帰率向上のために取り組んでおられる救急隊のみなさんには心から感謝申し上げ、一般質問を終わる。
―福祉企業委員会「市立療育センター条例一部改正」質疑―
岡本茂の質問
1・厚生労働大臣(国)が定める利用者負担額の根拠は。
7月末にうの花療育園保護者から相談を受けたが、8月当初、国が示していた利用者負担設定の根拠となる平均事業費は25万円。なおかつ、食費負担分として1食当たり650円と単価設定されていた。成人障害者と同じ650円という食費単価の設定が果たして妥当なのかも大いに議論がある。
結果、うの花療育園(知的障害児通園施設)では、一般世帯で月額39,300円、低所得1・2世帯で12,560円という利用者負担であった。
ところが、8月24日の国の厚労省主管課長会議で、知的障害児通園施設平均事業費は14万4千円と変更された。平均事業費25万円であったものが、いつの間にか14万4千円となり、食費単価も650円、230円、70円が補足給付として新しく設定された。
1)平均事業費の算定根拠、食費単価650円について国からどのような説明を受けたのか。
2)平均事業費の変更、食費単価について補足給付についての説明は。
障害福祉課の答弁
7月5日に国の説明に基づき、府の説明があり、各施設にかかる平均事業費と食費単価の説明があった。根拠については特に聞いていない。額は少し高いのではないか、またこの額ではすべての方が保育所に集中するのではないかとの疑問。
そのような高いという多くの意見が国に届き、8月24日の主管課長会議で障害児通園施設の利用者負担は本人ではなく、保護者が行うこと、特に若い世帯の多い学齢前の障害児について一般子育て世帯との均衡から保育所の保育料程度の負担水準にする軽減措置を拡大するとの説明を受けた。
岡本茂の質問
2.うの花療育園保護者一同、療育園保護者会からの要望についての見解は。
8月にうの花療育園保護者一同、療育園保護者会からそれぞれ市長宛、市議会議長宛に要望書が出されている。
内容はいずれも、身体障害・発達障害の子どもたちにとって、療育園は早期療育の重要な場であるとともに、通園保護者が若年層親世帯への経済的負担の影響(今までの3~5倍になる家庭が大半)が重くのしかかること。
また、給食は療育の一環であり、保育所でも主食費は月1,300円、私立幼稚園月額2,000円~3,000円、小学校給食費3,200円~3,400円ということを考えると。成人障害者と同じ14,300円を幼児期の障害児に適用するのは不合理との指摘も要望として出されている。
市はこれら要望についてどのように受け止めているのか。
あわせて、今回の独自軽減追加分について考慮したポイントは。
障害福祉課の答弁
要望については、1)利用料の増加にならないように、2)給食費は市の一部負担を、3)兄弟姉妹が通園する場合の軽減策、4)国への意見書を提出してほしいなどの内容で両施設保護者から8月16日にいただいた。
市としては、就学前児童の給食費1食650円は高すぎるとの考えから材料費230円の設定を考えていた、国が低所得世帯については1食70円まで下げるとの説明を受け、また、本日、市の独自軽減として利用料を半額まで軽減する措置を行った。
岡本茂の質問
25万円という平均事業費の根拠は十分説明されていない。しかし、利用料の半額設定と食費単価について230円を上限に70円まで引き下げする点については市として大変努力していただいたと評価。
岡本茂の質問
3.保育料との均衡を考慮し、第二子減免の実施を。
要望書の中でも、兄弟姉妹のいる家庭について経済的負担を軽減してほしいという項目があげられている。保育所では、D4階層(市民税所得割8万未満)までについては、高い子どもさんの方の保育料の1/2、D5階層以上の方については、低い方の保育料の1/2という制度をとっている。
市の保育料との均衡の観点から、保育二子減免と同じ形をうの花療育園、療育園で検討できないのか。答弁を。
障害福祉課の答弁
障害児通園施設での利用者負担は自立支援法の考え方が基本となっており、保育所の利用負担と比較して、一見、不合理で冷たい面はあるが、法律・制度の違いということでご理解を。
岡本茂の質問
「児童福祉法」から「障害者自立支援法」という新しい法体系に入るということから、法の枠組みが違うことは理解できるが、現実に若い世代の急激な負担増を緩和する観点からぜひ検討すべきだ。
たとえば、2人在籍している低所得1・2の方は、現行2人で2,200円が一挙に1万1,840円。一般世帯の場合は2人で2万1,000円になり、9月から10月の間に約1万円家庭の負担が一挙に増える。これは不合理ではないか。
再度、検討の余地は。
障害福祉課の答弁
この場ですぐ回答はできないが、ご指摘の意見を十分ふまえ国に要望していくとともに、課内でも協議してまいりたい。
(この後、二人目の児童についての利用料1/2減免が実現しました)
4.新制度への周知は
岡本茂の質問
10月から新しい制度がスタートするが、保護者へのこれまでの経過説明ならびに今後の計画周知・理解の取り組みは。
障害福祉課の答弁
これまでにも施設担当者が保護者に制度説明を行い、障害福祉課からも施設に出向き説明。今後とも、施設担当者と連携し、利用契約を交わしていきたい。
岡本茂の質問
聞いているのは手続き面ではない。措置に基づく利用料から自立支援法に基づく利用料に移行するということ、市の独自軽減について、当然、保護者に対し十分に周知する取り組みが求められているのではないか。
障害福祉課の答弁
10月まで10日ほどしかなく、事務的に詰まっているが、早急に施設にも説明を行い、理解をいただくようしていきたい。
「障害者自立支援法」に関わり、市は安定的なサービス提供確保と現行サービス水準の確保をはかれ
―福祉企業委員会「地域生活支援事業利用者負担条例制定」質疑―-
岡本茂の質問
1.安定的なサービス提供体制の確立について
4月以降、自立支援法施行で新報酬単価が設定された。加えて、従来の月割りから日割りに変更された。これにより、知的通所、身体通所、知的入所各施設の本年4月と昨年4月との比較で減収はどの程度なのか。率も含めて、明らかに。
障害福祉課の答弁
知的障害者通所施設は市内7箇所あるが、昨年4月と比較して1,000万円の減額、率で約20%(19.91%)の減。
身体障害者通所施設は市内2箇所あり、昨年より100万円の減。率にして、14.6%の減。
知的入所施設は市内に2箇所で昨年に比べ130万円の減額。率にして9.3%の減。日払い方式への変更により大きく減額している。
岡本茂の質問
2.新施設体系への移行について
5年以内にそれぞれの施設が新しい自立支援法に基づく新体系への移行を迫られる。
市内にある知的障害者通所施設(定員50人)が、自立訓練(20人)と就労継続施設(B型・30人)という最も多いケースと思われる多機能型に移行した場合、現在の施設収入と新体系移行の施設収入はどのようになるのか。
障害福祉課の答弁
月に約85万円の減額隣、率にして約12%の減になると予測。
岡本茂の質問
4月以降、月割りから日割りに変更したことによって、知的通所では約20%の減収。これに加えて、新体系に移行した場合は、さらに12%減収になる。
これで本当に市内の障害者施設が今後運営していけるのか。通所施設利用者については、4月から利用料1割負担が発生し 食費実費分負担も新たに発生した。
市内のほとんどの障害者施設は認可・無認可含め、障害当事者の親が中心になり作業所を立ち上げ、親の負担の上に運営が成り立っている。
こういう厳しい中、施設減収分を利用者に背負わせる結果となることについて市の見解は。
障害福祉課の答弁
施設を運営している事業者からも、4月から大幅な減収となり、安定した施設運営ができないとの声を多くいただいている。
指摘の点については、サービス水準を後退させることなく、必要な人に必要なサービスが行き渡るよう、利用者、サービス提供事業者含め配慮いただくよう、引き続き国に要望してまいりたい。
岡本茂の質問
経営努力だけで解決する問題ではない。仕組みそのものを変えていかなければならないという事を課題として提起しておく。
岡本茂の質問
3.現行サービス水準の確保について
1)ガイドヘルプ対象事業の変更について
今回、ガイドヘルプ事業について12時間無料との独自軽減が追加された。
これまで、国は通院時のヘルプについてガイドヘルプを認めていたが、継続した通院治療については国本体の自立支援・介護給付事業、いわゆるホームヘルプ事業とした。
18年4月ガイド利用者496人中、これまでのガイド利用から通院時ホームヘルプ利用に変更せざるを得なくなる対象者数は。
障害福祉課の答弁
利用者496名中、通院医療での利用者は154名。通院に関しては、今までどおり時間制限することなく支給決定を行い、現行サービス量は維持。
岡本茂の質問
市町村事業としてのガイドヘルプ上限額は0円、2,000円、4,000円の設定。これが国の自立支援・介護給付事業となると上限額が低所得1 15,000円、低所得2 24,600円、一般課税所帯 37,200円の上限額まであがってしまう。
これは新たな課題として指摘しておきたい。
岡本茂の質問
2)日帰り(日中)ショートステイ存続について
これについても、学齢期の障害児を持つ保護者から「国の新体系移行で、日帰りショートがなくなる」と非常な危機感を持って要望が寄せられている。昨年度実績で、ショートステイ利用者のうち、日帰り利用者は何名か。
障害福祉課の答弁
児童を含む利用者数は451人。そのうち、日帰りショート利用者は360名で約8割の方が利用。障害者を抱える家族にとって重要な事業と認識し、市町村事業として継続実施したい。
岡本茂の質問
日帰りショートについては、非常にニーズの高い事業だけに、現行サービスを後退させない観点から今回、市が市町村事業の任意事業として位置づけたことは高く評価。
岡本茂の質問
4.障害者自立支援法の10月本格実施に向けた体制について
1)障害区分認定変更率は
区分認定について、対象者約900人中、9/8現在で認定終了は343人で約1/3との答弁があった。
国が、試行自治体6月末6,845件の2次判定変更率を集約した調査では、33.2%が1次判定から2次判定で上昇。特に知的・精神は大きく上昇しているのが傾向として示されている。
高槻市での、障害程度区分(身体・精神・知的)、二次判定区分変更率は。
障害福祉課の答弁
知的(199人)については95件が上位変更、47.7%。
身体・知的重複(79人)では21件が上位変更で26.6%、精神(24人)では16件が上位変更で66.7%、
全体(343人)では、区分変更件数は136件で39.7%。
当初予想通り、知的・精神については内面の問題もあり、医師の意見書により変更が多い結果。国が示した事例の約1/3よりは高い数字となっている。
岡本茂の質問
2)制度施策変更についての周知は
「自立支援法パンフレット」について約2000部作成したということだが、団体や各施設に配布する中5月か6月にはもう品切れになってしまった。
ただでさえ、わかりにくい制度だけに、自分の受けるサービスがどうなるのか、利用料がどうなるのかを含め、10月からの移行含め周知をどう図っていくのか。
障害福祉課の答弁
制度変更については、障害者団体等を通じて説明、お願いなりをしてきたところだが、今後、市広報、ホームページ等を通じて知らせていきたい。パンフレットについては、今後内容も含め検討していきたい、
岡本茂の質問
3)市障害福祉課の窓口相談体制について
障害福祉課の窓口対応の問題だが、いつも10人、20人の方が列を成して並んでいる。多いときは番号札を出していると聞く。カウンターのところは1列で座れるのは5人前後だと思うが、隣同士のプライバシーも守れない。
4月の制度移行以前からそういう状態が続いている。相談にこられた障害者がきちっと相談してもらえたと帰っていただく体制にすべきではないか。
障害福祉課の答弁
精神障害者福祉もH14年度から始まり、毎年のように制度変更がある中で毎年増えている。
車椅子の方もこられ、通路が狭い問題もあり、待つところがないということも聞いている。手帳についても種類があり隠したいという気持ちの方も折られ、プライバシーの問題と自覚している。
関係課と課の配置について相談しているが、なにぶん、庁舎スペースの関係上、その調整をまっている。
岡本茂の表明
5.地域生活支援事業利用者負担条例についての意見表明
障害者自立支援法については、4月以降の見直しに次ぐ見直しに加え、サービス支給の基礎になる区分認定調査が10月実施に間に合わないことも審議に中で明らかになった。
同時に、利用者負担について言えば、本体である国の自立支援給付の介護・訓練等給付、自立支援医療等の利用負担(定率1割、上限37,200円)が大きな問題。
ただ、今回、当初の市独自軽減案に加えて新たな追加軽減案が本委員会に提示されたことについては、障害者団体や障害当事者の粘り強い運動とその声に一歩でも近づくものとして、高く評価したい。
1)「法」の抜本的見直しを含む国への制度改善を改めて強めること。
2)今日の審議の中でも出されたなお残された課題について、引き続き障害当事者の声を真摯に受け止め課題解決にむけ市としての検討と財政的努力を行う旨の二点を附帯意見として要望し、本条例については賛成する。

|
「障害者自立支援法」本格実施にあたり、 提案者 岡本茂 本年4月から「障害者自立支援法」が施行され、この10月からは市町村事業とされた地域生活支援事業等が本格実施される。 記 1.安定的なサービス提供確立のためグループホーム・ケアホーム、ショートステイ、施設利用等の報酬基準や単価を実態に合わせて見直しを行うこと。 平成18年9月28日 高槻市議会 |
「障害者自立支援法」に基づく市町村事業・市独自軽減の内容
| 事業(サービス)名 | 主な事業内容 | 利用者負担額 | 負担上限月額 |
| 相 談 支 援 | ・相談 無 料 ・情報の提供 ・助言 ・専門機関の紹介 |
無 料 |  |
| コミュニケーション支援 (手話通訳派遣) |
・手話通訳の派遣 | 無 料 |  |
| 日常生活用具給付 | ・日常生活用具の給付 <ストマを補装具から 日常生活用具とする 見直しなどあり> |
市長が定める基準額を超えない範囲内で、用具の給付に要する費用の額の100分の10に相当する額 | <負担上限月額> 生活保護 0円 市民税非課税 12,000円 市民税課税 24,000円 |
| 移 動 支 援 (ガイドヘルプ) |
支援に通常要する費用として市長が定める額の100分の10に相当する額 | <負担上限月額> 生活保護 0円 市民税非課税 2,000円 市民税課税 4,000円 |
|
| 地域活動支援センター | 創作活動や生産活動の機会の提供等に加え、 Ⅰ型 地域の連携強化、ボランティア育成等 (高槻地域生活支援センター) Ⅱ型 機能・社会適応訓練、入浴サービス等 (障害者福祉センター等) Ⅲ型 地域の障害者の援護 (小規模通所施設等) |
センターが実施する事業に通常要する費用として市長が定める額の100分の10に相当する額 | |
| 日中一時支援 (日帰りショートステイ) |
・ショートステイ(宿泊は除く) | 事業に通常要する費用として市長が定める額の100分の10に相当する額 | |
| その他の事業 | ・訪問入浴 | 事業に通常要する費用として市長が定める額の100分の10に相当する額 |