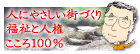 �g�b�v�y�[�W�@�@�V���L���@�@�z�b�g�j���[�X�@�@
�g�b�v�y�[�W�@�@�V���L���@�@�z�b�g�j���[�X�@�@�A���P�[�g�@ �����}�K�@�@���߂Ă̂����@�@�����N�W�@�@���⍇���@�@�T�C�g�}�b�v �@�@
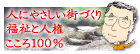 �g�b�v�y�[�W�@�@�V���L���@�@�z�b�g�j���[�X�@�@
�g�b�v�y�[�W�@�@�V���L���@�@�z�b�g�j���[�X�@�@![]() �c��E�I�b�`�@�@�ЂƂ育���@�@�f����
�c��E�I�b�`�@�@�ЂƂ育���@�@�f����
�A���P�[�g�@ �����}�K�@�@���߂Ă̂����@�@�����N�W�@�@���⍇���@�@�T�C�g�}�b�v
�@�@
2006�N1��1���i���j���j�f��
![]() �@12�����c��I���܂����I
�@12�����c��I���܂����I
12��1���ɂ͂��܂���12�����c��͓�����20����\�������������A26���ɕ�B�u�j�������Q�����i���v����A����ՃZ���^�[��ᣑS�����������Č�6���A������{�݂̎w��Ǘ��ң�w��43���A�Œ莑�Y���]���R���ψ��I�C���ӁA��\�Z���������܂����B
�@
�@�@�u�j�������Q�����i���v�͈ꕔ�ψ���C���̏�A�S���v�ʼn�
�œ_�̢�j�������Q�搄�i��ᣂ́A��3���[��{���O�́u�D�P��o�Y�Ɋւ������̈ӎv���j���̈ӎv�������ɑ��d�����v(����)���u�����̈ӎv���j���̈ӎv�������ɑ��d�����v�Ɉꕔ�C�����A�c��̌��Ă��܂ߑS���v�ʼn����܂����B
�@
�@�u�����{�݂̎w��Ǘ��ҁv���Ԍ���7�c�̂͂��ߊǗ��҂��w��
����܂Ŏs�̊O�s�c�̂ɊǗ��^�c���ς˂��Ă��������{�݂ւ̖��ԎQ���ƂȂ颎w��Ǘ��Ґ��x������ɂ��āA���Ԍ���10�{�݂͂��߁A���s�ϑ��c�̂���肵�Ďw��Ǘ��҂Ƃ���33�{�݂̌v43�{�݂̎w��Ǘ��҂̎w����c�����܂����B
�����Ő��s���v�[����V�l�����Z���^�[�w��Ǘ��Ҍ��Ɋւ���s�z2��2,500���~�ɑ��A1��4,466���~�̒�Ċz�Ŗ{���ɏ\���ȊǗ��^�c�Ǝs���T�[�r�X���オ�s����̂��v���A�s���T�[�r�X�̌����w��Ǘ��ґI��o�߂̌�������������ɂ��đ����̎��₪�o����܂����B
�Ǘ��^�c�o��R�X�g�ʂ����łȂ��A�s���T�[�r�X�̊ϓ_��������ꂩ������{�݂��ǂ��ς��̂���������܂��B
�@
�@���ڐ����́u���Ύs���h������a�s�s���v����͎^�������Ŕی�
���ڐ����͢���h���n��錾�^���S���l�b�g���[�N�v�̉^�����āA�s���L����������12,518�Ɋ�Â�12��9���ɏ�ᐿ�����s���A����������s���ĐR�c���s���܂����B
�ψ���R�c�ł́u���h���n���錾�����̂ɒn�������̂��Ȃ肦��̂��v�u�W���l�[�u��������h���n����������i���ׂĂ̐퓬���E�ړ�����E�R�p�{�݂̓P���A�Z���ɂ��G�s�����s���Ȃ��A�R���s�����x�����銈�����s���Ȃ����j��n�������̂����E�h�q���ɑ���s�g�ł�����̂��v���A��ᐧ��̎������̋^�₪�o����A�ψ���A�{��c�Ƃ��^�������Ŕی�����܂����B
�@
�@�����s���ψ���Ţ�j�������Q�搄�i��ᣁA�u�w���ۈ玺�̏�Q�����������̓P�p�v������
�ψ����E���قɂ��Ă͂킩��₷���悤�ɁA���ږ��ɏ��Ԃ�ς��A�ҏW�������܂����B
�j�������Q�搄�i���ɂ���
�P�D�u��ᣐ���̈Ӌ`��
���{�̎���
�u�j�������Q����͎Љ�I������I�Ȓj���̐�����G����ے肷����̂ŁA�s�����s���̌l�����ɉ�����ׂ��łȂ��v���邢�́A�u���@19���i�v�z����їǐS�̎��R�͂����N���Ă͂Ȃ�Ȃ��j�A21���i�W��A���Ћy�ь��_�A�o�ł��̑���̕\���̎��R�́A�����ۏႷ��j�Ɉᔽ����v�Ƃ̈ӌ����ꕔ�ɂ���B
�����ɢ���S�E�ǐS�̎��R��Ƃ����ǂ��A�l���d���A���ɐ�����n��Љ�������Ă������Ƃ́A�Œ�����߂���ׂ��Љ�K�́B
���߂ď�ᐧ��̕K�v���ɂ��Ďs�̌��������߂�B
�s���������̓���
�܂��܂��j���Ԃ̊i��������A�^�̒j���������������邽�߂ɒj�������Q���{�@����̌o�߂��ӂ܂��A�{�s�̒j�������Q��������߂��������߂��Ă���B
���͐�����ے肷��̂��ł͂Ȃ��A�j�������Q��Љ�`����j�Q����悤�ȌŒ�I�������S�ɂ��Ă͐������Ă��������ƍl���Ă���B���{�̕��������ꂩ�畢�����̂ł͂Ȃ��B
���{�̎���
��ᐧ�荪���Łu���{�̕��������ꂩ�畢�����̂łȂ��v�Ƃ̓��ق����������A���́u���{�̕������ׂĂ��p���ł����v�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B�v���X�ʂ͐ϋɓI�Ɋ������������A���̕����͍������Ă����w�͂��K�v�Ǝw�E���Ă����B
�Q�D��ᐧ��Ɏs���ӌ��͂ǂ����f���ꂽ�̂�
���{�̎���
1�N���ɋy�ԐR�c���o�ď�ᐧ��Ɏ������B�]���͐R�c��\�f�Ă����ɁA�s�����p�u���b�N�R�����g�����{���s���č���Ƃ������@�B����͐R�c��p�u���b�N�R�����g�����{�A�������R�c��g�����̐R�c���ւē��\���܂Ƃ߂��_���������B���̈Ӗ��ŏd�݂̂��铚�\�B
�����ŎO�_���₷��B
�P�j�p�u���b�N�R�����g�i�{�N3��17���`4��28���j�̈ӌ������́B
�Q�j�s���ӌ������\�Ăɂǂ̂悤�ɔ��f���ꂽ�̂��A�u�C���̗p�v�u�L�ڍς݁v�u��|���f�v�̌����́B�@
�R�j�{��c���^�ł��u�����Ă��ꂽ���Ă͓��\�ĂƔ�r���đ傫����ނ��Ă���̂��͂Ȃ����v�Ƃ̌��O���o���ꂽ�B���̓_�ɂ��Ĥ���߂����\���ĕ��ƍs����ď������Ƃ̐������́B
�s���������̓���
�P�j�ӌ�����288���B�����������Ō��������܂߂��300�������B�d���������������Ƃ��Ă�106���B
�Q�j106�����A�u�C���̗p�v10���A�u�L�ڍς݁v14���A�u��|�͐�������Ă���v14���Ōv38���B
�R�j�傫��5�_�B�@���ۏ��@���ɏƂ炵�ē��e�̐��m���A�A��{���O���f���鑼�����@�̕\����̃o�����X��B�킩��₷���\���ɓw�ߤ���Ղȕ��͂ɂ����A�C��3���̗��O�����ŏd�v�Ȃ��̂ɂ��đ�4���ŋ�̓I�ɐG�ꂽ��D�o���邾���V���v���ɕs���Ȃ����łȂ����̂ɂ��Ă͍폜�����B
�R�D���Ă͓��\�Ă����ނ��Ă͂��Ȃ���
���{�̎���
���\�ĕ�����̕ύX�ɂ��āu�o���邾���V���v���Ɂv�u�s���łȂ����̂ɂ��Ă͍폜�����v�Ƃ̂��Ƃ����A4�_���������������������B
�P�j���\�ĕ��i�O���j�u�j�������Q��Љ�������s�̍ŏd�v�ۑ�̂ЂƂƈʒu�Â��A�֘A������g�𑍍݂��I���v��I�ɐ��i���Ă������߂ɐ��肷��v�Ƃ���B
�����u�ŏd�v�ۑ�̈�Ƃ��Ĉʒu�Â��v�ͤ�p�u���b�N�R�����g�Ɋ�Â��R�c��\�ĂɐV���ɕ⋭���ꂽ�i�C���̗p�j���e�����A�s���ĕ��ł͌�������Ȃ��B�����́B
�Q�j��3���i��{���O�j�́u�D�P�E�o�Y�Ɋւ��鏗���̎��Ȍ��茠�v�u�����̔��f���d�v�ɂ��āA�J�C�����A�l���J����c�⍑�́u�j�������Q��v��v�ł��A���v���E�v���_�N�e�B�u�E�w���X���C�c�i���Ɛ��B�ɂ��錠���j�Ƃ��Ė��L����Ă���B
�s�ͤ�u�D�P�E�o�Y�ɂ��鏗���̔��f�v���ǂ̂悤�ɍl���Ă�����̂��B�������B
�R�j��3���i��{���O�j2���Ť���\�ĕ��ł��u���ɒj���̎Q���ۏႷ�鐧�x�A���̐�����}��v�Ƃ��邪��s�����Ăɂ͂Ȃ��B�s�̌����́B
�S�j��6���i�s�̐Ӗ��j�Ť���\���Ắu�s�͑����I��v��I�Ɏ{������{����v�Ɠ������u���玖�Ǝ҂Ƃ��Ă̐Ӗ����ʂ����v�Ƃ��邪�A�s���Ăł͊܂܂�Ă��Ȃ��������́B
�s���������̓���
�P�j�u�ŏd�v�ۑ�v�ɂ��Ă����A��������Ƃ����ӎv�\�����̂��̂��A������d�v�ۑ�Ƃ��Ĉʒu�t���Ă��邱�Ƃ̕\���Ɨ����������������B���̗��O���i3���j�ł����ɂ������Ă��Ȃ��B�܂��A�u�����I���v��I�ɐ��i���Ă����v���͓��R�̂��Ƃł��褊����ďȗ������B
�Q�j�s���āu�����̈ӎv���j���̈ӎv�Ɠ����ɑ��d�v�̓J�b�v���E�j�����D�P�E�o�Y�Ɋ����铯��̌�����L���Ă���Ƃ̓��e�Ղɐ��m�ɂ���킵���\���B
�R�j�u���ɒj�����v�̕\���ɂ��ẮA���Ԉ�ʂɂ͒j���ɋ��߂��Ă���̂����|�I������������F���ł��Ȃ��B�u���x�E��������v�Ƃ̕\���ɂ��̈Ӑ}�͐�������Ă����B
�S�j������琬�x���s���v��ɂ����Ă�301�l�ȏ�̎��Ǝ҂Ƃ��Ďs���v�������`��������A�Ӗ�������������͂Ȃ��B���Ǝ҂Ƃ��ē��R�̎��Ƃ��č폜�����B
���{�̎���
�P�j1�_�ڂɂ��ẮA�����肻�̂��̂��u�ŏd�v�ۑ�Ƃ��Ă̔F���v�Ɗm�F�B
�Q�j2�_�ڂ́u�D�P�E�o�Y�v�ɂ��ẮA�u���Ղɂ킩��₷���\���Ɂv�ƌ������قł��������A���̓_�ɂ��Ă͋^�₪����ۗ�����B
�R�j3�_�ڂ́u�j���̎Q�搧�x�v������j���̈玙�x�Ƃ̍��Ύs�̎擾�̓[���B���̎��Ԃ����̎Љ�f���Ă���B���搂�͂��ׂ��s�����ł����������B�{�ͤ�p�p�N�I�[�^�[���x����A���e�̔������玙�x�Ƃ��擾���鐧�x�������s���Ă���B
�ۑ�ƂȂ��Ă���̂͒j���̈玙�x�ƁE���x�ƁB�j�����Ǝ��E�玙�E���ɎQ�悷�鐧�x������d�_�ۑ�Ƃ��Ď��g�ނ悤�����v�]���Ă����B
�S�j4�_�ڂ́u�s�̍�����̑[�u�v�́A��K�v�Ȑ��i�̐���Ɋ܂܂�Ă���Ƃ̂��ƁB
�����̐Ӗ���ɂ��ẮA�s�����Ǝ҂Ƃ��ĐӔC��Ƃ����̂łȂ��Ƃ̂��Ƃł��������A�������琬�x���s���v�棂ł͍��Ύs��301�l�ȏ�̈�ʎ��Ǝ҂Ƃ͕ʂɓ��ʎ��Ǝ҂Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă���B��ʎ��Ǝ҂Ɠ���ł͂Ȃ��B���莖�Ǝ҂Ƃ��ė��搂�͂̎s�̖���������B���̓_���v�]���Ă����B
�S.�����ψ��̍\����@�\�������
���{�̎���
���ɁA��18���i���\���o�j�ɂ��āA�R�c��\�ł́u�s�����{����j�������Q��{��A�@�@�@�܂��́A���̌`���ɉe�����y�ڂ��ƍl������{��ɂ��ċ���ӌ����s���ɐ\���o�鎖���o����v�A2���Ţ�s���͎s����Ɨ������@��(��O�ҋ@��)��݂��A���Y�@�ւ̈ӌ����A�v���A�K�ɏ�����A�����Ģ��O�ҋ@�ւ͎s���ɑ������܂��͊������邱�Ƃ��o���飂Ƌ����ψ���̋@�\������܂ŏ�����Ă���B
�������A���ĕ��ɂ͋����ψ���̋@�\������܂ł͋L�ڂ���Ă��Ȃ��B
�����ł��q�˂���B
�Ɨ�����S�ۂ��邽�߂ɋ����ψ��̍\���A�E���A�����A�@�\���ǂ̂悤�ɍl���Ă���̂��B
�s���������̓���
�ڍׂ͋K���Œ�߂�\�肾���A�\����(�ٌ�m�A�w�ғ����ʔ��ΐE)3���ȓ��B�������������ɂ߂Ȃ���l�������l���Ă��������B
�E���ɂ��ẮA���\���o�ɂ�苁�߂���ӌ��ɑ����s���ɋ�\�B���R�A�K�v�Ȓ����A�\���o�҂�E���ւ̃q�A�����O�A�W���ރ`�F�b�N���z�肳���B
���{�̎���
�ʓr�A�\����@�\������ɂ��ċK���Œ�߂�ɂ��Ă��A����Ď��ɋ����ψ��̍\����@�\������A�葱�����߂��K�����o���ׂ��B
�K���ɂ��Ă͂����߂ǂɂ܂Ƃ߂���̂��B�R�c��܂��͋c��ψ���ɋ��c��Ɏ����ׂ����ƍl���邪�ǂ����B
�s���������̓���
�x���Ƃ�1�����ɂ͋K�����܂Ƃ߂����B�c��A�R�c��Ɏ������ɂ��Ă͊�{�I�ɗ�������B������ׂ��Ή��������B
�T�D�j�������Q�搄�i�ւ̍���̎��g�݂�
���{�̎���
�Ō�ɓ�_�B
�P�j.��ᐧ���̎{�����f�ɂ��āA����13���ɢ�j�������Q��v��̍��蓙��Ƃ��邪�A���s��j�������Q��v�������2003�N�`1012�N��10�J�N�v��ł���A��Ƀv�����������āA��A��Ⴊ�o����Ƃ����W�B
�u�v�����v�Ƃ̐������Ɋւ��A���Ԍ������̎����ɏ���|���ǂ����f�����Ă������ۑ������A�l�����́B
�Q�j�{��c�łࢃ��v���E�v���_�N�e�B�u�E�w���X���C�c����̖�肪�A�s���I�ɏ\���F������Ă��邩�̋c�_���������B
����̒j�������Q��������i�K�̒j�������Q��Љ�̐��������������B�����ɐ��i��ţ�Ƃ�������]�݂������A�c�O�Ȃ��獡���̎��Ԃf���Ă���B
�uDV�@�v�ɂ��Ă݂��A�����Ă͢�v�w���܂͌������ʣ�ƌ����A�����s�����������O�̂��Ƃ�����ꂽ�Љ�i�����������A�����ł́u�j���̏����ɑ���ƒ���\�͂͐l���N�Q�v�ƋK�������Ɏ������B
�l���̐����͂ǂ�ǂ�オ���Ă����B����A�Љ�̐i�W�̒��ŋt�ɂ��̏������������Љ�����B���A�c����s����s�����܂߁A�����Ă����������߂���B
�����Ҋ܂߁A����̐����j�������Q��Љ�����ւ̃X�^�[�g���C���ɂ��Ă������ӂ́B
�s���������̓���
�P�j��v������Ɋ�Â��{��ɂ��ẮA�R�c���уp�u���b�N�R�����g�ł��l�X�Ȉӌ������������Ă���B����19�N�x���������Č��s��v��������Ԍ������ƂȂ�̂ŁA18�N�x�����납��19�N�x�O���ɂ����Č�������Ƃ��s�������B
�����̓���
�Q�j�w�E�̓_�܂߁A����A�{���W�J�Ƃ��킹�ω������ɂ߂Ȃ���A�^���ɑΉ����Ă��������B
�@
�w���ۈ玺�ւ̏�Q����������������P�p���ׂ��I
�P�A�w���ۈ玺�̑ҋ@�ɂ���
���{�̎���
�P�j�{�N�x�w���ۈ玺�������l���́B
�Q�j���݂̊w���ۈ玺�ҋ@�������Ƃ��̓���Q���̑ҋ@�l�����B
�Љ�畔�̓���
�P�j�{�N11�������݂œ�����������42���v1,933�l�B
�Q�j�ҋ@��������46�l�A���A��Q����6�l�B
�Q�D��Q�����������̍�����₤
���{�̎���
�P�j��Q���̑ҋ@����6���Ɋւ���āA1�ۈ玺���45��(�Վ����60��)���A��w�����玺�������Q�������l����4���ȓ��Ɛ������Ă���ƕ��������������B
�Q�j�����Ƃ���A���������ɐ������Ă���̂��B��Ⴉ�A�K�����A�v�j�Ȃ̂��B
�Љ�畔�̓���
��Q������l���������͢���Ύs�w���ۈ�ɂ������Q���ۈ���{�v�j��Ɋ�Â�������A1�ۈ玺4���̘g��݂��Ă���B
�R�D�����������߂��u�v�j�v�͍��ʗv�j�ł͂Ȃ���
���{�̎���
���{�v�j��4���ƒ�߂Ă���Ƃ̎��������̍����́B
�Љ�畔�̓���
�w���ۈ玖�Ƃ́A���e�̏A�J�ɂ�闯��ƒ�x���A�ی�҂̓K�ȊČ�����Ȃ���w�N�����̌��S�琬��ړI�Ƃ��ĊJ�n�������Ƃł���A���̖ړI�͈͓̔��Ńm�[�}���C�[�[�V�����̍l�����Ɋ�Â��S����85���̏�Q���̐ϋɓI������s���Ă���B
����ɂ��Ă͌��펙�Ə�Q�����Ƃ��ɐ������Ă������߂ɂ́A����ɂӂ��킵�����A�W�c�̋K�͂ɔz������K�v������A�K�ȕۈ�����ێ�����ϓ_�������g��݂��Ă���B
���{�̎���
�t�ɐq�˂邪�A��Q�����������鎖�ŗǍD�œK�ȕۈ���Ɏx����������Ƃ������Ƃ��B
�Љ�畔�̓���
���펙�ƂƂ��ɐ������Ă������߂ɁA������ӂ��킵���ۈ�����K�v�B����ȊO�ɁA�����I�ȃL���p�V�e�B�̖��������A���g��݂�����Ȃ��B
�S�D�����������߂��u�v�j�v�P�p�̈ӎv��
���{�̎���
�W�c����������Ə�Q���̎Q�������ۂ������N�ۏ��ǂ̃A�h�x���`���[�E�I�[�N�̔��ȁE�������ǂ��ӂ܂��Ă���̂��B�s���ς́A�{��c�Ől���N�Q�ƎӍ߂����͂��B�A�h�x���`���[�E�I�[�N�̔��Ȃ܂��Ă��Ȃ��A���̐��������͕K�v�ƍl���Ă�����̂��B
.�v�j���̂��̂����ʏ����ł͂Ȃ��̂��B
�@
(�����ŐR�c�����f��)�@
�ψ�������u���ʏ����Ƃ̎w�E�����邪�A�����̈ӎv�ɂ��Ă̓��ق��I�v�̎w�E
�@
�Љ�ϕ��̓���
���a54�N�̊w���ۈ玺��ᐧ��ȗ��A��Q���̎�ʥ���x���킸�A���ɗ{��w�Z�����16���������������Ă���B����߂Đ�i�I�ȏ�Q���̎��g�݁H������Ă����B�m�[�}���C�[�[�V�����̎����Ɏ��g��ł����B
�l�I�A�{�ݓI�Ȗʂł̉ۑ�Ƃ��Ĉ��̐�������������Ȃ��B���������ǂ̕ۈ珊�ł��c�B
�@
(�u����ł͓��قɂȂ�Ȃ��v�̐����o�āA�܂��܂��x�e�ɁB
�Љ�畔���A�����A���N�ے��̂R�l�����ْ����̂��߂̋��c�B��A�ψ���ĊJ)
�@
�Љ�畔���̓���
4���g�̖�肾���A���ԂƂ��Č��������̂����邪�A�l���g�ɂ��Ă͍ēx�A�v�j�������������Ԃɍ��킹���`�œ������������Ă��������B
�T�D�ēx�A�s���ςƂ��Ă̌��ӂ�
���{�̎���
�c�t���ł���Q���̓����g��݂��Ă���̂��B
�s���ϊǗ����̓���
�c�t���ł́A���ɏ�Q�g�݂͐��Ă��Ȃ��B
���{�̎���
�����s���ςłȂ��Ή����قȂ�̂��B����̌����Ɍ����ċ��璷�̌��ӂ����������B
���璷�̓���
��w�E�����������_�A����\���Ɍ������Ă��������B
�@