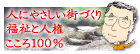 トップページ 新着記事
トップページ 新着記事 アンケート メルマガ 初めてのかた リンク集 お問合せ サイトマップ
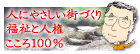 トップページ 新着記事
トップページ 新着記事 ![]() ホットニュース 議会ウオッチ ひとりごと 掲示板 会議室
ホットニュース 議会ウオッチ ひとりごと 掲示板 会議室
アンケート メルマガ 初めてのかた リンク集 お問合せ サイトマップ
2003年4月18日(金)掲載
![]() プロローグ(1994年)
子ども・女性・高齢者・障害者の人権ネットワークを設立!
プロローグ(1994年)
子ども・女性・高齢者・障害者の人権ネットワークを設立!
1994年6月、永年勤務した高槻市役所を退職し、「人権ネットワーク」を結成して代表に。「体験ウオーク」や結成記念シンポジウム等を開催。1995年4月、市議会議員選挙に立候補。新人ながら11位(3,165票)の高位で初当選。
![]() 1995年
初当選そして本会議初質問 「子育てにやさしいまち・子ども 総合ビジョン策定」を市に迫る
1995年
初当選そして本会議初質問 「子育てにやさしいまち・子ども 総合ビジョン策定」を市に迫る
緊張の中の本会議場での初質問。子育てにやさしい街、子育て支援を鋭く市にぶつけました。 また、介護の社会化にむけ、シンポジウム「地域ケアのネットワークづくり」や福祉施設見学会も開催。
![]() 1996年
まちづくりにこそ女性の視点を! 女性政策審議会の設置、女性市民グループへの研究助成を提案
1996年
まちづくりにこそ女性の視点を! 女性政策審議会の設置、女性市民グループへの研究助成を提案
総合市民交流センター(女性センター)開設にあたり、女性の声をまちづくりに積極的に生かせと提案。 男女共同参画研究助成事業もスタートしました。 また、子ども権利条約のワークショップも開催。議会で、スクールカウンセラー配置や不登校児への対策、教育改革の重要性を訴えました。
![]() 1997年
人にやさしいまちづくり 歩道整備、段差解消、JR駅のバリアフリー化の遅れを鋭く指摘
1997年
人にやさしいまちづくり 歩道整備、段差解消、JR駅のバリアフリー化の遅れを鋭く指摘
阪急高架・交通体系特別委員として、阪急富田駅周辺の高架化とともに、交通バリアフリーを提起。歩道整備・段差解消について、大幅な予算確保を確約させました。 98年6月、JR摂津富田駅に車いす対応型エスかレターが設置。JR高槻駅プラットホームへのエスカレーター・エレベーター設置も来年3月には完成見通しとなりました。 又、この年、東城山町内で発見された地下壕が戦時中の地下軍事工場であるとGHQ資料を下に提示し、タチソ等市内トンネネル群の全容調査を市に求めました。
![]() 1998年
議員自ら情報公開を! 岡本茂のホームページを開設
1998年
議員自ら情報公開を! 岡本茂のホームページを開設
子育て支援について本会議で二度目の質問。公立幼稚園4才児クラスでの大量の抽選漏れなど幼稚園教育振興計画策定を要求。ようやく、少子化プロジェクトが発足し、99年から子育て支援センターが富田・春日保育所でもオープン。シングルマザーの児童扶養手当差別条項も撤廃されました。 又、公営住宅での障害者グループホームが住民の理解を得られず開設できない実態を本会議で指摘。障害者が共に地域で暮らせる社会づくりを要請。
![]() 1999年 二期目当選
高齢者・障害者にやさしいまち 介護の社会化と介護総合条例の制定を
1999年 二期目当選
高齢者・障害者にやさしいまち 介護の社会化と介護総合条例の制定を
議会も議員定数40名を36名に自ら削減し、二期目の選挙。3,247票の御支援を得て、引き続き20位で当選。議会毎の「まちづくりトーク」もこの年からスタート。 また、介護保険スタートを目前に「介護保険がやってきた」(演劇とディスカッション)、「誤解保険から介護保険へ」シンポジウムを開催。 本会議でも、市民参画による条例制定と在宅高齢者総合支援事業の制度化を要望。翌年、配食サービスが制度化されました。
![]() 2000年
命輝け第九コンサートを高槻で開催 図書館行政、地域に開く学校づくり へ具体的提言
2000年
命輝け第九コンサートを高槻で開催 図書館行政、地域に開く学校づくり へ具体的提言
1月に、障害者も共に参加する「第九」コンサートを高槻現代劇場大ホールで開催。 3月議会では行政評価、福祉施策の転換、環境政策、都市交通体系、図書館分館整備、学校読書活動など21世紀のまちづくりについて市長と論戦を交わしました。 また、地域教育協議会、学校評議員制度導入を提言。
![]() 2001年
ともに生きる社会 (まち) 多文化共生へ外国人ネットワークが設立、人権尊重の社会づくり条例、環境基本条例が制定
2001年
ともに生きる社会 (まち) 多文化共生へ外国人ネットワークが設立、人権尊重の社会づくり条例、環境基本条例が制定
2010年を最終年度とする高槻市新総合計画がスタート。人権尊重の社会づくり条例、環境基本条例も制定。
「市立養護学校存続を求める意見書」を提案
一方、「学校規模適正化等審議会」が市立養護学校 の廃校を前提にした答申を提案。6月議会で「存続を 求める意見書」の提案者となり、全会一致で採択しました。
電子自治体の推進を
また、電子自治体の推進を議会で具体的に提言。庁内文書の電子データ化とLAN構築、市のホームページへの審議会議事録や各種計画の情報公開、各種申請書のホームページからのダウンロードを実現させました。同時に、IT講習の推進と市民のパソコングループ支援、公民館でパソコンルーム開設を推進しました。
![]() 2002年
市民が主体のまちづくり 市民による「社会福祉法人・つながり」設立、新しい福祉運動の展開
2002年
市民が主体のまちづくり 市民による「社会福祉法人・つながり」設立、新しい福祉運動の展開
市民に広く呼びかけ、「社会福祉法人・つながり」を設立 (2002年11月、正式法人認可)。 2003年4月、知的障害者通所施設「サニースポット」が開所予定。市民が福祉を担う時代をつくりました。 議会では、「まちづくり条例」制定や、NPO支援、交通バリアフリー基本構想策定など多方面に渡って論戦を交わしました。